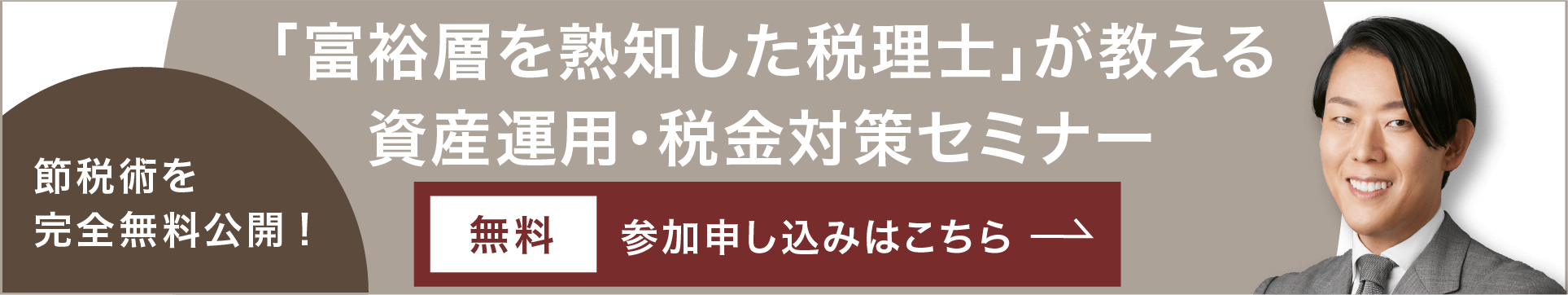年収が1億円以上あると、所得税や相続税は高額になります。「できるだけ納める税金を減らしたい」「資産を守りたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、年収1億円以上の高所得者向けの節税方法を紹介します。
税金ごとの具体的な節税方法や注意点について詳しく解説するため、税金対策を検討中の方は必見の内容です。税務に関する知識が深まれば、自身のケースに合った税金対策が見つかるでしょう。
年収1億円以上で高額になりやすい税金

年収が1億円以上ある高所得者の給料からは、実際にどれくらいの費用が差し引かれるのでしょうか。ここでは、高所得者の手取り金額や控除される税金を紹介します。高額になりやすい税金の種類や制度内容も解説するため、併せて確認しましょう。
年収ごとの手取り金額早見表
手取り金額とは、額面金額から税金や社会保険料を差し引いた金額です。年収別に手取り金額を確認できる早見表を作成しました。早見表と適用条件は以下の通りです。
| 年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り金額 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 約180万円 | 約1,635万円 | 約462万円 | 約2,721万円 |
| 6,000万円 | 約183万円 | 約2,093万円 | 約562万円 | 約3,160万円 |
| 7,000万円 | 約186万円 | 約2,551万円 | 約662万円 | 約3,600万円 |
| 8,000万円 | 約189万円 | 約3,009万円 | 約762万円 | 約4,039万円 |
| 9,000万円 | 約192万円 | 約3,467万円 | 約861万円 | 約4,478万円 |
| 1億円 | 約195万円 | 約3,922万円 | 約961万円 | 約4,917万円 |
【適用条件】
・会社員(雇用保険料含む)
・独身(配偶者、扶養親族なし)
・介護保険第2号被保険者に該当
・所得控除は基礎控除のみ
・健康保険料と厚生年金料は東京都の金額を適用
・千の位以下切り捨て
法人代表者の給与からは、雇用保険料は差し引かれません。また、住民税は前年の給与を元に計算するため、前年と年収が異なる場合は手取り金額にも差が生じます。上記の表は前年と年収が同じことが前提である点にご注意ください。
所得税は超過累進税率
所得税は超過累進課税が採用されています。超過累進課税とは、対象となる金額が増加し一定額を超えると、超えた部分に対して順次高い税率が課される制度です。年収1億円の場合、所得税率は最高値である45%が適用されます。所得税の速算表は以下の通りです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円以上695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円以上900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
(参考: 『所得税の税率|国税庁』/ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)
相続税が発生しやすい
相続税は、基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を上回る金額に対して課されます。超過累進課税が採用されており、課税遺産総額が多いほど税率も高くなります。相続税の速算表は以下の通りです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
最高税率は55%で、資産が多ければ税額も増えます。ただし、相続税の計算は複雑で、「遺産の金額×税率」で税額が決まるわけではありません。
(参考: 『相続税の税率|国税庁』/ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)
所得1億円以上は税負担が軽くなる現象も
高所得者は、所得税や相続税が高額になりやすい一方で、一部の税負担が軽くなる現象も生じます。富裕層の多くは労働の対価による報酬だけでなく、配当による利益も得ているためです。
株式投資や投資信託のような資産運用で得た利益は、配当所得に分類されます。配当所得の税率は20.315%で、給与所得に課される所得税率より低いため、実質的な投資家優遇制度といえるでしょう。
ただし、金融所得課税の見直しが実行される可能性がある点には注意が必要です。制度内容が見直されれば、今後配当所得の税負担が増えるかもしれません。
高所得者が知っておきたい所得税の節税方法

高所得者の給与から差し引かれる費用のうち、約8割を占める所得税を減額できれば、大きな節税効果が期待できます。高所得者におすすめの節税方法は主に4つです。自身のケースで適用できるものがあれば適宜導入し、手元に残る資金を増やしましょう。
各種控除を適用する
所得税の所得控除や税額控除を適用すれば、所得税額を減らせます。控除の一例は以下の通りです。
| 所得控除 | 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除 |
|---|---|
| 税額控除 | 配当控除、外国税額控除、政党等寄附金特別控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 |
控除できる金額が多くないケースもあるため、手続きに煩わしさを感じる方もいるかもしれません。しかし、税金対策は制度を上手に活用し、所得を減らす努力をコツコツと積み重ねることが大切です。
資産管理会社を設立する
資産管理会社とは、自身の資産を自分で管理するためのプライベートカンパニーです。高所得者にとって多くのメリットがあり、税金対策に適しています。主なメリットは以下の通りです。
・家族に所得を分散することで所得税を減らせる
・所得として生前に財産を分配すると、相続税の節税につながる
・所得税の最高税率より低い法人税率が課される
・経費として認められる対象範囲が広がる
・繰越控除できる期間が長くなる
税制優遇制度を利用する
NISAやiDeCoといった税制優遇制度を利用しながら資産運用するのも方法のひとつです。掛け金の全額が所得控除の対象で、配当所得が一定期間非課税といったメリットがあります。また、預貯金ではなく投資であるため、効率的に資産を運用してインフレリスクにも対応できます。各制度の概要は以下の通りです。
| 種類 | 税制面のメリットと概要 |
|---|---|
| iDeCo | ・掛け金を全額所得控除にできる ・運用益が非課税 ・年金を受け取る際にも控除を適用できる |
| NISA | ・配当金や譲渡益が一定期間非課税 ・新規投資額で上限は毎年120万円(つみたてNISAは毎年40万円) ・非課税期間は最長5年間(つみたてNISAは最長20年間) |
※2024年以降は新NISAに変更される
不動産投資を活用する
不動産投資は節税効果を期待できる投資方法です。不動産の取得費用を減価償却により損益通算できるため、所得を圧迫できます。
減価償却とは、固定資産の取得費用を耐用年数に応じて分配し、毎年少しずつ経費計上する会計手続きです。実際には初年度しか支出がなくても、耐用年数に該当する期間は減価償却分を経費として処理できます。経費が増えれば課税対象となる所得が減るため、所得税の節税に効果的です。
相続税を抑えるためにできる事前対策

基礎控除を上回る相続財産に対して税率10%~55%の税金がかかるため、保有資産が多い年収1億円以上の高所得者は、相続税も高額になる恐れがあります。相続税の税金対策は「財産を減らす」「評価額を下げる」「特例制度を利用する」の主に3つです。財産を受け取る相続人の税負担を軽減するためにも、税金対策を検討しましょう。
生前贈与で財産を渡しておく
生きている間に財産を渡しておくことで、相続財産を減額できるため、相続税の節税につながります。生前贈与の代表的な方法は以下の通りです。
・年間110万円までの基礎控除を利用し、暦年贈与で財産を少しずつ渡す
・住宅取得資金や子育て資金の一括贈与といった非課税制度を利用する
・2,500万円までの特別控除がある相続時精算課税制度を適用する
特に、相続時精算課税制度は控除額が大きいため、資産が多い方に適しています。2,500万円を超える財産を贈与しても、超過した分に対しては一律20%しか税金がかかりません。
「一時的に価値が下がっている」「将来的に価値が高騰しそう」といった土地や株式を保有している場合も有効です。贈与後に財産の価値が上がっても、相続税を計算する際には相続時精算課税制度適用時の評価額が適用されます。
生命保険の非課税枠を利用する
生命保険の非課税枠を利用するのも方法のひとつです。相続税の計算時に該当金額分を控除できます。非課税額は「500万円×法定相続人の数」です。例えば、法定相続人が3人いるケースは「500万円×3人=1,500万円」が非課税限度額になります。
また、生命保険金は遺留分の対象とならない点もポイントです。受取人に固有の権利が発生することから、他の法定相続人に遺留分を請求される心配がありません。自身の死後でも、財産を渡したい相手にしっかりと資産を譲れます。
相続税評価額を下げる
不動産経営は、所得税だけでなく相続税の節税にも効果的です。アパートやマンションを購入して第三者に賃貸すると、土地や建物の相続税評価額が下がります。
また、個人が使用する自宅や事業所を相続する際は、「小規模宅地等の特例」を適用可能です。特例を使用すると、相続税評価額を最大80%減額できます。建物の種類ごとの具体的な減額割合は以下の通りです。
| 相続開始前の利用区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330平方メートル | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400平方メートル | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 50% |
(参考: 『小規模宅地等の特例|国税庁』/ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm)
節税対策で気を付けたいポイント
税金対策には、納める税金を減らせて手元に残る資産を増やせるという大きなメリットがあります。ただし、闇雲に対策しても十分な恩恵を享受できないケースもあるため注意が必要です。
まずは、出費が増える場合がある点に気を付けましょう。「節税したい」という気持ちが先行すると、支出額が増えて自身の財産が減ります。限度額が決まっている節税制度も多いため、事前にしっかりと確認することが大切です。
また、税務署に脱税と判断されるとペナルティが発生するデメリットもあります。脱税とは「故意に税金を逃れる行為」です。税負担を軽減しようとするあまりに、個人的な買い物を経費にするといった行為は避けましょう。
ネイチャーグループは資産形成をトータルサポートします
適切に税金対策をしながら最大限の節税効果を享受するには、税務に関する専門知識が必要不可欠です。万が一、節税方法に誤りがあり税務署から脱税と見なされると、重加算税や懲役・罰金刑といった刑罰が科されます。税金対策に悩んだ際は、専門家に相談しましょう。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、国内外で相談・案件数累計1万件以上の実績を持つ国内最大級のコンサルファームです。税務や資産運用に精通した専門家が多数在籍しています。
確定申告の申告書作成から保有資産の向上に向けたコンサルティングまで、トータルサポートが可能です。税金対策をご検討中の方はぜひ一度ご相談ください。
まとめ

所得税や相続税に採用されているのは、超過累進課税です。年収1億円以上の高所得者は課税対象となる金額が増えるため、納める税額も増えます。自身のケースに合う節税対策があれば適宜導入し、手残り資産を増やしましょう。
税金対策をご検討中の方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。税務に関する豊富な知識と経験を持った税理士が、お客さまに最適なプランをご提案します。
資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。
お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。
豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。
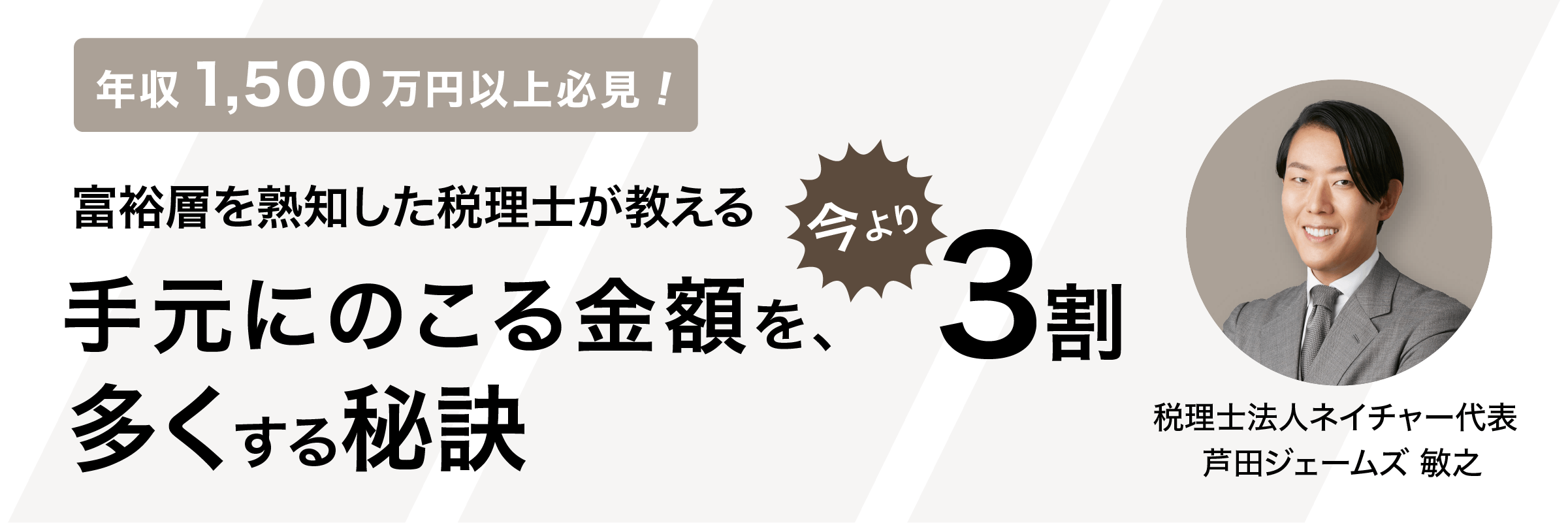
「富裕層であればあるほど税負担が高くて困る。」「所得税・法人税の対策をしたいが難しい。」などとお困りではありませんか?
ネイチャーグループでは、参加無料のオンラインセミナーを開催しています。メディアに多く出演している弊社ネイチャーグループ代表 芦田ジェームズ 敏之が登壇し、2023年度の税制改正に対応した節税術を無料公開いたします。ご自身の資産を残すために役立つ内容のため、是非ご参加ください。