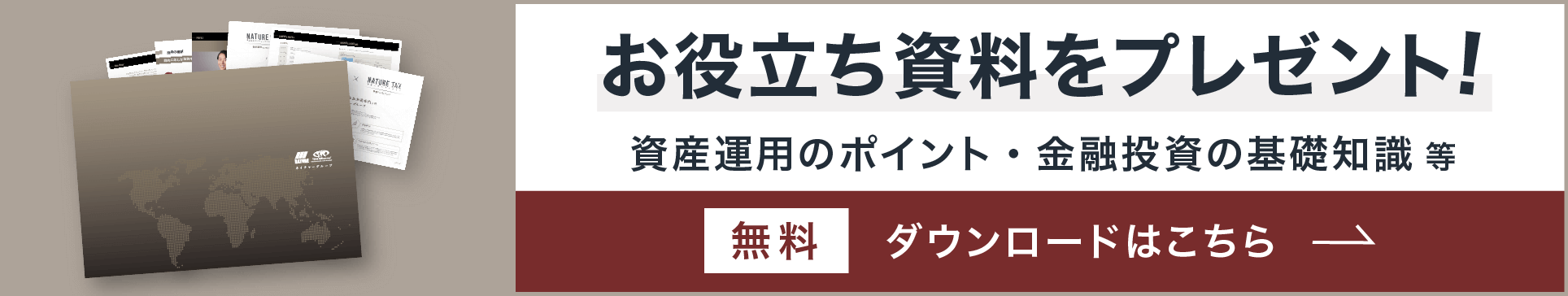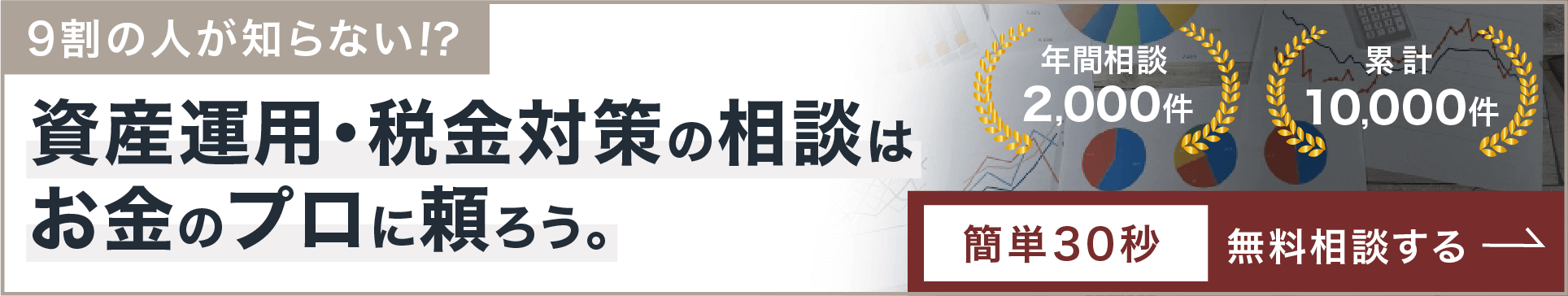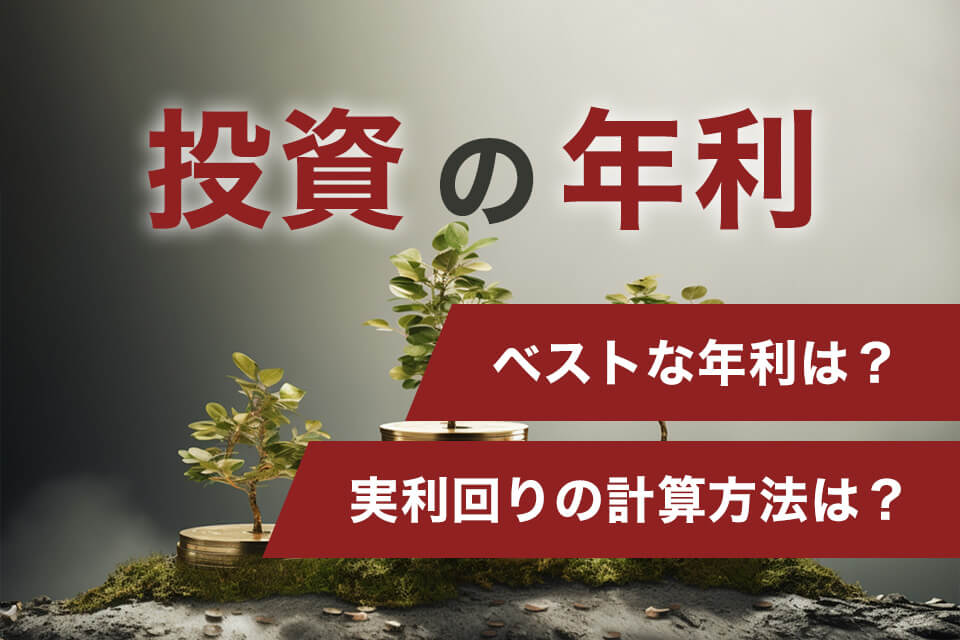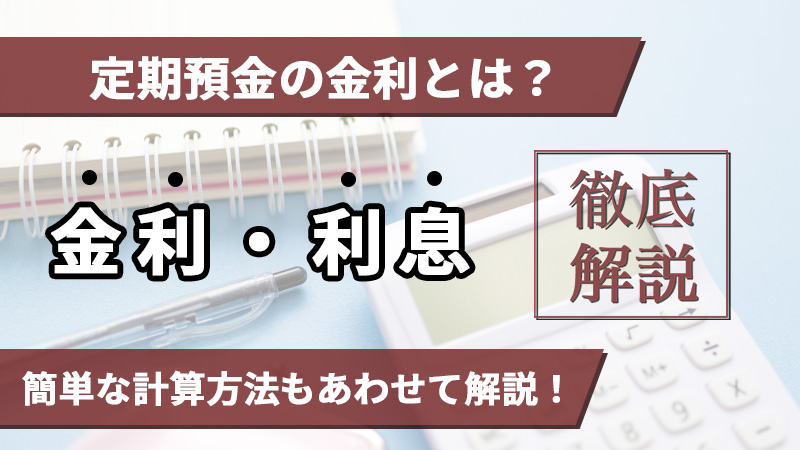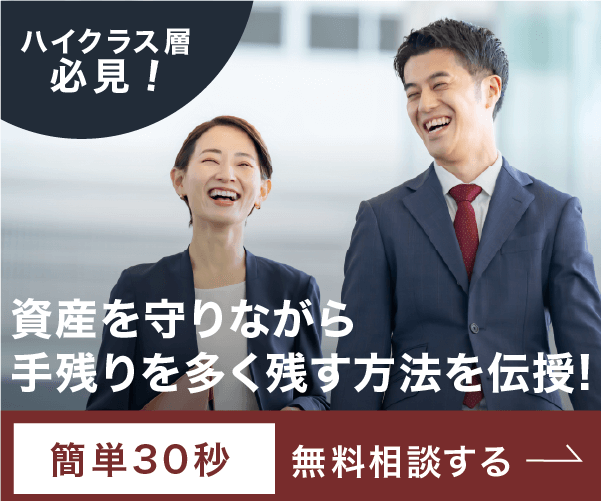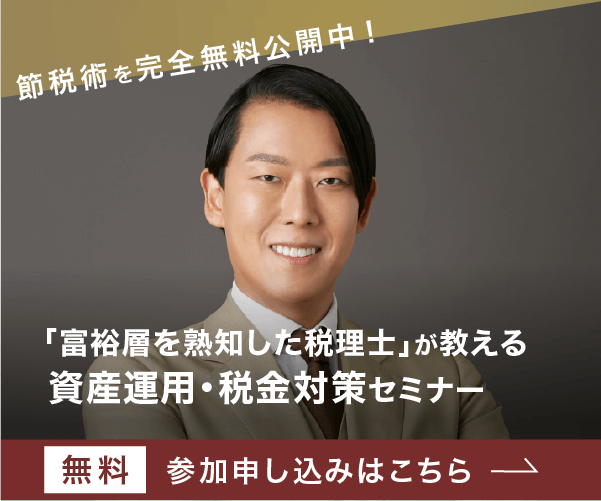![]() 2020年8月26日
2020年8月26日![]() 2024年4月30日資産運用
2024年4月30日資産運用
投資信託の手数料とは?手数料一覧と目安・コストを抑える方法を紹介

投資信託を実践する際には、運用会社や投資先で定められた手数料も考慮しなければなりません。複数の手数料が一律で決められているわけではないため、どのように計算すればよいか分からず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、投資信託における手数料の取り扱いについて詳しく解説します。計算方法を理解すると、実際に費やす金額を明確にしたりお手頃な信託先を見極めたりできるでしょう。投資信託の種類と価格差もあわせてご紹介します。
目次
投資信託でかかる手数料一覧・目安
投資信託を行う上で発生する手数料の割合は、投資する種類や会社によってさまざまです。よく見られる目安として以下の表を参考にしましょう。
|
手数料の種類 |
支払うタイミング |
割合の目安 |
|---|---|---|
|
購入時手数料 |
購入時 |
0〜3% |
|
信託報酬 |
保有期間中 |
0.5〜3% |
|
監査報酬 |
保有期間中 |
投資信託による |
|
売却委託手数料 |
保有期間中 |
1~3% |
|
信託財産留保額 |
解約時 |
0〜0.3% |
|
換金手数料 |
解約時 |
0.2〜0.3% |
手数料を無料とするケースもあるため、「なるべく負担額を上乗せしたくない」という方は手数料の割合を重視して選ぶことも有益な方法です。無料であればよいというわけではありませんが、複数の投資先から選択肢を絞る結果にもつながるでしょう。
手数料が高額な場合、損益のバランスによっては損失を生むリスクもあります。長期運用も想定しながら、保有から解約までにかかる手数料を明確にできると安心です。
投資信託の購入時にかかる手数料は購入時手数料

購入時手数料とは、投資信託を購入するとと同時に支払う手数料のことです。
投資家は、申し込みをするにあたって、投資金額の数%を手数料として支払う必要があります。
購入時手数料の割合は、販売会社によって異なるので明確な金額は断言できません。ただし、1〜3%ほどの割合が目安となります。
- 購入時手数料:50万円×0.03(3%)=1万5,000円
- 支払い総額:50万円+1万5,000円=51万5,000円
なお、ノーロード型の投資信託に投資する場合は、手数料がかかりません。
投資信託でかかる手数料の種類|保有期間中
続いて、投資信託の保有期間中にかかる手数料である「信託報酬」「監査報酬」「売却委託手数料」の3つを紹介します。
信託報酬
購入時手数料と同様に重要な要素が「信託報酬」です。管理手数料や運用管理費用ともいわれます。投資信託を購入してから売却するまでの期間、保有し続けるために支払う手数料です。
保有期間中は自動的に信託報酬が差し引かれています。手数料の割合は投資先によってさまざまです。低い場合は0.5%程度、高いケースでは3%程度と考えてよいでしょう。
購入時手数料と異なるのは、継続的に支払い続けなければならない点です。自ら支払うものではないため実感しにくいものの、割合が大きいほど損に感じるかもしれません。
利益が出ない場合は損失を増幅させるリスクもあるため、安く済ませる方法もおさえておきましょう。
監査報酬
監査報酬とは、公認会計士のような監査法人から監査を受けるにあたって支払う報酬のことを指します。監査費用とも呼ばれます。
投資信託を行うにあたって、公認会計士による監査が義務付けられています。
監査費用は、投資信託や依頼する監査法人によって異なるため、相談する際に費用面も確認しておきましょう。
売却委託手数料
売却委託手数料とは、投資信託側が株や債券などの商品を売買する際に発生する手数料です。
投資信託は、投資家から入ってきた資金を運用する、もしくは組み入れ資産の入れ替えなどを目的に売買をします。
投資家が売却委託手数料を支払うに至るまでの仕組みは以下の通りです。
- 投資信託会社が売買をする
- 売買先の証券会社に支払う手数料が発生する
- 信託財産から手数料が差し引かれる
- 基準価額が下がって投資家が間接的に負担する
なお、売買委託手数料は、資金の流出入の大きさや組み入れ資産の入れ替え頻度に応じて大きく異なります。
組み入れ資産の入れ替え頻度が多い投資信託なら、株や債券の売買高も大きくなり、その結果として売買委託手数料も嵩むでしょう。
投資信託でかかる手数料の種類|解約時
投資信託の手数料は、解約時にも発生します。ここからは、解約時に発生する2つの手数料を見ていきましょう。
信託財産留保額
投資信託を解約する際、解約手数料として「信託財産留保額」を定めているケースがあります。投資先によっては手数料無料とする場合もあるため、あらかじめ確認してから投資できると安心です。一般的には0.3%前後の割合となります。
信託財産留保額が上乗せされる場合、投資家自身が別途支払う必要はありません。基準価額をもとに、解約代金から差し引いた上で算出されるためです。投資信託を購入する際には、解約を想定して手数料の有無も把握しておきましょう。
換金手数料
換金手数料は、投資信託を換金・解約するときに負担する費用のことです。
主に証券会社や銀行といった販売会社に、解約時の事務手続きにおける対価として支払います。
なお、投資信託の販売会社によって、かからないこともあります。
投資信託で大きくかかる手数料の計算方法

手数料の仕組みが理解できると、実際の投資金額をもとにシミュレーションができます。複数の手数料を要するケースも多いため、運用する上でどのくらいの金額が必要になるのかを算出してみましょう。3種類の手数料における計算式に加え、具体例もあわせて解説します。
購入時手数料の計算シミュレーション
購入時手数料は、投資信託を購入するタイミングで支払います。
なお実際の投資では、税金も含めて計算されるため、10%の消費税も含めて計算してください。30万円の投資で2%の手数料を支払った場合、税込みの支払い額は以下の結果になります。
- 購入時手数料:30万円×0.02(手数料2%)=6,000円
- 税額:6,000円×0.1(10%)=600円
- 購入に必要な総額:30万円+6,000円+600円=30万6,600円
信託報酬の計算シミュレーション
信託報酬の具体的な金額を算出するためには、投資金額に加えて年単位の割合を明確にしなければなりません。
日割りでかかる手数料でもあるため、1日でいくら引かれるのか計算してみましょう。
以下は、2%の手数料で30万円を1年間運用した場合のシミュレーションです。
- 信託報酬:30万円×0.02(手数料2%)=6,000円
- 税額:6,000円×0.1(10%)=600円
- 1年間に要する手数料:6,600円
- 1日単位の手数料:6,600円÷365日=約18円
1日単位で見ると少額に思えるものの、利益が発生しなければ減額が続きます。1年後の損益が0円となった場合、以降は6,600円を差し引いた金額で運用するかたちになる仕組みを理解しておきましょう。
信託財産留保額の計算シミュレーション
信託財産留保額を計算する際は、解約するタイミングでの基準価額で算出します。一口あたりの価格を明確にし、保有している口数から総額を計算しましょう。解約時の保有総額100万円、信託財産留保額の割合が0.3%の取引を例にすると、以下のような計算方法になります。
信託財産留保額:100万円×0.003(0.3%)=3,000円
最終的に受け取る金額:100万円-3,000円=99万7,000円
信託報酬を安く抑える方法3つ

投資信託の手数料を安く抑えたいという方は多いでしょう。
そこで、投資信託の手数料を安く抑える方法を3つ紹介します。
購入時手数料無料(ノーロード型)の商品を選ぶ
「投資金額以外に支払金額を上乗せされるのがもったいない」と感じる方には、購入時手数料が無料の投資信託もおすすめです。
ノーロード投資信託(ノーロードファンド)ともいわれており、近年ではノーロードの仕組みを採用する運用会社も増加傾向にあります。
購入時手数料の支払いで押さえておきたいことは、手数料以上の利益を考慮する必要がある点です。3%の手数料が上乗せされる場合、投資信託の価値が3%以上上昇するまでは利益が発生しないことになります。
スタート時の手数料が不要になれば、このようなリスクを心配する必要もありません。損益の計算も簡略化しやすいため、初心者にもメリットが多いシステムといえるでしょう。
信託財産留保額がない商品を選ぶ
近年では、投資信託の解約時に発生する信託財産留保額が無料の商品も増加傾向にあります。信託財産留保額がなければ、解約時にかかる手数料はグッと抑えられるでしょう。
なお、信託財産留保額の金額は、投資信託の目論見書に記載されています。
また、ネット証券なら投資信託一覧ページにも掲載されていますので、信託財産留保額が発生しない商品はないか確認してみてください。
信託報酬の安い商品を選ぶ
インデックスファンドのような、信託報酬が安い商品を選ぶのも有効な戦略の一つです。
そもそもインデックスファンドとは、日経平均株価や東証株価指数などの指標と連動する形で運用される投資信託を指します。
ローリスク・ローリターンな性質を持っており、リスクを抑えながら運用したい方に適している方法です
インデックスファンドの特徴として、運用方針が明確になっているため、ファンドマネージャーの負担は大きくかかりません。そこで信託報酬が安く設定される傾向にあります。
一方、アクティブファンドは平均的なリターンを上回る利益を出せるよう運用される投資信託です。
手数料は、高めに設定されているため、運用する際は注意しましょう。
投資信託の手数料に関するよくある質問
では最後に、投資信託の手数料においてよくある質問を紹介します。
投資信託で手数料負けすることはありますか?
投資信託で手数料負けする可能性はあります。
信託報酬や監査報酬などの管理費用がかかるため、それを上回る利益が得られなければ、支払う費用のほうが大きくなり損をしてしまいます。
手数料負けを避けるためにも、まず手数料が低いもしくは無料の商品を選ぶことが大切です。
運用実績が蓄積されてきてから、手数料が高い商品にも挑戦してみるといいでしょう。商品選定の判断はとても重要です。
投資信託の手数料が無料になるのはなぜですか?
投資信託の手数料無料化は、収入減につながるリスクのある施策といえます。
しかし、アメリカの手数料無料化を皮切りに、シェアの拡大を目的としていると考えられます。投資家目線では、リスクが小さく最低限の資金で運用できるため、顧客の増加を期待できるでしょう。
また、AIの活用により、運用コストも減少していくと予想されます。そうした点も考えられる理由の一つです。
投資信託の手数料が気になるなら専門家に相談がおすすめ
投資信託のメリットは、100円や1万円など少額から始めやすい仕組みにあるといえます。多額の資金を用意できない方や、初めて投資に挑戦する方でも安心感を高められるでしょう。ただし、知識がない状態で始めることは賢明ではありません。
手数料のほかにも考慮しておきたい要素は多数あります。投資額が増えるほど損失リスクも高まるため、投資先を比較して決断する意識が必要です。「選択肢を間違えた」と後悔する結果を招かないよう、専門家に相談してアドバイスしてもらいましょう。
プロに投資信託を依頼すると、知識量に自信がない方でも失敗するリスクを軽減できます。資金が高額な方にとっても、精神的な負担を和らげるきっかけにもなるでしょう。
依頼先の選択に悩んでいる方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお任せください。
\投資信託よりも確実に増やす方法とは?/
まとめ:投資信託の手数料を安く抑える方法を知って効果的に運用しよう

投資信託を始める前に理解しておきたいことは、手数料の種類と割合の目安です。
信託先によっては、無料で投資できるケースもあるため、自分が望む投資信託を見つけて運用しましょう。リスクとリターンのバランスを考慮して選ぶ工程も重要です。
手数料の具体的な金額が気になる方は、シミュレーションして最終的な数字を算出してみましょう。
なお、「どのように進めればよいか分からない」という場合は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。将来のビジョンを見据えた資産運用について豊富な実績をもとにアドバイスします。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
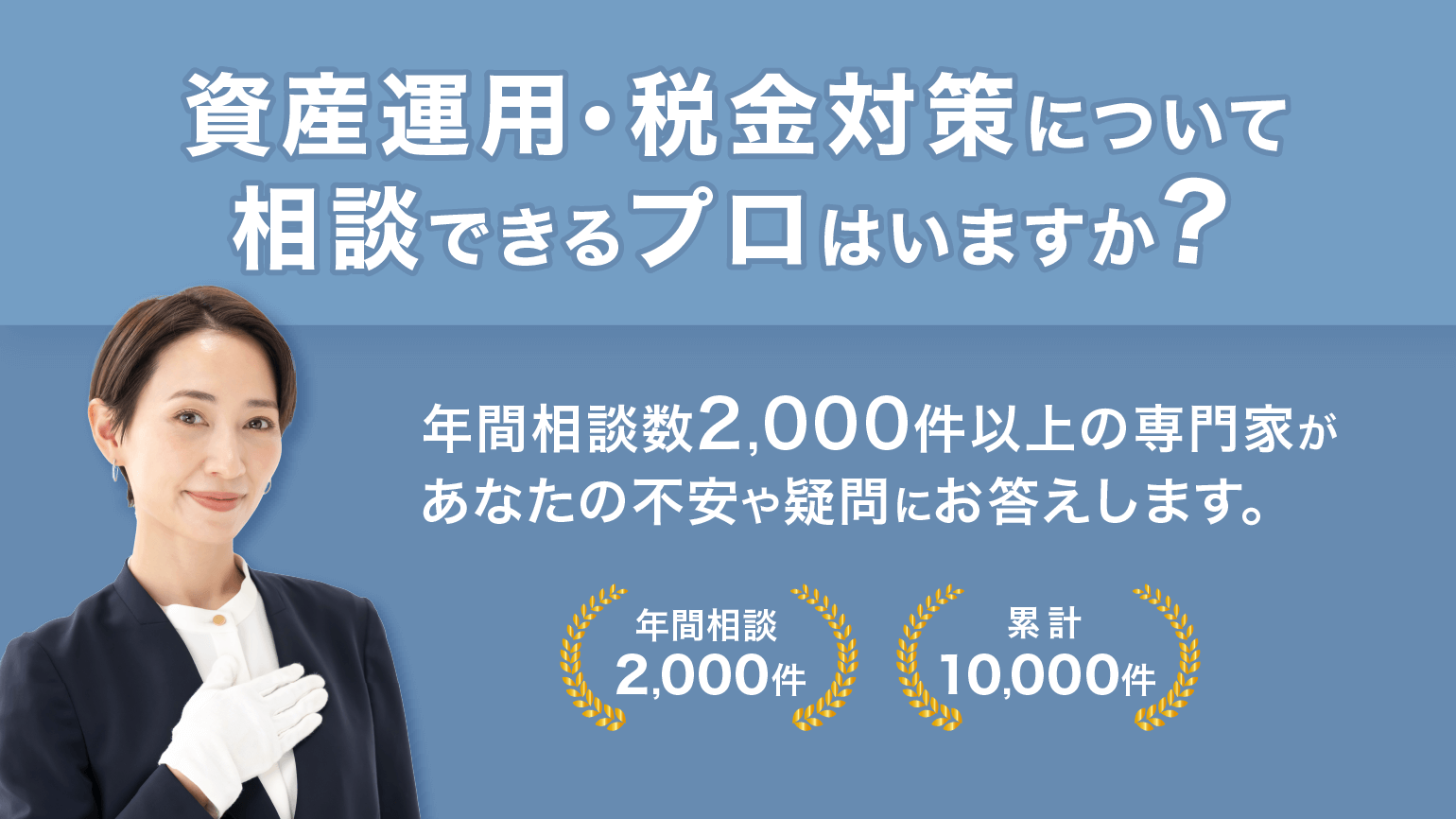
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用