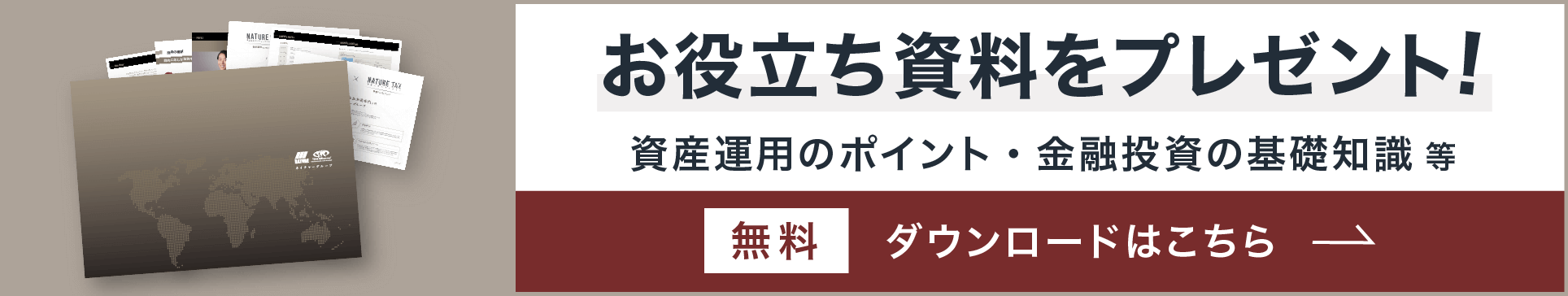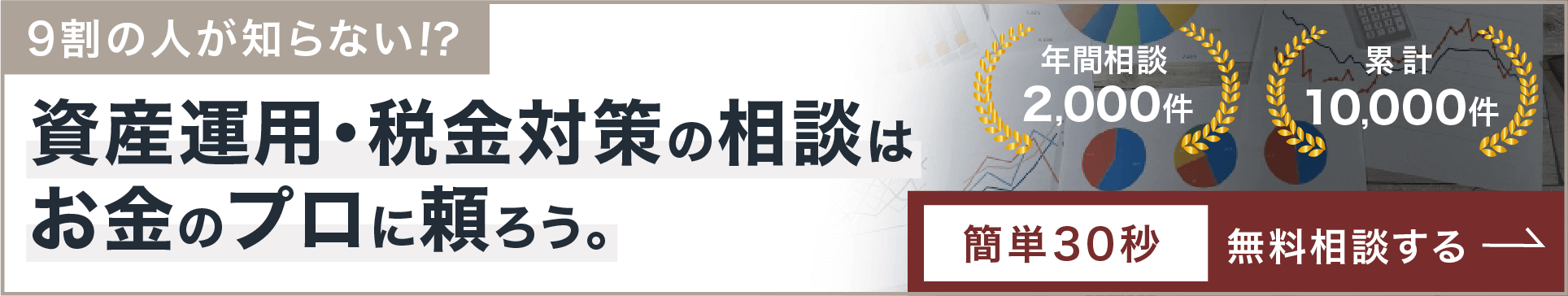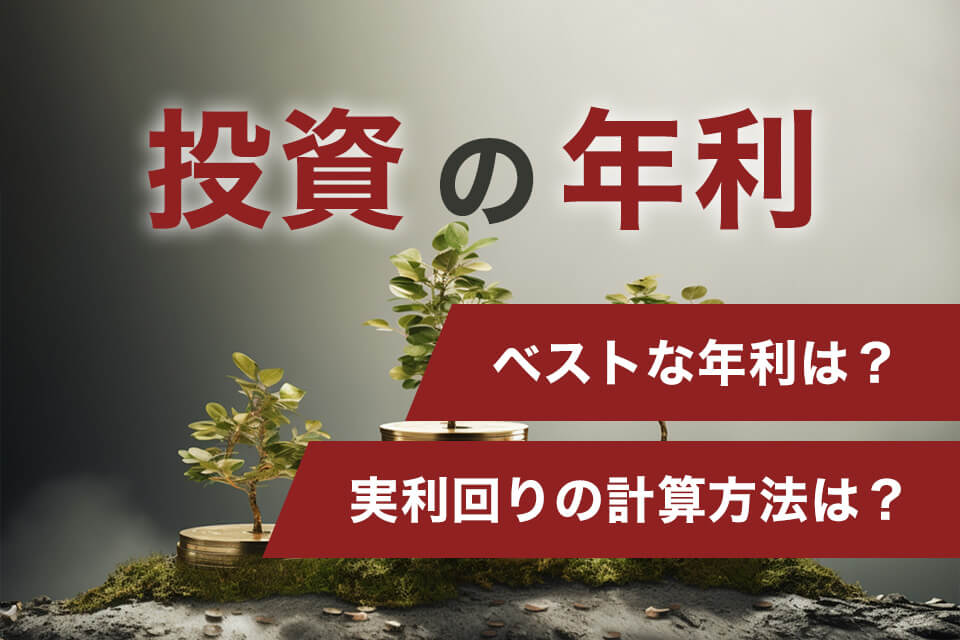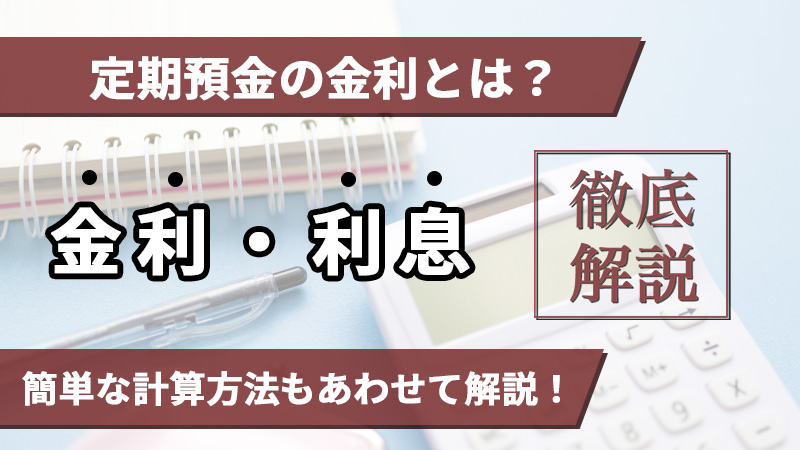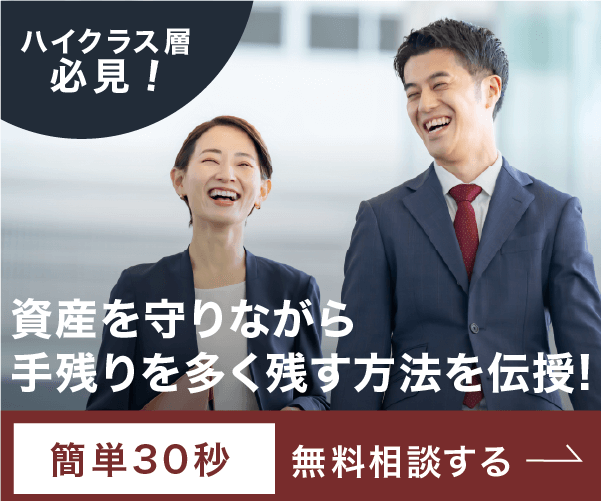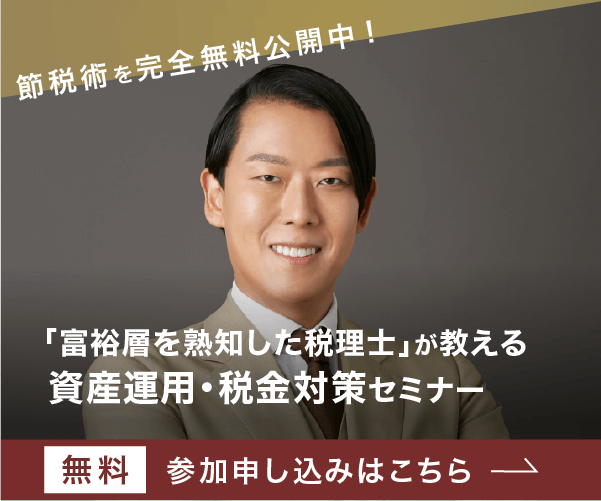![]() 2020年10月19日
2020年10月19日![]() 2025年4月24日資産運用
2025年4月24日資産運用
投資信託の利益確定はいつ?ベストなタイミングややり方を紹介

大きな利益が見込める資産運用方法のひとつに「投資信託」があります。興味のある方やこれから始める方、現在運用中の方の多くは、どのように利益を出すかが気がかりではないでしょうか。
投資信託で利益を出すには「利益確定」がキーワードです。利益を生むために必要な知識はいくらあっても損にはなりません。そこでこの記事では、投資信託の利益確定をするタイミングをご紹介します。注意点も解説するので、正しいタイミングで利益確定ができるでしょう。
目次
投資信託の利益確定とは?

投資開始時の元本よりも資産の価値が上昇し「含み益」になった状態で売却の決断をし、約定できたら「利益確定」「利益確定売り」をします。
利益を現金化する際には、投資を頼んだ投資信託会社に解約手続きの依頼をしましょう。手続きが済んだら数日で振り込まれます。海外に投資した場合は、時差があるため振り込まれるまでに国内の投資先よりも時間がかかるでしょう。
投資信託で保有資産のさらなる向上を望まれる方に、資産運用・税金対策に特化した個人専門のコンサルファームが正しい節税方法をお伝えしています。税務効果も考慮した資産運用について気になる方は、ぜひ一度ネイチャーグループへご相談ください。
\【期間限定】今だけAmazonギフトカードプレゼント!/
投資信託で利益確定・売却するタイミング

含み益が大幅に増加した時のみが利益確定の決断をするタイミングではありません。市場と自分の資産の状況をトータルで考え、客観的に全体のバランスを見る感覚で決断する必要があります。
利益確定のタイミングは、長年投資をしている方でも難しいと感じているかもしれません。ここであらためて基本的な判断基準を確認しましょう。
購入時より基準価額が値上がりした
投資資産を購入した価格よりも基準価額が上回ったときは、利益確定のタイミングです。これは分かりやすい基準なのですが、「もう少し待てば利益を増やせるのでは」と多くの投資家が悩む場面でしょう。
最高値になるまで待ってできるだけ多くの利益を増やすのではなく、確かな利益を得ることがポイントです。基準価額は急に下がる場合もあるので、リスクを避けるために少しでも利益が出たら利益確定の決断をするのはよい判断だといえます。
資産のバランスを整える(リバランスする)とき
資産の投資先・種類が複数に渡る投資家は、リスクを減らすための割合を決定して資産を投資します。しばらく続けていくと割合が崩れていくので、資産のバランスを再調整しなければなりません。これを「リバランス」といい、バランスが崩れた状態を元に戻す作業を指します。
リバランスのために一部の資産を解約しなければならないこともあるでしょう。その場合は、条件のよい資産を利益確定します。
別の商品を購入する資金集めのとき
投資中の商品が利益を出しにくい状態にあったり、他の商品の利益が見込めたりする状況だと、金融商品や投資先の変更を決断する投資家もいます。資金を用意できないときは、資金捻出のために利益確定しなければなりません。
解約時には、含み損だったり手数料・税金がかかったりします。また投資時にも手数料や税金がかかるので、別の商品に乗り換えるときは出費も考慮しましょう。
ライフイベントでまとまった資金が必要なとき
結婚、出産などでは結婚式の費用や出産費用などの出費が増加する、転職、介護などでは収入が減少することで家計が厳しくなる可能性があります。
ライフイベントの中には、上記のように資金が必要になるものも多いです。手元に現金を確保できている場合は特に問題ありませんが、不十分な場合は投資信託を売却して現金を確保するのも選択肢の1つです。
目標金額に到達したとき
投資信託を運用する際は目標を明確にしておくことも大切です。値上がりした時点で利益確定させるのも選択肢の1つですが、細かく利益確定させると手数料が増加し効率よく資産を増やすことができません。
運用開始時に目標を設定しておけば、目標を達成するまで利益確定をしないため、無駄な手数料を省くことで効率よく資産を増やせるでしょう。
投資信託で利益確定させて買い直すタイミング
金融商品を利益確定させて買い直すと、場合によっては損をします。損をしないためには利益確定させて買い直すのに最適なタイミングを把握しておくことが大切です。
利益確定させて買い直すタイミングについて詳しく見ていきましょう。
上昇トレンドが継続している
相場が上昇傾向にある場合、一度利益を確定させて買い直しても利益を得られる可能性が高いです。しかし、急に現金が必要といった特別な理由を除き、上昇トレンド中に利益を確定して買い直すことはおすすめしません。
その理由は、金融機関を保有していない空白期間が生じる、複数回取引することによって手数料の負担が増えて損をするためです。特別な理由がない限り、上昇トレンド中は金融商品の売買を繰り返さないほうが良いでしょう。
金融商品が一時的に高騰している
金融商品が一時的に高騰しているタイミングでは、一度利益を確定させて、下がってから買い戻すことで利益を増やせる可能性があります。
何らかのニュースによって一時的に金融商品の価格が高騰することも少なくありません。しかし、価格の高騰は一時的なものであることが多く、時間の経過とともに下がることが多いです。
もし、その金融商品を長期的に運用することを予定しているのであれば、一時的に価格が高騰した際に売却し、下がってから買い戻すことで手持ち資金を増やせるでしょう。
他に魅力的な金融商品が見つかった
金融商品の種類は1つだけではありません。他に利回りが期待できる、将来性や成長性が高い金融商品を見つけた場合は、利益を確定させて他の金融商品を買い直すのも選択肢の1つです。
保有中の金融商品の運用も続けたい場合、利益分のみを他の金融商品購入に充てるという選択肢もあります。
投資信託の利益確定で気をつけること

利益確定のタイミングを見極めて解約手続きに入る際は、いくつか事前に知っておきたいルールがあるので、項目をひとつずつ確認しましょう。利益確定だけではなく投資信託で資産運用をするときは、不要なトラブルを避けるためにもルールは把握しておく必要があります。
最終的な利益は分配金も含める
解約して受け取れる利益は、解約手続きをし、利益確定したときの総利益となります。総利益は商品を購入したときの元本と、購入時の基準価額より価値が上がった分の利益、投資信託会社の決算日に出る利益である「分配金」です。
利益の計算をするときは分配金も忘れずに含めます。分配金は行っている会社と行っていない会社があるので、利益確定前に確認しましょう。
また、分配金には「特別分配金」があり元本を切り崩して配当しているものもあります。この場合は元本が少なくなるので注意が必要です。
税金や手数料のことも忘れない
投資信託を解約するときには、実質的な手数料である「信託財産留保額」がかかります。多くの投資家から資金を集めて運用する投資信託では、ひとりの解約手数料をほかの投資家が負担するような状況にならないために設けられたシステムです。
解約時にかかる税金があることも考慮しましょう。売却益に約20%課税されるので、利益が低いとマイナスになるケースがあります。
一部だけを売却することも考える
含み損など将来的に不安な要素が出てきたら、投資資産すべてをコストカットしたいと思う投資家は多いでしょう。経験の浅い投資家がしやすい方法は、一部を売却に回し、残りの資産を運用し続ける「部分売り」がリスク軽減におすすめです。将来再度価値が上がったときに運用できます。
純資産の総額が減少したときには注意が必要
投資信託や資産運用会社の信用度である成績を確認するには、保有する株式や債券などの資産の時価総額「純資産総額」をチェックすると判別しやすいでしょう。純資産総額の増減は、投資家が商品を購入するかどうか、株や債券などの資産価格が上がるかどうかが影響します。
将来の展望が明るければ、純資産の総額が減少しただけで解約することは避けたほうが賢明です。しかし純資産総額の推移は、投資信託の成績を知る基準になります。減少したときは、なぜ資産価値が下がっているのかを把握することが大切です。
解約しても返金には時間がかかる
無事解約の手続きが終了しても、現金が振り込まれるまでタイムラグがあります。解約した資金の使い道がすでに決まっている場合は、必要な日までに受け取れるよう利益確定日を考えなければなりません。振り込まれるタイミングは商品や国によって異なるので、交付目論見書で確認しておきましょう。
解約できない期間(クローズド期間)もある
一部の投資信託には、解約をまったく受け付けない期間である「クローズド期間」を設けているものがあります。急激な一斉解約で資産が大量に流出し、資産運用が不安定になることを防ぐためのシステムです。安定的な運用をして質の高いサービスを提供するための期間でもあります。
これも目論見書に明記されていますが、必要なときに解約できないと資産運用計画に支障が出るでしょう。投資前にクローズド期間の有無を確認できると安心です。
長期投資(長期保有)をしたほうがよいこともある
投資信託で資産運用は、短期よりも長期のほうが収益率は高い傾向にあります。最初から長期計画での運用を考えたほうが、リスク回避のためにもよいでしょう。長期で資産保有を前提にしていれば、価値が下落しても慌てずに動向を注視できます。
短期では売買の回数が多くそのたびに手数料が発生するため、利益を多く出すことは難しいでしょう。マイナスになる可能性も考えられます。
確定申告が必要な場合がある
投資信託で利益が発生した場合、利益に対して譲渡所得税が課されます。譲渡所得は申告分離課税であるため、原則確定申告が必要です。
しかし、特定口座を開設して源泉徴収口座を選択している場合は、確定申告が不要です。特定口座を開設したものの源泉徴収なしの簡易申告口座を選択した場合または一般口座で取引している場合は、確定申告が必須なので忘れず確定申告をしましょう。
投資信託のこまめな利益確定は避ける
投資信託で利益が出た場合は、こまめに利益確定することは基本的におすすめしません。その理由は、投資信託は長期間運用することによって収益率が高くなる、短期間で売買を繰り返した場合は手数料の負担が大きくなるためです。
現金が必要な場合における利益確定はやむを得ませんが、長期保有を目的とする場合は、利益が出てもこまめに利益を確定することは避けましょう。
投資信託の利益の仕組みとは?

投資信託をはじめとした投資の最大の目的は、利益を出すことです。資産の運用中に資産価値が増減しても冷静な判断ができるように、そして利益率がよいときに利益確定ができるように仕組みを知ることから始めましょう。基本となる利益の仕組みの中から代表的な2つのポイントについて解説します。
投資信託の利益は2種類ある
投資信託の利益の種類は「売買差益」と「分配金」の2つです。「売買差益」は文字どおり、商品を買ったときの価格と売ったときの価格の差を指します。運用益が基準価額よりも高いときに売れば利益を得ることが可能です。しかし投資信託は元本保証がないので、低いときに売ると損になってしまいます。
「分配金」は、投資信託の運用で発生した収益から投資家へ配られるお金のことです。会社の決算日に資金を運用していれば分配されます。年1回の分配金もあれば、毎月1回の分配金がある商品などそれぞれです。分配金は運用成績に反映されるので、増減があるものだと認識しましょう。
基準価額が変動する原因は主に3つ
原因の1つ目は「運用損益」が挙げられます。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券といった資産を時価評価し、諸経費を引いた金額(純資産総額)を投資口数(受益権総口数)で割って算出します。運用がうまくいって価値が上昇すれば基準価額も上昇、運用に失敗して価値が下落すれば基準価格も下落するのです。
2つ目は「分配金の支払い」です。分配金の支払いが少ないほうが、最終利益は高くなります。発生した利益を元本に足して再度運用するので、純資産が増え時価評価が上がり、基準価額も上昇するためです。
3つ目の「運用費用の支払い」も、基準価額が下がる原因といえます。投資信託は各投資家の投資金額から支払われるので、純資産が減少してしまう仕組みです。
投資信託の利益率や利回りはどう算出する?

資産運用する上では、資産をどれだけ効率的に増やせるかが重要です。投資信託は「利益率」や「利回り」を算出する計算式で数値化できます。計算することにより、投資の将来設計を立てやすくなったり、商品の種類を選ぶ目安になったりするでしょう。ここでは「利益率」と「利回り」の相違点を確認しながら算出方法を解説します。
利益率を出す方法
投資信託で発生する、投資家への分配金の水準を計る指標が「利益率」です。「分配金利回り」とも呼ばれ、投資信託の年間収益に対する分配金の割合を示します。算出方法は以下のとおりです。
利益率(分配金利回り)=分配金の収益(分配金-税金-手数料)÷投資元本×100
分配金の収益は過去の実績である分配金累計額、投資元本は直近の月末基準価額で計算します。そのため基準価額に変化が生じれば実際に手にする利回りや、予想した利回りとは異なるでしょう。1年前の基準価額より直近の月末基準価額が下回れば、実質の利回りはマイナスになることもありえます。
利回りを出す方法
投資信託の利回りは、分配金に商品を売却したときに得られる売買差益を加えた、投資金額に対するすべての利益の割合を指します。投資信託でどれだけ儲けられるか(値上がり率)を確認できるので、どの銘柄を購入するかの目安にもなるでしょう。利回りは、投資信託のランキングで順位付けされる大切な指標です。
利回り=すべての収益(分配金+売買差益-税金-手数料)÷投資元本×100
上記の計算式で投資信託の利回りを算出できます。利回りは年間の総合収益率で、年利回りとも呼ばれることをあわせて覚えておきましょう。
投資信託で利益をさらに上げる方法

運用状況を確認し利益確定の決断をするだけではなく、積極的に利益を上げるコツがあります。資金力や投資環境など投資家によって相性が異なる方法なので、以下にあげる項目を確認し、できそうなことから始めましょう。利益をさらに上げるおすすめの4つの方法を詳しく解説します。
分配金を再投資する「複利投資」を行う
分配金がある投資信託では、年1回以上利益を定期的に手にできる可能性があります。このような分配金を投資家に渡さず、再び投資にまわす方法が複利投資(複利運用)です。
たとえば初年度の分配金を1年目の投資元本とあわせて、2年目の投資元本とします。1年目の分配金が足された元本なので、前年度より利益率が単利運用よりも高くなることが特徴です。
数年単位で複利運用すればするほど利益は膨らむので、長期投資に向いている投資信託では複利で投資をしたほうが、メリットが大きいといえます。
毎月購入する金額を一定化させる
投資信託の商品には、一度に資金を用意できなくても投資が可能な「積立投資」があります。毎月一定額をコツコツと積み立て成果をあげる方法なので、積立投資も長期投資向きです。
価値の変動があるため、そのときの価格がベストなのかどうかの判断は慣れた投資家でも難しいといわれています。決められた金額を自動的に積み立てるので、その判断のストレスを軽減できるでしょう。
また毎月一定額を積み立て、商品の価格の増減を平均化して購入できるので高掴みのリスクを抑える効果もあります。「ドルコスト平均法」という方法なら、価格が変動しがちな商品でも一定の金額で買い続けることにより、リスクを抑えられるでしょう。
節税対策ならNISA
NISAはNISA専用口座で投資する場合において利用できる税制優遇制度です。投資で得た利益は一定額まで税金がかからず、18歳以上であれば誰でも口座を開設できます。購入できる商品は、金融庁の許可がある株式や投資信託など決められているのが特徴です。
利益確定のときに引かれる税金がなくなり手数料のみになるので、収益額はその分高くなるのがメリットです。投資信託でも節税対策ができるNISAを投資の選択肢に入れてもよいでしょう。
2024年以降は以下のつみたて投資枠と成長投資枠の2つのいずれかを選択できます。
|
つみたて投資枠 |
成長投資枠 |
|
|---|---|---|
|
年間投資枠 |
120万円 |
240万円 |
|
非課税保有期間 |
無期限化 |
無期限化 |
|
非課税保有限度額(総枠) |
1,800万円 |
|
|
1,200万円(内数) |
||
|
口座開設期間 |
恒久化 |
恒久化 |
|
投資対象商品 |
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
上場株式・投資信託等 |
|
対象年齢 |
18歳以上 |
18歳以上 |
プロのアドバイスを受ける
資産運用などで多額の投資をするときに、ひとりで運用をすることに不安を抱いている方もいるのではないでしょうか。投資の経験があっても迷うので、初心者ならなおさらといえます。
資産運用について疑問点がある方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお任せください。不安を解消できるだけはなく、運用の無駄を省きさらに利益をあげるきっかけにもなるでしょう。
投資信託の利益確定させるタイミングの判断が難しいと感じたらネイチャーグループへ
投資信託で利益確定させるタイミングを誤った場合は、利益の最大化を図れずに損をする可能性があります。タイミングの判断が難しいと感じた場合は、専門家に相談することも選択肢の1つです。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、税務と資産運用に特化した、日本最大級のコンサルティングファームです。
国内外合わせて年間2,000件、累計1万件の圧倒的な相談実績から、皆さまに合ったご提案をします。資産運用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
\投資信託よりも確実に増やす方法とは?/
まとめ:目的に合ったタイミングで投資信託を利益確定させよう

投資信託で資産運用をするときは、利益確定の決断が重要です。利益をあげるために価値が高くなったときに解約できるか、タイミングの見極めが難しいでしょう。しかし注意したいポイントや投資信託の資産運用の仕組みを理解すると、利益を見込んだ利益確定ができます。
それでも不安なときは、冷静に価値変動の動向を見極められる第三者のアドバイスが効果的です。これから始める方から現在の運用を見直したい方まで、まずはネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)へご相談ください。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
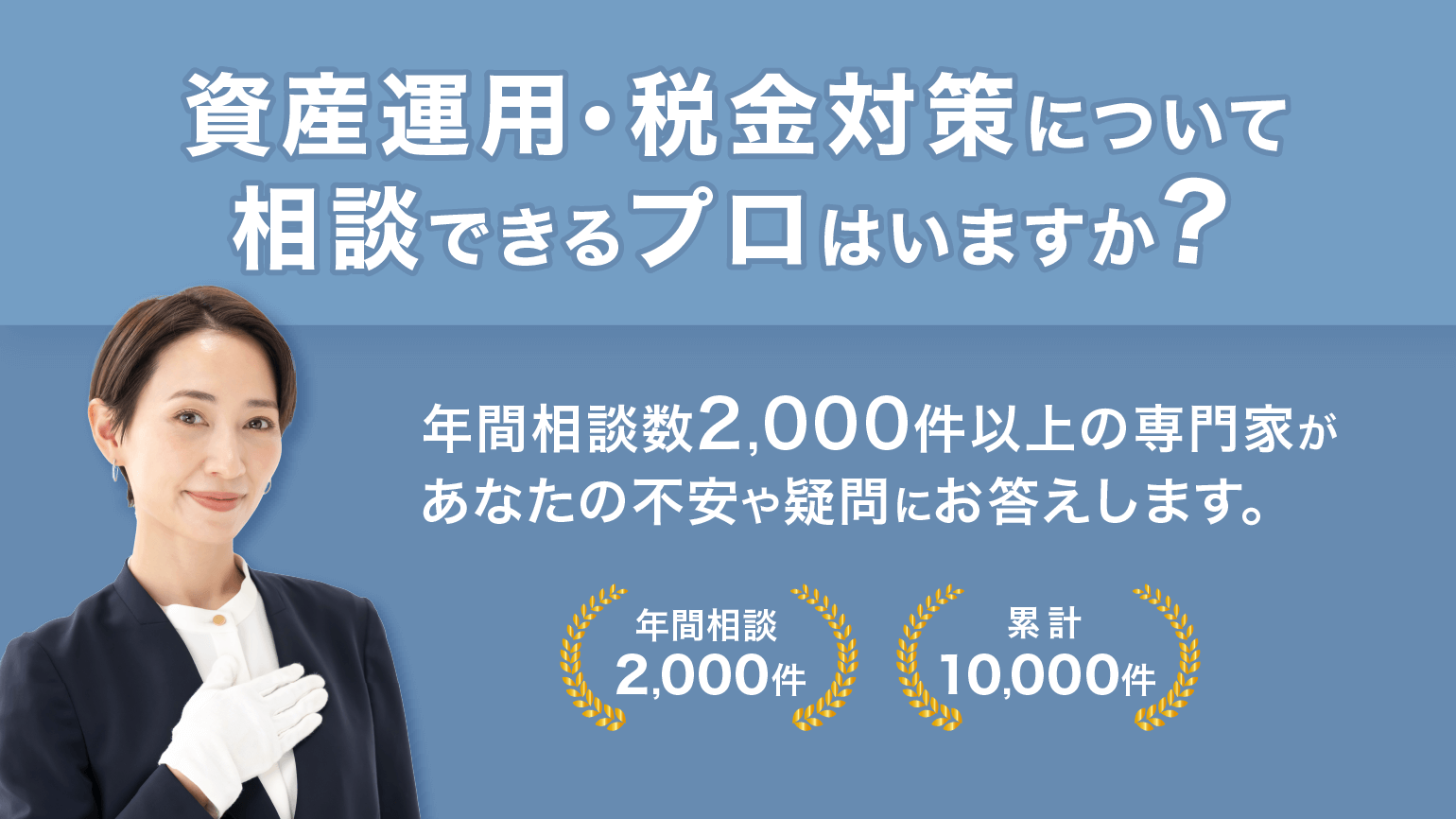
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用