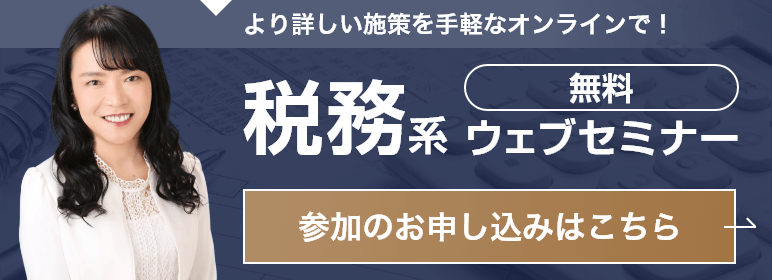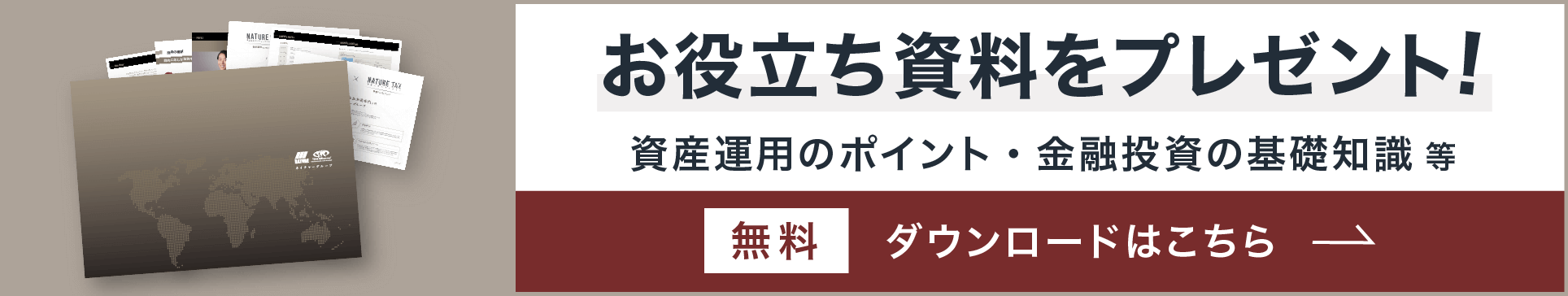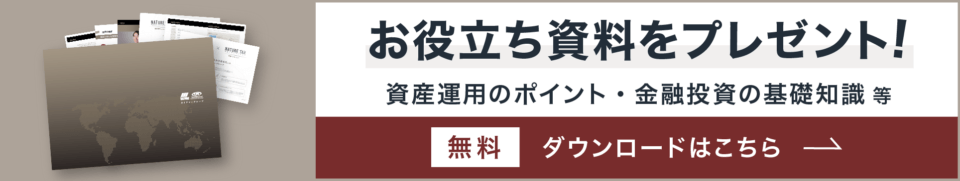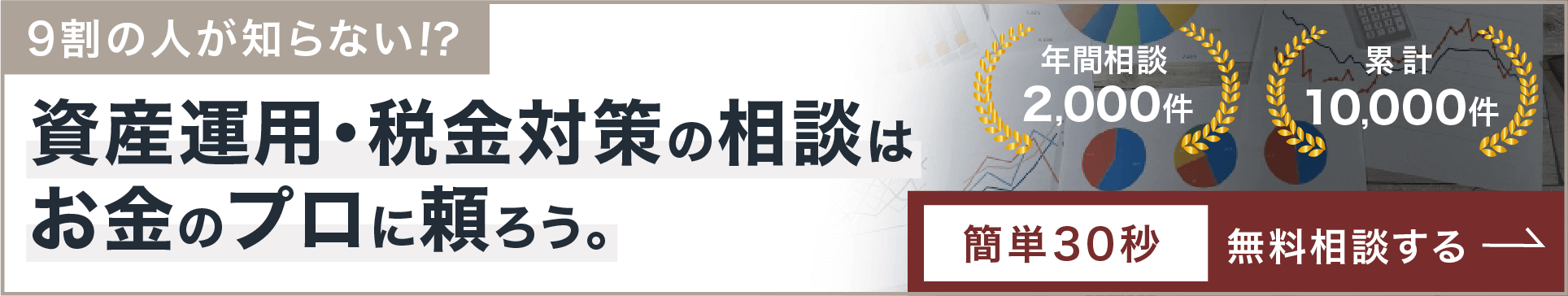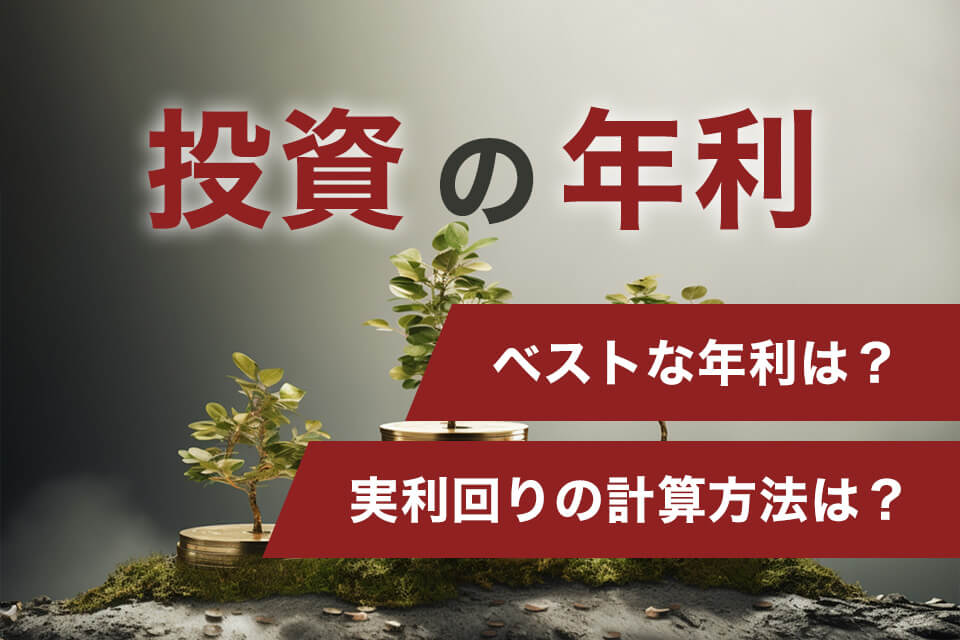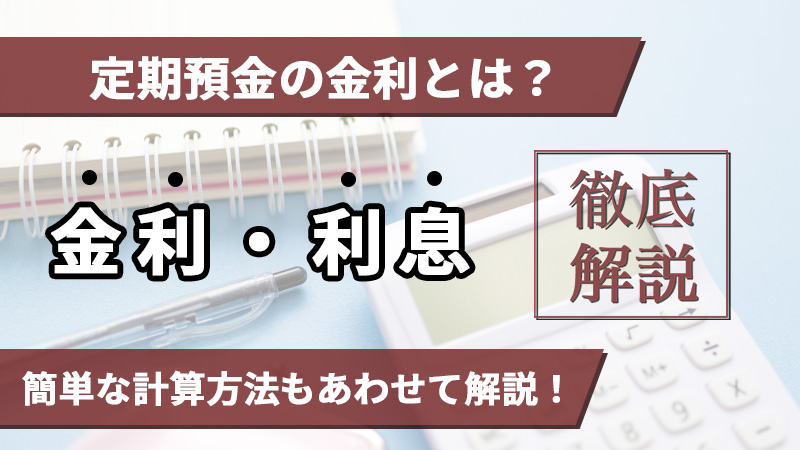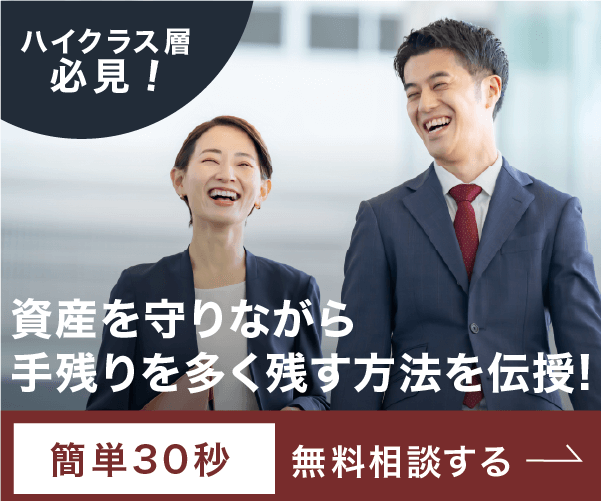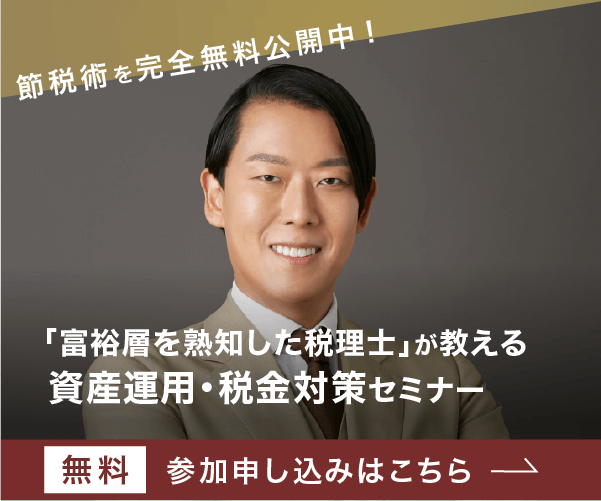![]() 2021年12月15日
2021年12月15日![]() 2021年12月17日
2021年12月17日
相続税と贈与税とは?税負担が軽くなるのは?疑問を全て解説!

相続税とは遺産を受け継いだ際にかかる税金です。それに対し、贈与税とは個人から財産を受け取った際にかかる税金のことを指します。どちらも一定額を超える価額に対してかかる税金ですが「違いが分からない」という方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続税と贈与税の相違点や特徴、税率について詳しく解説します。双方の仕組みや特徴を把握することで、自分に合った財産承継をするための判断材料になるでしょう。
目次
相続税と贈与税それぞれの特徴と税率

相続税と贈与税は、どちらも財産を受け取った際にかかる税金です。ここでは、相続税と贈与税の特徴について詳しく解説します。違いを把握すれば、どちらを選択すればいいか判断しやすくなるでしょう。基礎控除や課税対象、計算方法についても紹介します。
相続税の特徴と税率
相続税とは、相続や遺言によって遺産を受け継いだ際、遺産総額が基礎控除額を上回る場合にかかる税金です。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します。以下は税額を求める流れです。相続税の速算表で税率や控除額も確認しておきましょう。
【相続税額を計算する流れ】
| 1.正味課税遺産額を求める | ・正味課税遺産額=遺産総額-(債務・非課税財産など) |
|---|---|
| 2.課税価格を求める | ・相続時精算課税や相続開始前3年以内の財産などがあれば加える |
| 3.課税遺産総額を求める | ・課税遺産総額=課税価格-基礎控除額 |
| 4.相続人の法定相続分で按分し法定相続人ごとの税額を求める | 課税遺産総額×法定相続分×税率 |
| 5.相続税の総額を求める | 4で出した各相続人の税額を合計 |
| 6.各相続人・受贈者が納める実際の税額を求める | 相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額 |
相続税の速算表を用いる場合、税額は「法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額」で求められます。
【相続税の速算表】
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(参考: 『財産を相続したとき|国税庁』/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm)
贈与税の特徴と税率
贈与税は、個人から一定額を超える財産を受け取ったときにかかる税金です。贈与税の課税方式には暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、どちらかを選択する必要があります。
暦年課税では年間110万円の基礎控除があるため、年間110万円以内の贈与に贈与税はかかりません。暦年課税の税率には一般税率と特例税率があります。税額の計算式と速算表を以下にまとめました。
| 贈与税額=1年間に受けた財産の合計価額-基礎控除110万円×税率-控除額 |
【一般税率の速算表】
要件:特例贈与財産用に該当しない贈与に対して用いられる
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例税率の速算表】
要件:直系尊属(父母・祖父母)から20歳以上(贈与があった年の1月1日時点)子・孫などへの贈与に対して用いられる
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
(参考: 『贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)
相続時精算課税では累計2,500万円までの贈与税の特別控除がありますが、相続時に相続財産に加えられて相続税の課税対象になります。また、一度相続時精算課税を選ぶと同じ贈与者からの贈与について暦年課税は利用できません。慎重に検討した上で決定しましょう。
相続税と贈与税はどちらのほうが高い?
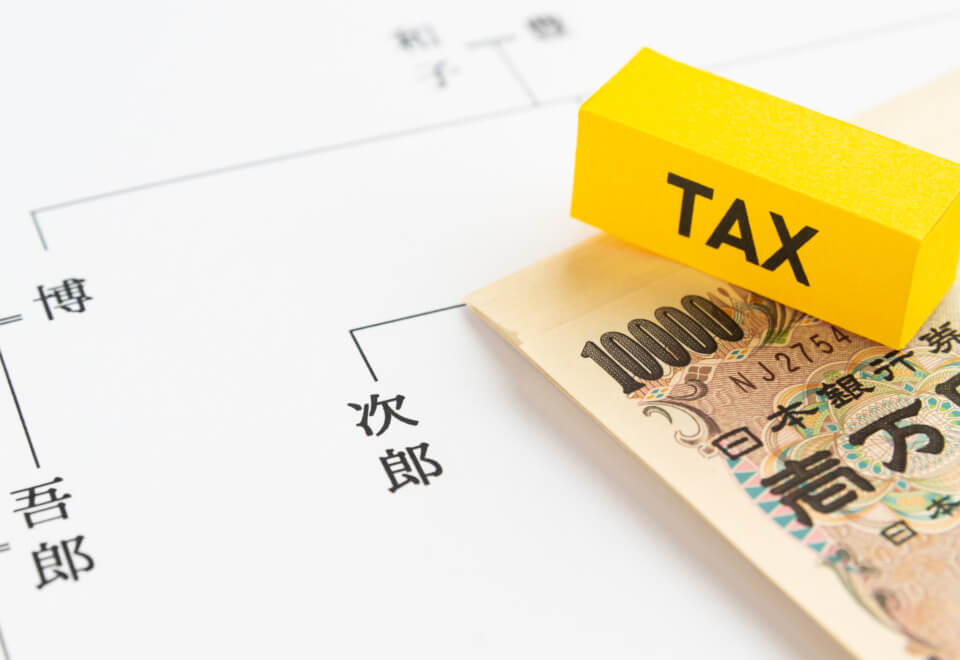
相続税と贈与税はその特性上、比較されることの多い税金です。「贈与税のほうが高い」と認識している方もいるかもしれません。そこで、ここでは贈与税と相続税の税率を比較しながら検証します。世間で贈与税のほうが高いと思われている理由についても把握しましょう。
税率だけを見れば贈与税のほうが高く思える
以下の表に贈与税率と相続税率をまとめました。税率だけを見ると、贈与税のほうが課税対象額に対する税率が高いことが分かります。
| 基礎控除後の課税価格 | 贈与税率(※) | 法定相続分に応じた取得金額 | 相続税率 |
|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 1,000万円以下 | 10% |
| 400万円以下 | 15% | 3,000万円以下 | 15% |
| 600万円以下 | 20% | 5,000万円以下 | 20% |
| 1,000万円以下 | 30% | 1億円以下 | 30% |
| 1,500万円以下 | 40% | 2億円以下 | 40% |
| 3,000万円以下 | 45% | 3億円以下 | 45% |
| 4,500万円以下 | 50% | 6億円以下 | 50% |
| 4,500万円超 | 55% | 6億円超 | 55% |
※暦年課税における20歳以上の受贈者を対象にした特例税率を用いています。
例えば、1,000万円の課税価格に対する贈与税率が30%であるのに対し、相続税率は10%です。5,000万円の課税価格に対する贈与税率は55%、相続税率は20%と大きな差があります。
しかし、実際には財産の額や種類、贈与税の非課税制度などの利用によっても変わります。また、贈与であれば複数回に分けての分割が可能です。暦年課税を選択した場合、年間110万円以内で贈与すれば贈与税はかかりません。一概に「相続税のほうが得」とはいえないでしょう。
一般的に贈与税が高いといわれている理由
世間では、相続税よりも贈与税のほうが高いという認識があります。それは、相続税を納める人が少ないことも理由のひとつかもしれません。
国税庁の資料によると、令和元年の被相続人数(死亡者数)は138万1,093人、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は11万5,267人です。実際に相続税を納めた人の割合はおよそ8.3%になり、全体として少数であることが分かります。
相続税を納める予定がない場合は、贈与税を納めて贈与を受けるメリットは限定的といえるでしょう。一方で相続税を納めることが想定される場合は、生前贈与を受けたほうが相続対策になることもあります。
(参考: 『令和元年分相続税の申告事績の概要』/https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf)
生前贈与は遺産相続よりも有利か│パターン別計算例と比較

同じ財産を受け取る場合、生前贈与と遺産相続はどちらが有利か気になる方もいるでしょう。そこで、ここからは相続税額が生前贈与の有無や贈与額、贈与期間などによってどのように変化するか計算例を比較します。なお結果はあくまでも一例です。財産状況やその他の条件によっても変わります。
暦年課税の基礎控除額内で贈与を受けた場合
ここでは暦年課税の基礎控除額内で10年間贈与を受けた後に相続した場合と、生前贈与なしで遺産相続した場合を設定します。前提条件は以下の通りです。
【前提条件】
| ・課税価格:3億円 ・受贈者及び相続人:子2人 ・贈与税は暦年課税を選択する ・法定相続分で相続する |
・10年間で子2人がそれぞれ年間110万円(合計2,200万円)の贈与を受けたときの贈与税
贈与税の暦年課税では、年間110万円の基礎控除があります。従って10年間贈与を受けた場合でも贈与税はかかりません。※実際は、毎年同額の贈与を続けると定期贈与とみなされ、相続税の課税対象になることがあります。
・10年間の贈与を受けた後の相続税額
総額2,200万円を生前贈与で受け取っているため、残りの2億7,800万円を子2人で相続します。以下は計算過程と子1人あたりの相続税額を算出した結果です。
| 課税遺産総額 | 2億7,800万円-(3,000万円+600万円×2人)=2億3,600万円 |
|---|---|
| 法定相続人ごとの税額 | 2億3,600万円×1/2=1億1,800万円 1億1,800万円×40%-1,700万円=3,020万円 |
| 相続税の総額 | 3,020万円×2人=6,040万円 |
| 子1人あたりの相続税額 | 3,020万円 |
・3億円の全てを遺産相続した場合の相続税
以下は生前贈与なしで3億円を子2人で相続した場合の相続税額を算出した結果です。
| 課税遺産総額 | 3億円-(3,000万円+600万円×2人)=2億5,800万円 |
|---|---|
| 法定相続人ごとの税額 | 2億5,800万円×1/2=1億2,900万円 1億2,900万円×40%-1,700万円=3,460万円 |
| 相続税の総額 | 3,460万円×2人=6,920万円 |
| 子1人あたりの相続税額 | 3,460万円 |
比較すると、子1人あたりの相続税の差額は440万円です。このケースでは、暦年課税の基礎控除額内で生前贈与を続けることで、相続税額を軽減できることが分かります。
生前贈与で贈与税を納めた場合
ここでは、暦年課税の基礎控除額を超えて贈与を受け10年間贈与税を納め続けた場合と、贈与を受けずに相続した場合の納税額を比較します。
【前提条件】
| ・課税価格:3億円 ・受贈者及び相続人:子2人(20歳以上) ・親(配偶者なし)からの贈与 ・贈与税は暦年課税(特例税率) ・法定相続分で相続する |
・1年間で子2人がそれぞれ500万円の贈与を10年間(計1億円)受けたときの贈与税
まず、1年間の贈与税を計算し、10年間の贈与税額を算出します。以下は計算結果です。なお、親からの贈与は特例税率に該当します。
| 基礎控除後の課税価格 | 500万円-110万円=390万円 |
|---|---|
| 1年あたりの贈与税(特例税率で計算) | 390万円×15%-10万円=48万5,000円 |
| 10年間の贈与税の合計(子1人あたり) | 48万5,000円×10年間=485万円 |
・10年間贈与税を納めた後の相続税額
総額1億円を生前贈与で受け取っているため、残りの2億円を子2人で相続します。
| 課税遺産総額 | 2億円-(3,000万円+600万円×2人)=1億5,800万円 |
|---|---|
| 法定相続人ごとの税額 | 1億5,800万円×1/2=7,900万円 7,900万円×30%-700万円=1,670万円 |
| 相続税の総額 | 1,670万円×2人=3,340万円 |
| 子1人あたりの相続税額 | 1,670万円 |
| 10年間の贈与税額と相続税額の合計(子1人あたり) | 485万円+1,670万円=2,155万円 |
・3億円の全てを遺産相続した場合の相続税額
生前贈与は受けずに子2人で3億円を相続した場合の相続税額は以下の通りです。
| 課税遺産総額 | 3億円-(3,000万円+600万円×2人)=2億5,800万円 |
|---|---|
| 法定相続人ごとの税額 | 2億5,800万円×1/2=1億2,900万円 1億2,900万円×40%-1,700万円=3,460万円 |
| 相続税の総額 | 3,460万円×2人=6,920万円 |
| 子1人あたりの相続税額 | 3,460万円 |
全てを遺産相続した場合と、生前贈与を受け贈与税と相続税を納めた場合とを比べると、子1人が納める税額に1,305万円の差が生じます。このケースでは、贈与税を納めた場合でも相続税額を軽減できることが分かりました。
一度にまとまった金額の生前贈与を受けた場合
ここでは、分割ではなく一度でまとまった金額の贈与を受けた後に相続した場合と、贈与を受けずに相続した場合の納税額を比較します。
【前提条件】
| ・課税価格:3億円 ・受贈者及び相続人:子2人(20歳以上) ・親(配偶者なし)からの贈与 ・贈与税は暦年課税(特例税率) ・法定相続分で相続する |
・子2人が1年間で5,000万円ずつ贈与を受けたときの贈与税額
| 基礎控除後の課税価格 | 5,000万円-110万円=4,890万円 |
|---|---|
| 子1人あたりの贈与税(特例税率で計算) | 4,890万円×55%-640万円=2,049万5,000円 |
・上記の贈与後に相続した場合
総額1億円を受け取っており、残りの2億円を子2人で相続します。贈与税額と相続税額の合計は以下の通りです。
| 課税遺産総額 | 2億円-(3,000万円+600万円×2人)=1億5,800万円 |
|---|---|
| 法定相続人ごとの税額 | 1億5,800万円×1/2=7,900万円 7,900万円×30%-700万円=1,670万円 |
| 相続税の総額 | 1,670万円×2人=3,340万円 |
| 子1人あたりの相続税額 | 1,670万円 |
| 贈与税額と相続税額の合計(子1人あたり) | 2,049万5,000円+1,670万円=3,719万5,000円 |
・3億円の全てを遺産相続した場合の相続税額
生前贈与は受けずに子2人で3億円を相続した場合の相続税額は以下の通りです。
| 課税遺産総額 | 3億円-(3,000万円+600万円×2人)=2億5,800万円 |
|---|---|
| 法定相続人ごとの税額 | 2億5,800万円×1/2=1億2,900万円 1億2,900万円×40%-1,700万円=3,460万円 |
| 相続税の総額 | 3,460万円×2人=6,920万円 |
| 子1人あたりの相続税額 | 3,460万円 |
一度に1人5,000万円の贈与を受けた後(合計1億円)に相続した場合は、3億円の全てを遺産相続した場合に比べ259万5,000円の税負担が増す結果になりました。このケースでは、生前贈与しても相続税対策という観点からは効果を得られなかったといえるでしょう。
生前贈与で相続税や贈与税対策をする際の注意点
「生前贈与したほうが税金を減らせるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、そうとは限りません。所有財産の種類や家族構成など複数の要素が関係するからです。以下のケースでは、生前贈与によって税負担を減らす効果を得やすいと考えられます。
・基礎控除額内の暦年贈与を続け、相続財産の削減ができた場合
・低い税率内に収まる金額で贈与を続け、相続財産の削減ができた場合
なお、相続税には「3,000万円+(600万円×相続人数)」の基礎控除があるため、遺産総額が基礎控除を超えない場合は、相続税対策のために生前贈与する必要はないといえるでしょう。
知っておきたい|相続税や贈与税で使える控除や特例制度

相続税や贈与税には、さまざまな控除や特例が設けられています。これらを利用すると、納税額を大幅に減らすことも可能です。ただし、誰もが利用できるわけではなく、それぞれに細かな要件が定められています。どのような制度があり、自分があてはまる制度があるかを事前に確認しておきましょう。
相続税の主な控除や特例制度
相続税は受け継ぐ財産が多くなるほど高額になりますが、以下のような控除や特例制度があります。税金対策のためにも、利用できる制度がないか把握しておきましょう。
【相続税の主な税額控除や特例制度】
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 暦年課税に係る贈与税額控除 | ・相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受け、贈与税を納めた相続人は相続税から贈与税分が控除される |
| 相続税の配偶者控除 | ・被相続人と法律上婚姻関係にある人が受けられる控除 ・1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のうち、いずれか高額なほうの価額が控除される |
| 未成年者控除 | ・20歳未満の法定相続人に対して適用される控除 【控除額】 ・10万円×満20歳までの年数分 |
| 障害者控除 | ・障害者の法定相続人に対して適用される控除 【控除額】 ・一般障害者:10万円×85歳までになるまでの年数 ・特別障害者:20万円×85歳までになるまでの年数 |
| 相次相続控除 | ・過去10年の間に被相続人が財産を相続し、相続税を納めていた場合に適用を受けられる |
| 小規模宅地等の特例 | ・土地・建物の面積など一定の要件を満たした上で、相続や遺贈により取得した同居の親族などに適用される特例 ・土地の評価額を最大80%減額できる |
贈与税の主な控除や特例制度
贈与税には、状況に応じて利用できる控除や特例制度があります。要件を満たしていれば、贈与税を非課税にすることも可能です。どのような制度があるかを確認して、贈与税対策を検討しましょう。
【贈与税の主な控除・非課税制度】
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 暦年贈与における基礎控除 | ・年間110万円までは贈与税がかからない |
| 相続時精算課税制度 | ・累計2,500万円までは贈与税がかからない ・相続時には相続財産に加えて課税対象となる |
| 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 | ・婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用の不動産または居住用不動産を取得するための資金の贈与を受けた場合、最大2,000万円までが控除される(基礎控除110万円を含めると2,100万円) |
| 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 | ・直系尊属から住宅購入などを目的とした資金を贈与された場合、最大3,000万円まで非課税となる ・非課税限度額は契約日などによって異なる。 |
| 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 | ・直系尊属から教育資金に充てる資金を贈与された場合、最大1,500万円まで非課税になる ・受贈者は30歳未満であることなどが要件 |
| 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 | ・直系尊属から結婚・子育てに充てる資金を贈与された場合、最大1,000万円まで非課税になる ・受贈者は20歳以上50歳未満であることなどが要件 |
相続税や贈与税対策のことなら|税理士への相談がベスト!
「効果的な相続税や贈与税対策をしたい」と検討している方は、専門知識を持った税理士への相談をおすすめします。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、資産運用と相続対策を専門とした税理士法人です。
日本の相続税の最高税率は55%と非常に高く、資産が大きくなるほど税負担は重くなります。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、納税額のシミュレーションをしながら、お客様に合った最良のご提案が可能です。次世代へスムーズに財産を渡すために、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ

相続税と贈与税は、どちらも一定額を超える財産を受け取る際にかかる税金です。税率だけを見ると贈与税のほうが高く見えますが、一概にそうとはいえません。控除や特例制度を利用しながら、状況に合った相続対策を計画的に進めることがポイントといえます。
相続税・贈与税対策を検討されている方は、ぜひネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお任せください。お客様の資産状況を踏まえて、よりよい税金対策をご提案します。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
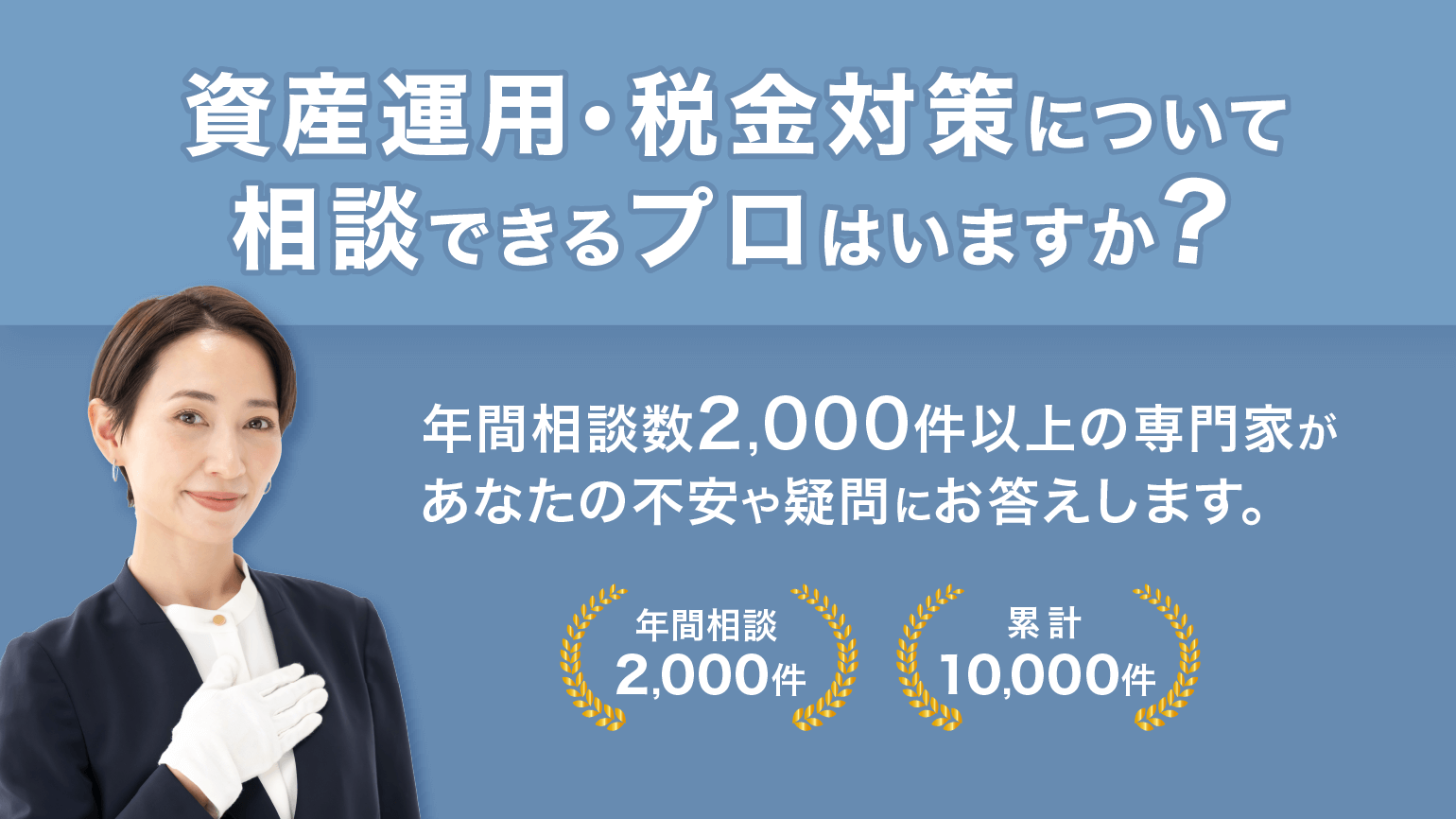
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用