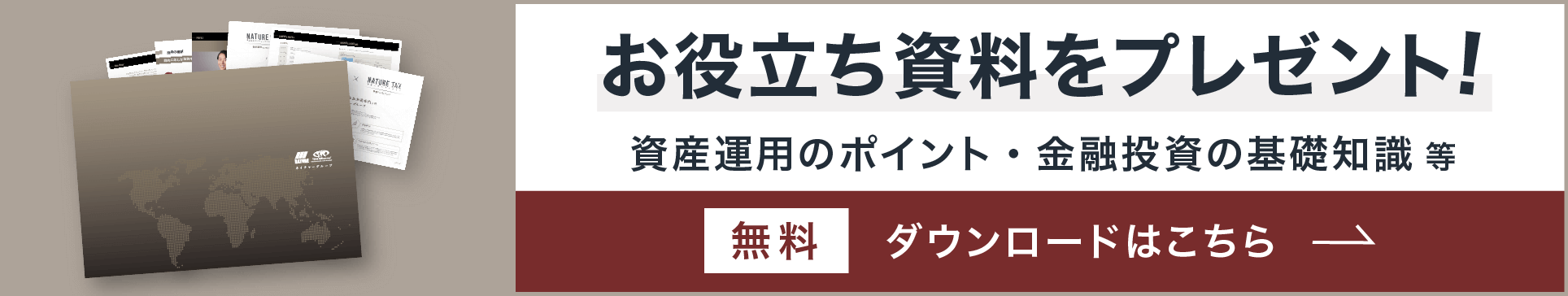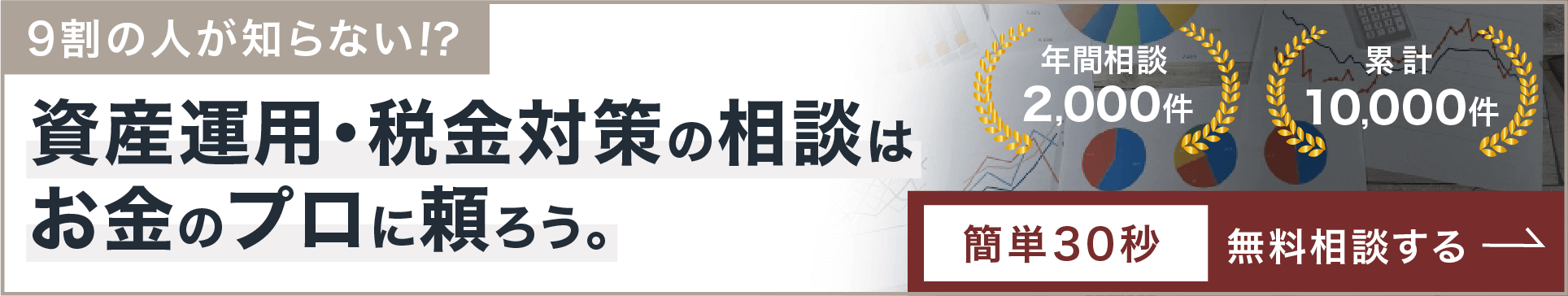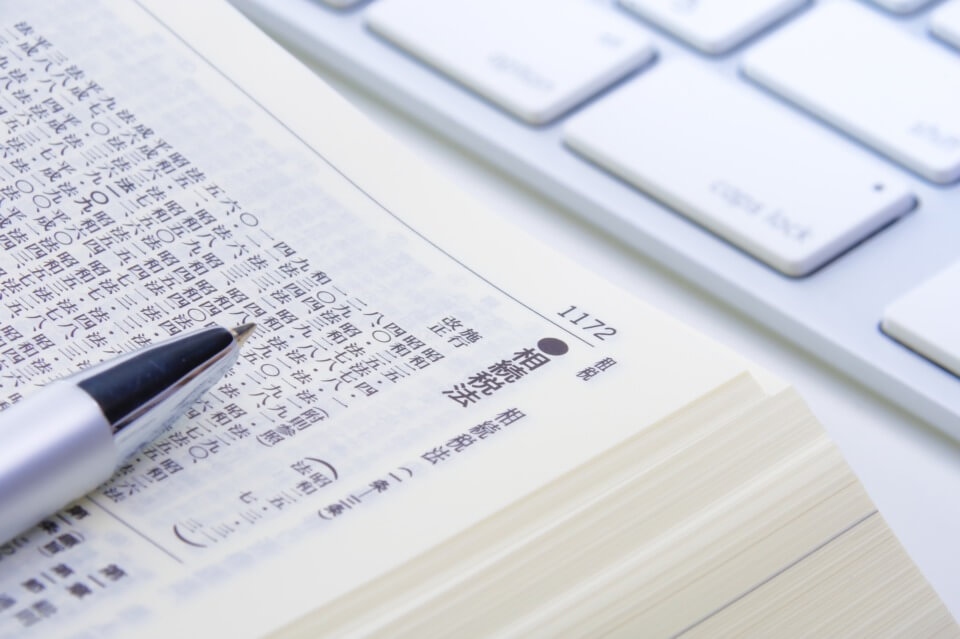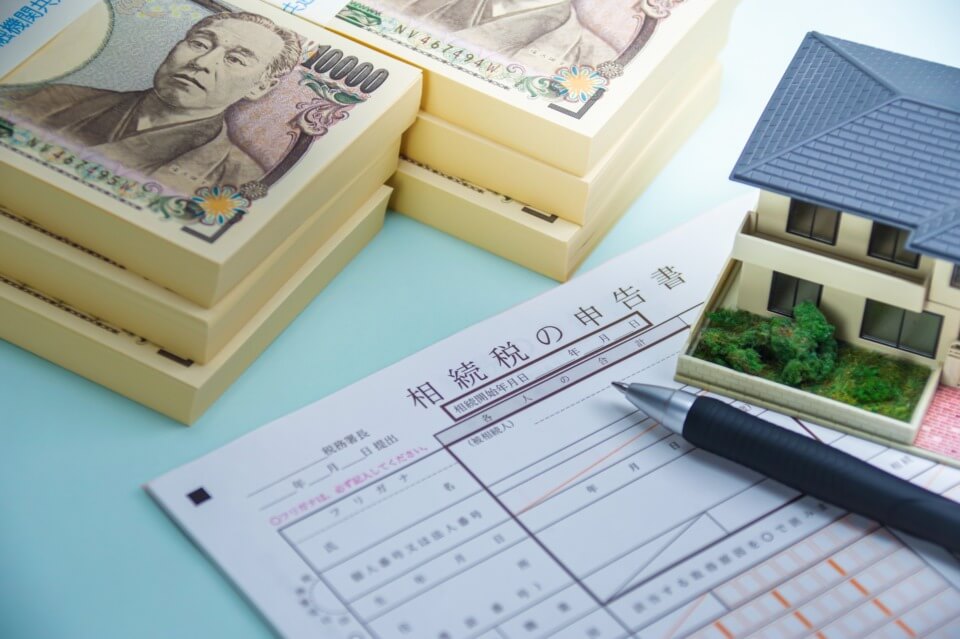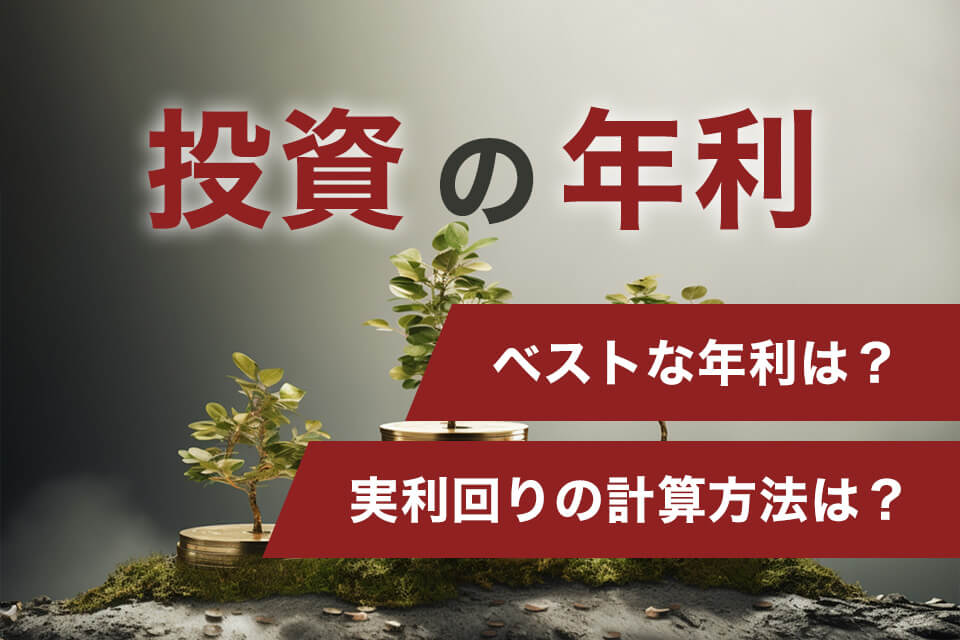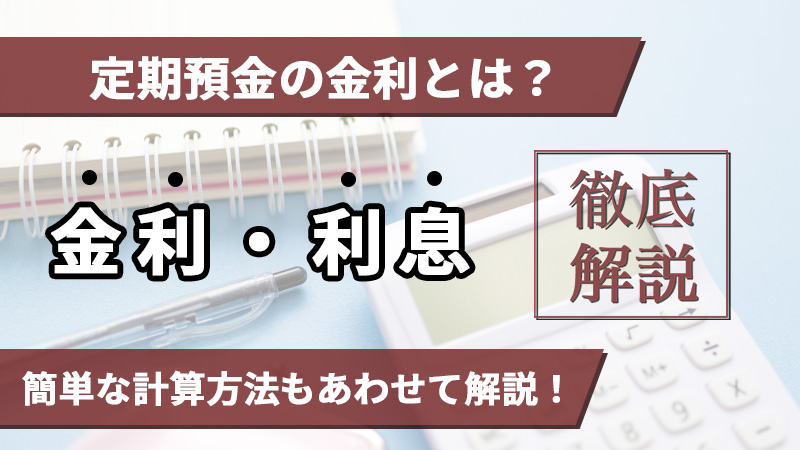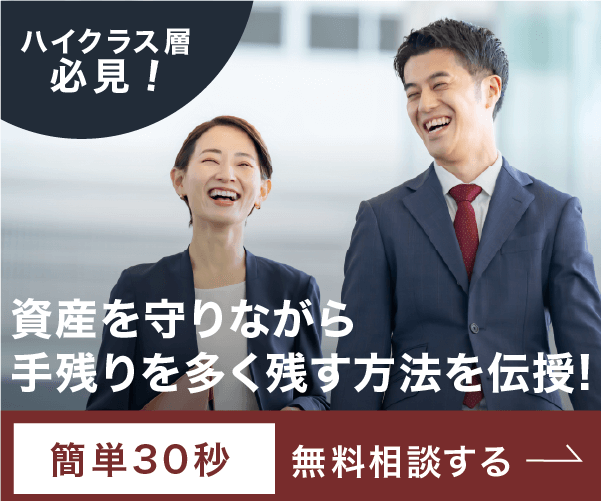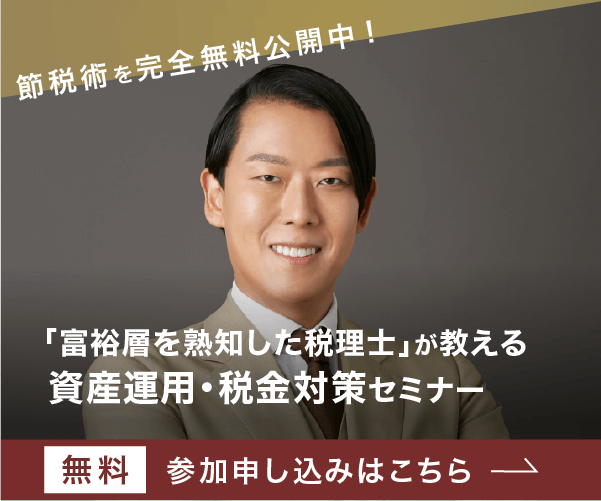![]() 2018年4月3日
2018年4月3日![]() 2023年4月13日相続・事業承継
2023年4月13日相続・事業承継
事業承継とは?成功するためにもメリットやデメリットを知っておこう

会社の経営者といえども、50年や60年先も自分自身がトップで責任ある立場にいられるかといえばそうではありません。
人間は年を重ねるごとに老いていくもの。
仕事ができる状況ではなくなったら、会社をたたむか誰かに後を継がせなければなりません。
もちろん、自分で築き上げてきたお城をいとも簡単にたたみたくないのは、誰もが思う事でしょう。
そこで、誰かを後釜として引継ぎさせることを、事業承継といいます。
ここでは、事業承継をしたことによって何が起こりえるのか。
また、それによってどのようなメリットやデメリットがあるのかを見ていきましょう。
そもそも事業承継とは?
事業承継は、個人の資産を引き継ぐのではなく事業をそのままそっくり渡すことが本来の目的です。
事業承継がうまくいくと、会社は2代目、3代目と生き残れるということです。
ですが、誰でもそれができるわけではありません。経営を知らない親族に事業承継してしまうと、おそろしく会社の寿命が縮まるリスクも考えられます。
つまり、事業承継をするにしても、人選が非常に大切なのです。
大企業の場合は、社員数も役員も多いので、後継者になる器を持つ人材がたくさんいるという特徴があります。
対して中小企業だとどうでしょう。
中小企業にとって、これは大きな課題になります。
少ない社員数ということもありますし、そもそも役員すらいない会社も存在しています。
そうなれば、後継者選びに悩んでしまうことでしょう。
とはいえ、事業承継をしたいと思ったのであれば、のんびりしているわけにはいきません。
事業承継をうまくすすめていくためには
事業承継といってもおおきくわけて3つの方法があるということをご存知でしょうか。
誰かに引き継ぐだけではない、別の方法もあります。
以下に、各方法について見ていきましょう。
社員や家族に引き継ぐ
もし、会社で自分の子供が働いていたらどうでしょうか。
おそらくほとんどの経営者は、その子供に事業承継をさせるという選択肢をとります。それは当然のこと。
自分の子供は誰よりも信頼できますし、意思を引き継ぐにはもってこいの方法といえます。
しかし、親は親です。いくら社員だったとしても子供はかわいいもの。
子供に事業承継をした結果、売り上げを伸ばすどころか、赤字転落してしまうというリスクも考えておかなけばなりません。
また、時代の流れもあり働き方の選択肢は多様化しています。
ですから、子供が親の事業を引き継ぐということは少なくなってきています。
また、会社に負債があればそれを子供に背負わすのは、親としても避けたいところでしょう。
一方で、一般の社員や役員であれば、親としての甘えもないため心を鬼にして事業承継をできるのではないでしょうか。
事業承継する場合には、自分が保有している株式や今までやってきた仕事を譲渡しなければなりません。通常、負債もそのまま継承します。
また、事業承継をするということは、任命された人物は会社の顔になるというわけです。ですから、あいさつ回りも徹底して行うようにしましょう。
M&A
最近よく耳にするM&A。
このM&Aとは、2つある会社を1つにまとめたり、どこかの会社が別の会社を買い取り、吸収したりすることをいいます。
とくに中小企業においては、事業承継のためにこのM&Aがよく選択されています。
少し前までは、後継者選びが難航し見つからなかった場合は、廃業を余儀なくされるケースが多くを占めていました。
しかし、近年はM&Aのメジャー化により、吸収合併等の手法で廃業せずに会社を存続させる手法も見られるようになっています。
M&Aは吸収される側だけではなく、吸収する側にもメリットがあります。
ここ最近では、時代の流れがすさまじく早く、どの分野でも競争が熾烈になってきています。
当然、それについていけず事業に失敗することもあるでしょう。
従って、いかにして競争に勝ち残れるのかが大きなポイントといえます。
そこでM&Aが活躍します。
同業会社に対してM&Aを実施することで、顧客の開拓もスムーズにできますし、コストや時間も大幅に減らすことができるのです。
結果的にM&Aがうまくいけば、業界シェアのトップになれる可能性もあります。
一方で、M&Aにもデメリットがあります。
それは、売り手や買い手が簡単には見つからないということです。
例えば、いくら格安な一軒家が販売されていたとしても、その家自体に魅力を感じないと誰も購入してくれません。
それがM&Aにもあてはまるというわけです。
当然ながら、会社そのものの業績がとても悪い場合、それを好んで引き取りたいなんていう会社はほとんど存在しません。
買い手がつかない場合は、1年や2年以上かかるケースもあります。
会社を上場させる
会社を上場させることも事業承継にあたります。
今の時点で、後継者としてバトンタッチできる人材がいない場合や、借り入れなどの負債を背負わすのは心苦しい、なんてケースもあるのではないでしょうか。
また、社外から該当する人材を確保しようとおもっても、その人物が適任かどうかなんてわかりません。
そこで、株式上場をさせるというわけです。
株式上場をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
株式上場をすれば、会社としての信頼度がアップします。信頼度がアップするということは、優秀な人材がきてくれる可能性が大いにあるということです。
また、銀行からの借り入れの際に個人保証であったり、担保がいらなくなるというメリットがあります。
しかし、どの会社も簡単に株式上場を果たせるわけではありません。
なぜなら、証券会社のとても厳しい審査が待っているからです。
この審査に通過しないかぎり、上場できることはありません。
最終的に廃業させることも視野にいれよう
事業承継する人材がいなかったり、M&Aで買い手がみつからなかったり。当然、株式上場も果たすことができず。
この場合は、会社を廃業させるということも考えておかなければなりません。
廃業=倒産と思われがちですが、そうではありません。倒産ではなく、あくまで後継者不足による廃業です。
とはいっても、廃業すると従業員を解雇しないといけませんし、なにより事業そのものがなくなってしまいます。
つまり、いままで積み上げてきた努力の結晶が一瞬にして崩れ去るわけです。
これは経営者もそうですが、従業員も辛い思いをしなければなりません。
まとめ
今回は、ひと言に事業承継といっても、さまざまなやり方があるということを確認してきました。
しかし、一生懸命会社を大きくしてきたのに、廃業という選択肢は絶対に避けたいところ。
後継者問題で悩んでいるのであれば、廃業という選択肢をとる前に、考え得るだけの方法をやりきってみるべきです。
時間はかかりますが、事業承継が頭に浮かんだ時点で行動をとれば、いざ必要になったときに、自社にとって最適な道を選ぶことができるのではないでしょうか。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
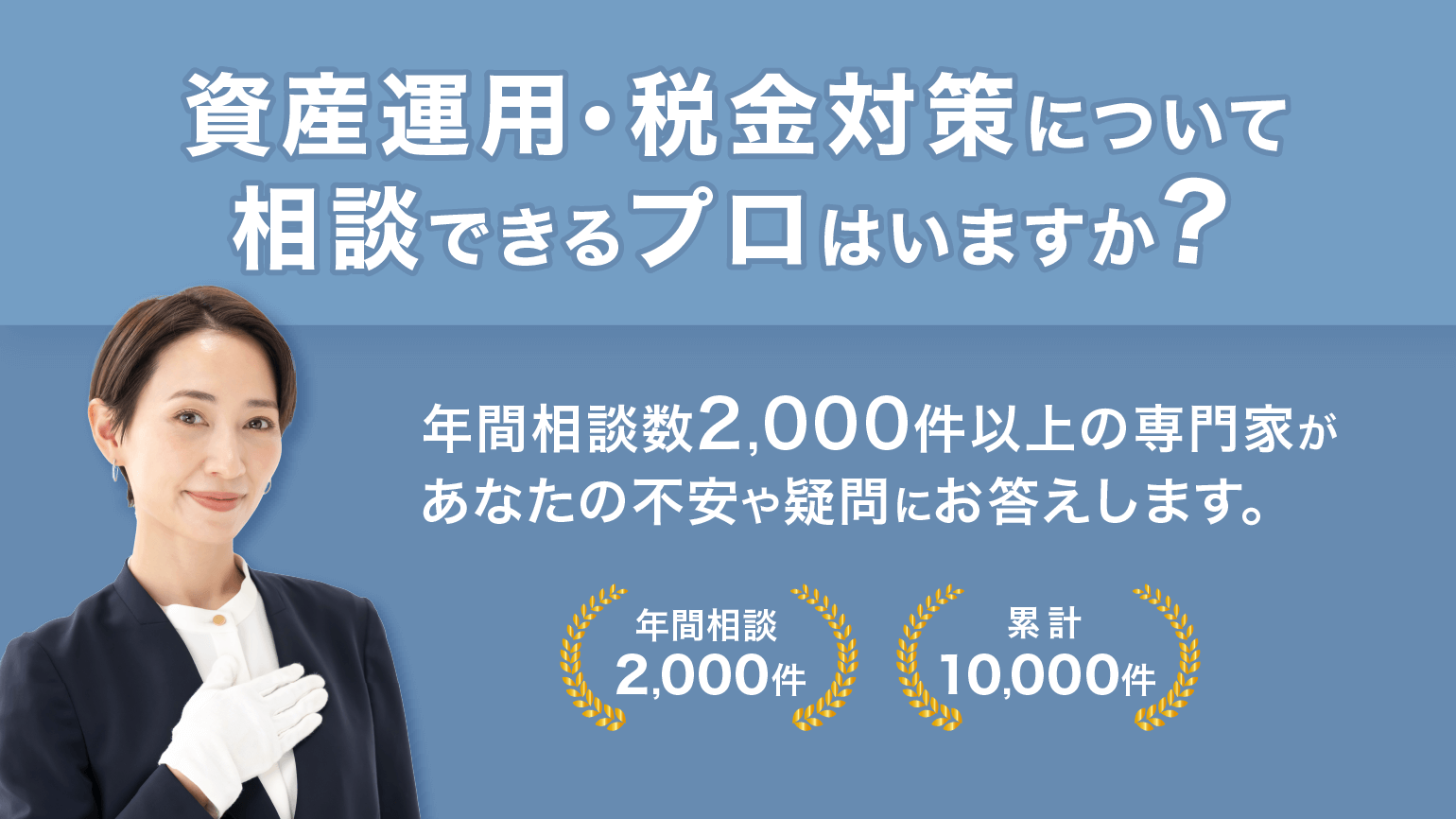
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用