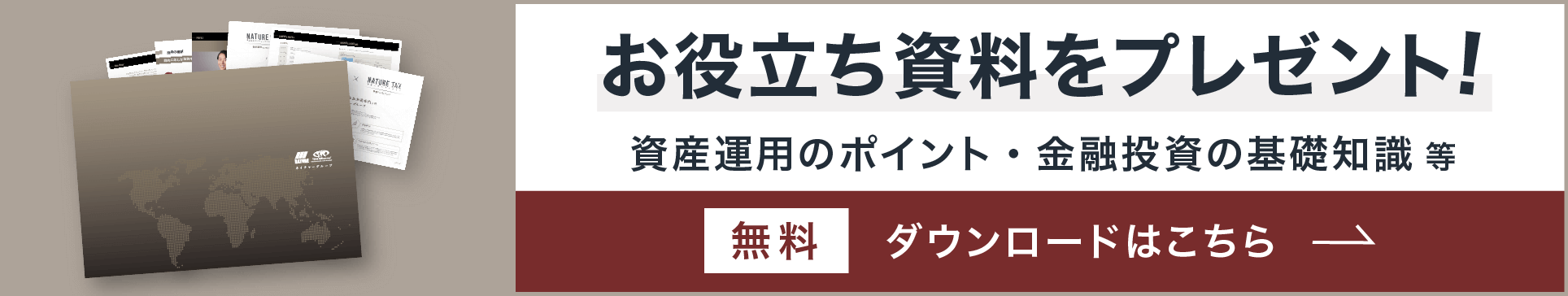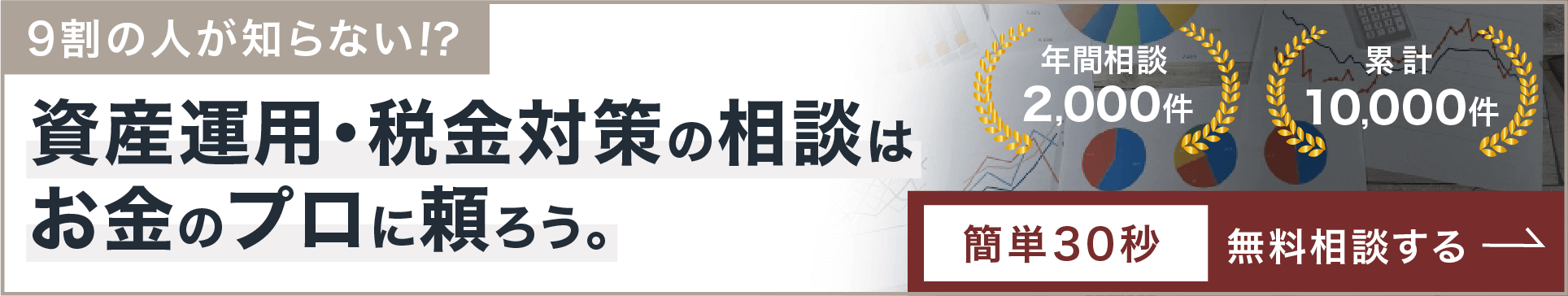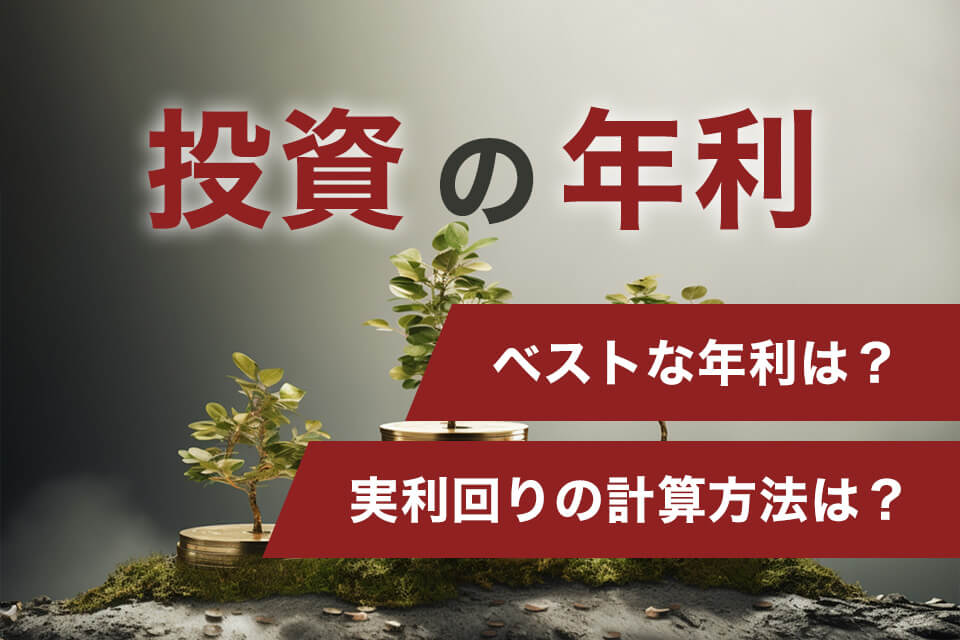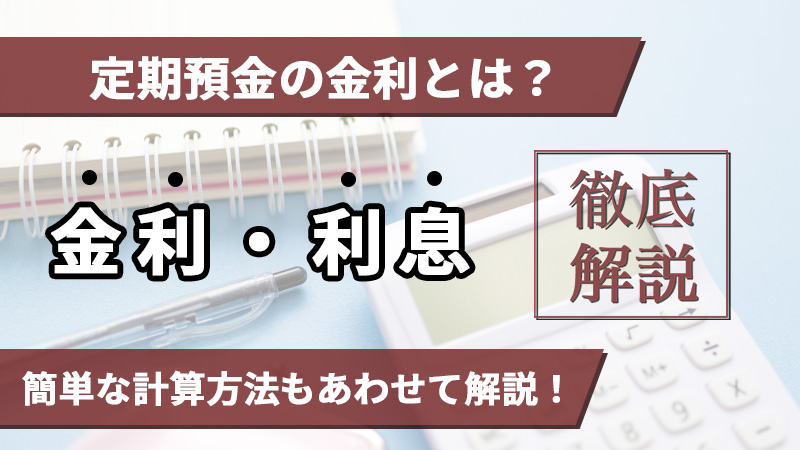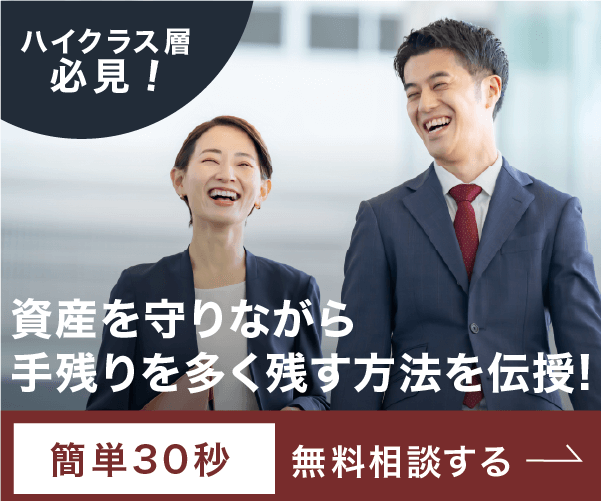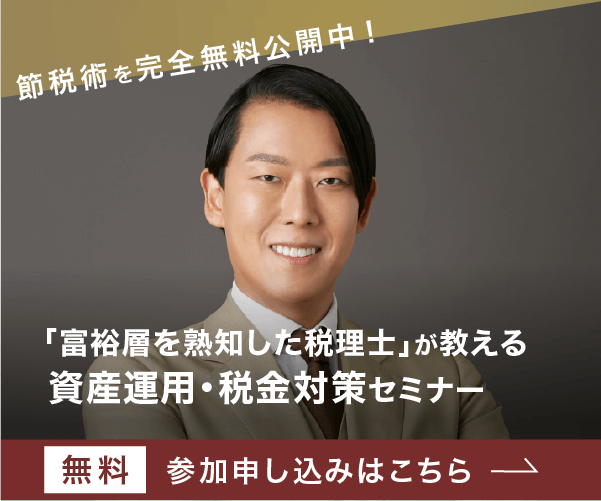![]() 2023年4月7日
2023年4月7日![]() 2024年2月29日相続・事業承継税務資産運用
2024年2月29日相続・事業承継税務資産運用
法人税を種類別に解説!計算方法や所得税との違いまでを正しく理解

法人に課される基本的な税金の種類は、法人税・法人住民税・法人事業税です。他にも似たような名称の税金があるため、混乱してしまう方もいるのではないでしょうか。名称が似ていても、納税先・用途・課税対象などがそれぞれ異なります。
この記事では、法人にかかる税金の種類を表にまとめて比較しています。種類別の違いを一目で確認できるため、法人税についてお悩みの方はぜひご一読ください。また、各種税金の計算方法や、個人事業主にかかる税金との違いについても詳しく解説します。
目次
法人税と所得税の違い
法人税と所得税はどちらも所得に対して課される税金ですが、課税対象や課税標準などがそれぞれ異なります。
税金に対する理解を深めるためにも、まずは両者の違いを詳しく見ていきましょう。
法人税と所得税の違い 1.納税義務者
所得税は個人、法人税は法人が納税義務者です。法人は法律で法人格を与えられており、社会的に人格をもつ存在として扱われます。
1人の人間として扱われるため、個人の所得に対して所得税が課されるのと同様、法人の所得に対しては法人税が課される仕組みとなっています。
法人税と所得税の違い 2.課税標準
所得税は個人の所得にかかりますが、法人税は会社の利益にかかります。利益は収益から費用を引いたもの、所得は収入金額から必要経費を引いたものです。そのため、どちらも内容的には同じです。
しかし、法人税は会社の利益に一定の調整額をプラスまたはマイナスをした税額調整後の金額に対して法人税が課されるという点で異なります。
法人税と所得税の違い 3.税額計算の対象期間
所得税の計算の対象期間は、暦年となっています。1月1日~12月31日までの間に稼いだ所得が所得税の課税対象となり、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行わなくてはなりません。
法人税は定款で定めた1年以下の期間である事業年度が計算の対象期間となります。事業年度の利益が法人税の課税対象で、事業年度終了日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出しなくてはなりません。
法人税と所得税の違い 4.課税方法と税率
所得税の課税対象となる所得は、10種類に分類されます。種類によって所得の計算方法が異なっており、所得の性格を考慮して各所得の合計額に対して税率によって税額計算する総合課税、合計せずその所得に対する税率によって税額計算する源泉分離課税、申告分離課税などがあります。
医療費控除や扶養控除などの所得控除を差し引いた課税所得金額に税率をかけて最終的な税額を算出するという仕組みです。なお、所得が多いほど税率が高くなる超過累進税率が用いられます。
一方で、法人税は法人の事業活動から生じた利益をまとめて課税します。所得税のような所得控除は設けられていません。税率も一定税率で、法人の種類や資本金の規模によって変化します。
法人税の種類とは?

法人税とは、法人税・法人住民税・法人事業税の総称です。決算で確定した税額を帳簿に計上する際は「法人税等」という勘定科目を使用します。
法人に課される税金の種類は複数ありますが、「誰に払うか」「なぜ納めるか」など特徴を比較することで違いを整理できるでしょう。ここでは、法人が納める税金の種類について解説します。
法人が納める基本的な3つの税金
法人が納める基本的な税金を以下の表にまとめました。
|
納税先 |
課税対象 |
課税される理由 |
|
|---|---|---|---|
|
法人税 |
国 |
所得 |
利益が生じたことへの課税 |
|
法人住民税 |
地方 |
法人税額※1 |
地域に事務所を所有することへの課税 |
|
法人事業税 |
地方 |
所得や収入など※2 |
事業を営むことへの課税 |
※1上記は法人税割の場合
※2資本金額や業種によって異なる
3つの税金の大きな違いは、納税先が国と地方(都道府県・市町村)のどちらになるかです。税金の種類によって、税額の基準となる金額や課税される理由も異なります。
法人に関するその他の税金
法人が納める税金の種類には、名称の似ているものが複数あります。
|
納税先 |
課税対象 |
課税される理由 |
|
|---|---|---|---|
|
地方法人税 |
国 |
法人税額 |
地域格差の縮小 (法人税と合わせて納める) |
|
地方法人特別税(廃止)※1 |
地方※2 |
法人事業税額の所得割額または収入割額 |
地域格差の縮小 (法人事業税と合わせて納める) |
|
特別法人事業税 |
※1地方法人特別税は令和元年9月に廃止され、代わりに特別税法人事業税が創設(令和元年10月)
※2法人事業税と合わせて徴収されるため納税先は地方ですが、課税主体は国
法人税を納める法人とは
個人と同様、法律上では法人にも人格が与えられ、納税義務が課せられています。法人を大きく分けると、内国法人と外国法人に区分されます。内国法人は国内に事務所を持つ法人、外国法人は内国法人以外の法人です。また、内国法人にはさらに以下5つの区分があり、区分によって課税のルールが異なります。
|
区分 |
具体例 |
|---|---|
|
公共法人 |
地方公共団体 |
|
公益法人等 |
学校法人、 公益社団法人 |
|
人格のない社団等 |
同窓会、 業界の団体 |
|
協同組合等 |
農業協同組合、 信用金庫 |
|
普通法人 |
株式会社、 合同会社 |
上記のうち、公共法人には法人税の納税義務がありません。また、区分によって課税所得の範囲が異なります。例えば、普通法人・協同組合等の課税所得の範囲は「全ての所得」ですが、公益法人等・人格のない社団等は「収益事業」に該当する所得のみが対象です。
法人税はどのような用途に使われるのか
法人税は国に納める税金であるため、その他の歳入(国の収入)と合算され、各省庁などへ分配される仕組みです。日本の歳入は法人税、所得税、消費税といった「税収」と「公債金(国の借金)」で構成されており、政策や社会保障のための費用として使われます。
法人税はどれくらい?税率と計算方法
法人が国に納める税金の種類は、「法人税」と「地方法人税」です。これらの税金は、事業によって利益が生じた法人に対して課税されます。「法人税はどれくらいかかるのか」気になる方に向けて、概要と計算方法を解説します。
法人税の税率・計算方法
法人税額は、所得に税率を掛けて計算する仕組みです。
- 法人税=所得金額×税率
- 所得金額=益金-損金
【普通法人の法人税率(令和4年4月1日以降)】
|
区分 |
税率 |
||
|---|---|---|---|
|
資本金1億円以下 |
年800万円以下の所得 |
下記以外の法人 |
15% |
|
適用除外事業者 |
19% |
||
|
年800万円超の所得 |
23.20% |
||
|
上記以外の普通法人 |
23.20% |
||
法人税率は、法人の種類や規模に応じて異なる「比例税率」となり、原則23.20%です。ただし、資本金1億円以下の中小法人には、15%または19%の軽減税率が適用されます。15%の軽減税率は令和5年3月31日までとされていましたが、令和5年度税制改正によって2年延長されました。
所得金額の計算に用いる「益金」とは事業や不動産売却による収入、「損金」とは収入を得るためにかかった費用などを指します。
法人税を計算する際の注意点は、課税対象となる所得と帳簿上の利益が必ずしも一致しない点です。法人の当期純利益は帳簿上の「収益-費用」で計算しますが、法人税額を計算する際の益金・損金とは一部異なります。法人税の対象となる所得を計算するには、一定の調整が必要です。
(参考: 『国税庁 No.5759法人税の税率』)
(参考: 『経済産業省 令和5年度税制改正のポイント』)
税務調整とは
税務調整とは、法人の利益と課税所得の調整をすることです。調整が必要になる理由は、企業会計と税法の計算方法が異なり、法人税などの計算が正確にできないためです。
企業会計は適正な損益計算で企業の利益を正しく把握することが求められる一方、税法は公平に課税を行うために課税所得を把握することが求められます。
交際費や寄附金、減価償却費といったように、企業会計上は費用に含むことができても、公平な課税を行うには、損金に計上できないものがあります。税務調整では、このような目的のズレの調整が行われるのです。
地方法人税の徴収開始はいつから?
地方法人税は法人税と合わせて徴収される国税で、令和元年10月より徴収が始まりました。法人税の納税義務を有する法人に対して課税されます。
- 地方法人税=法人税額×税率10.3%
日本では、地域間における税収の格差が開きつつあります。各地域が安定した税収を得るには、税収の偏りを是正する仕組みが必要です。このような背景から政府がさまざまな取り組みを行っています。地方法人税は、地方間における税収の偏りを適正化するために徴収される税金です。
(参考: 『国税庁 地方法人税の税率の改正のお知らせ』)
法人税の納付が遅れた場合のペナルティ
企業は事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人税の申告または納付をしなくてはなりません。
期日までに法人税を申告・納付しない場合は、以下のようなペナルティの対象となるので注意が必要です。
延滞税が発生する
法人税の申告・納付の期日を過ぎた場合、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。延滞税の金額は、期日の翌日から納付完了日までの日数に応じて計算されます。
現時点(2024年1月)の延滞税の税率は以下の通りです。
- 納期限の翌日から2か月を経過する日まで:原則年7.3%
- 納期限の翌日から2か月を経過した日以後:原則年14.6%
上記はあくまでも原則です。納期限の翌日から2か月を経過する日までは」年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」、2か月を経過した日以後では「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.4%」のいずれか低い割合が適用されます。
また、税率は年によって変わることがあるのでご注意ください。
無申告加算税が徴収される
期日までに法人税を申告しない場合、無申告扱いとなります。その結果、本来の納付額に15~20%の無申告加算税が課せられます。
法人税を納付している場合でも、税務調査にて隠ぺいや書類の改ざんといった不正事実が発覚すれば、納付額に対して35~40%の重加算税が上乗せされる可能性があるので注意が必要です。
青色申告が取り消される可能性がある
確定申告を期限内に2期連続で行わない場合、青色申告が取り消されます。青色申告には赤字(欠損金)の繰り越し等といったメリットがありますが、取り消されることで恩恵を受けられなくなります。
また、赤字決算の場合は利益がないので法人税は課されませんが、確定申告は必要です。また、赤字であっても法人住民税の均等割分は課税対象となるので注意してください。
法人税の納付方法
法人税は以下のように複数の納付方法に対応しています。
- 窓口納付
- コンビニ納付
- スマホアプリ納付
- クレジットカード納付
- インターネットバンキング納付
- ダイレクト納付
コンビニ納付は最寄りのコンビニで納付できる手軽さがメリットですが、納付できるのは30万円以下に限られているので注意が必要です。
また、クレジットカード納付は利用金額に応じてポイントが貯まる点はメリットですが、決済手数料がかかるといったように、各納付方法にはメリット・デメリットがあるため、各納付方法の違いを理解し、自身に合った納付方法を選択しましょう。
法人住民税・法人事業税の税率・計算方法
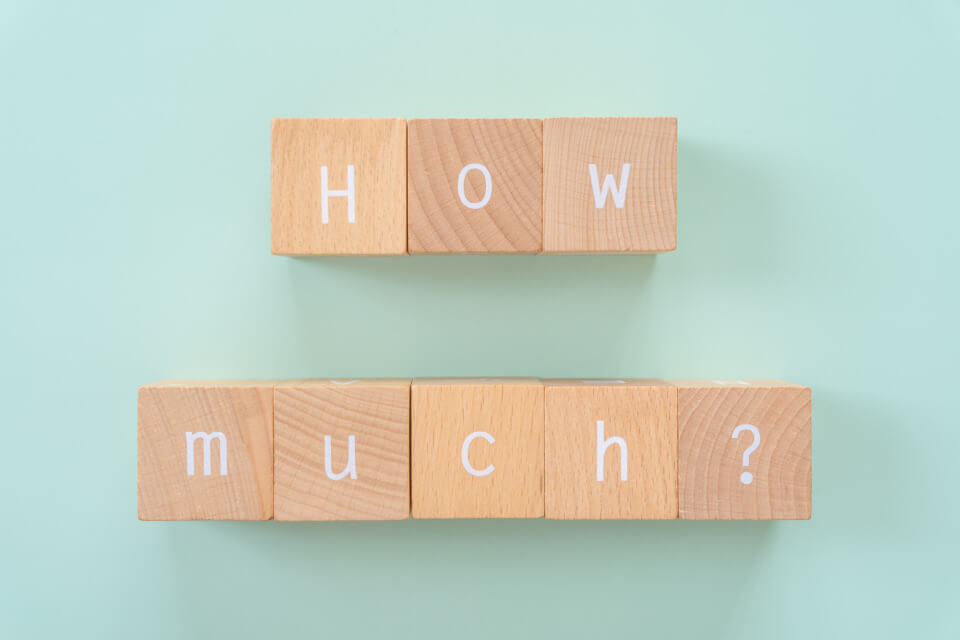
ひとりの人間と同様に、法人も地域社会の構成員と見なされます。また、地域で事業を営むには、何らかの形で行政のサービスを利用するでしょう。法人住民税や法人事業税は、地域の一員である法人が、事務所を構える都道府県・市町村へ納める税金です。ここでは、法人住民税と法人事業税の税率や計算方法について解説します。
法人住民税の計算方法
法人住民税は、都道府県民税と市町村民税の総称です。それぞれの「法人税割額」と「均等割額」を合計した金額を納めます。
- 法人住民税=法人税割額+均等割額
【法人税割額】
法人税割額=法人税額×税率※
※法人税割の税率(令和元年10月1日以降)
|
標準税率 |
制限税率 |
|
|---|---|---|
|
A都道府県民税 |
1.0% |
2.0% |
|
B市町村民税 |
6.0% |
8.4% |
|
合計(A+B) |
7.0% |
10.4% |
標準税率は基準として定められている税率、制限税率は各地域の税率が標準税率を超える場合の上限です。
【均等割額(資本金額1億円以下の普通法人)】
法人住民税の均等割額は、所得が生じない年度でも必ず課税される税金です。以下のように、資本金や従業員数に応じて税額が異なります。
|
資本金額 |
従業員数 |
市町村民税 |
都道府県民税 |
|---|---|---|---|
|
1,000万円以下 |
50人超 |
12万円 |
2万円 |
|
50人以下 |
5万円 |
||
|
1,000万円超1億円以下 |
50人超 |
15万円 |
5万円 |
|
50人以下 |
13万円 |
(参考: 『総務省 法人住民税・法人事業税』)
法人事業税の計算方法
法人事業税は、地域で事業を営むことに対して課される税金です。課税対象や税率は、業種によって異なります。例えば、原則の課税対象は所得ですが、保険業やガス供給業など一部の業種の課税対象は収入です。
- 法人事業税=所得または収入×税率
また、同じ業種でも資本金額によって税率が異なります。令和4年4月1日以降の税率は、以下の通りです。
【法人事業税の税率(資本金1億円以下の普通法人)】
|
所得 |
標準税率 |
|---|---|
|
年400万円以下 |
3.5% |
|
年400万円超800万円以下 |
5.3% |
|
年800万円超 |
7.0% |
法人事業税における課税の仕組みは複雑です。資本金1億円を超えると外形標準課税(付加価値割・資本割)が適用され、さらに複雑化します。外形標準課税とは、給与や純支払利子といった収益配分額や資本金額を基準に計算する方法です。
仕組みを正確に把握することが難しいため、不明点がある方は税務の専門家である税理士への相談をおすすめします。
地方法人特別税・特別法人事業税と法人事業税の違い
地方へ納める税金の種類は少々分かりにくいため、類似の税金を整理しておきましょう。
|
税金の種類 |
納付方法 |
注記 |
|
|---|---|---|---|
|
法人事業税 |
地方税 |
法人住民税と合わせて 地方へ納付 |
|
|
特別法人事業税 |
国税 |
法人事業税と合わせて 地方へ納付 |
令和元年10月に創設 |
|
地方法人特別税 |
国税 |
令和元年9月に廃止 |
|
|
地方法人税 |
国税 |
法人税と合わせて 国へ納付 |
法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税は、いずれも地方へ納める税金です。ただし、法人事業税以外は国が課税主体となる国税となります。
特別法人事業税と地方法人特別税の目的は、地域による税収の格差を適正化することです。地方法人特別税は令和元年9月に廃止され、代わりに特別法人事業税が創設されました。
特別法人事業税が国税にもかかわらず地方へ納める理由は、法人事業税の税率を引き下げる代わりに徴収されるようになったためです。
また、 地方法人特別税と地方法人税は名称が似ていますが、前者の納付先は地方、後者の納付先は国です。
法人と個人事業主はどっちがお得?
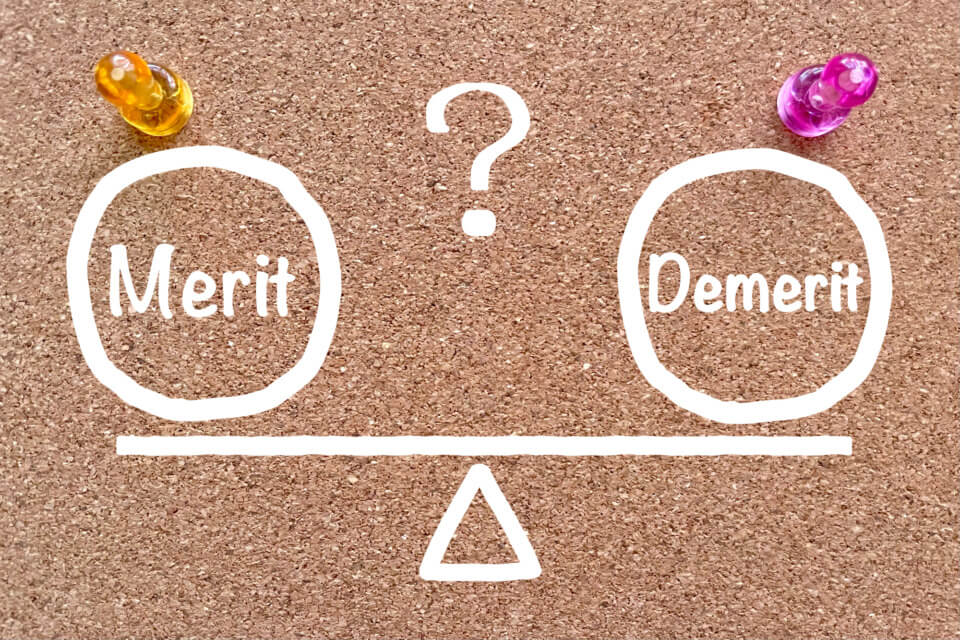
「法人と個人事業主では、税制上どちらが得なのか」気になる方もいるのではないでしょうか。以下の表は、法人税と所得税を4つの項目で比較したものです。
|
法人税 |
所得税 |
|
|---|---|---|
|
税率 |
比例税率 |
超過累進税率 |
|
計算方法 |
一括で計算 |
所得の種類別に計算 |
|
会計期間 |
事業年度 |
歴年(1月1日から12月31日) |
|
確定申告の負担 |
個人よりも複雑 |
法人よりも簡易的 |
ここでは、上記の違いから想定できる法人と個人事業主の損得について解説します。
高所得者は法人化で有利
所得税は、所得に応じて税率が高くなる「超過累進税率」です(税率5%から45%)。一方、法人税は比例税率(最大23.20%)が適用されるため、税率が一律になります(※)。従って、税率のみを考慮する場合、高所得の個人事業主は法人化したほうが有利といえるでしょう。
※一部の中小法人には軽減税率が適用されるため、厳密には一律ではありません
また、法人化した場合、法人と個人の2つの人格を用いることで節税の選択肢が広がります。例えば、法人の取締役が受け取る役員報酬は法人の経費となり、法人から個人が受け取る給料の一部に給与所得控除が適用されます。2つの人格を利用して収入を分散させれば、それぞれに適用される税率も下がる仕組みです。
効果的な税金対策には専門知識が必要ですが、個人事業主として収入を得るよりも法人化したほうが節税できる可能性があります。
所得の種類が多いと法人化で有利
所得税の対象となる所得は全部で10種類あり、所得に応じて課税方法が異なります。例えば、事業所得や不動産所得は総合課税に該当するため所得同士を合算して税率を計算する仕組みです。株式や不動産といった資産の売却時に課税される譲渡所得税は分離課税となり、他の所得と分けて計算しなければなりません。
一方、法人税は所得を種類ごとに区分せず、一括で税額を計算します。個人で複数の所得がある方にとっては、所得ごとの計算が面倒に感じることを考えると法人化が有利でしょう。
(参考:『国税庁 所得の種類と課税方法』)
減価償却は法人化で有利
事業を行う際に取得した自動車や機械装置といった固定資産は、減価償却という方法にて費用化するのが一般的です。
上記資産について、所得税の減価償却費は原則定額法で償却しますが、法人税は原則定率法とされています。定額法では毎期定額の減価償却費が計上される一方、定率法では取得年度から徐々に減価償却費が減少します。
早めに大きく経費計上したい方は、定率法を選択したほうが有利です。個人事業主は原則定額法ですが、申請書を提出することで定率法に変更する事も可能です。しかし、申請の手間と時間がかかることを考えると法人化したほうが手間を省けるでしょう。
確定申告の負担は個人事業主が有利
法人化を検討している場合、確定申告の負担増加に注意が必要です。個人の所得税は、1月1日から12月31日までの暦年で課税され、法人税は事業年度ごとに課税されます。法人の事業年度は定款などで定めた期間になりますが、6か月を超える場合は確定申告だけでなく中間申告も必要です。
また、法人は個人事業主よりも社会的信頼度が高く、取引先との契約や融資に強いといわれています。その一方、社会的責任が重く、決算書に関して個人よりも高い精度を求められます。確定申告時に作成する書類も多く、大きな負担がかかることを考えると個人事業主のほうが負担は少ないでしょう。
法人税と所得税のどちらがいいか迷っているならネイチャーグループへ
法人が納める税金には複数の種類があり、それぞれの計算方法や規定が複雑です。個人事業主と比べると税務の負担が大きいといえるでしょう。ただし、法人化することで税金対策の選択肢が広がります。法人税務や税金対策にお悩みの方は、実績が豊富な税理士へ相談してみてはいかがでしょうか。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、「効果的な税金対策と資産運用」に関するコンサルティングを得意とする税理士法人です。「年間2,000件」のご相談・ご依頼から培ったノウハウを基に、ベストなご提案をいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:法人税と所得税の違いを理解して最適な税金対策をしよう

法人の税務や税金対策を完璧にこなすためには、専門知識が必要です。自力で全てを行おうとすると、膨大な時間がかかる恐れがあるでしょう。税務の専門家である税理士へ相談すれば、その分、本業の事業拡大へ時間を費やせます。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、一般的な税務から効果的な税金対策、資産運用まで全面的にサポートいたします。経験豊富な税理士がベストな選択肢をご提案いたしますので、法人税でお悩みの方はぜひご相談ください。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
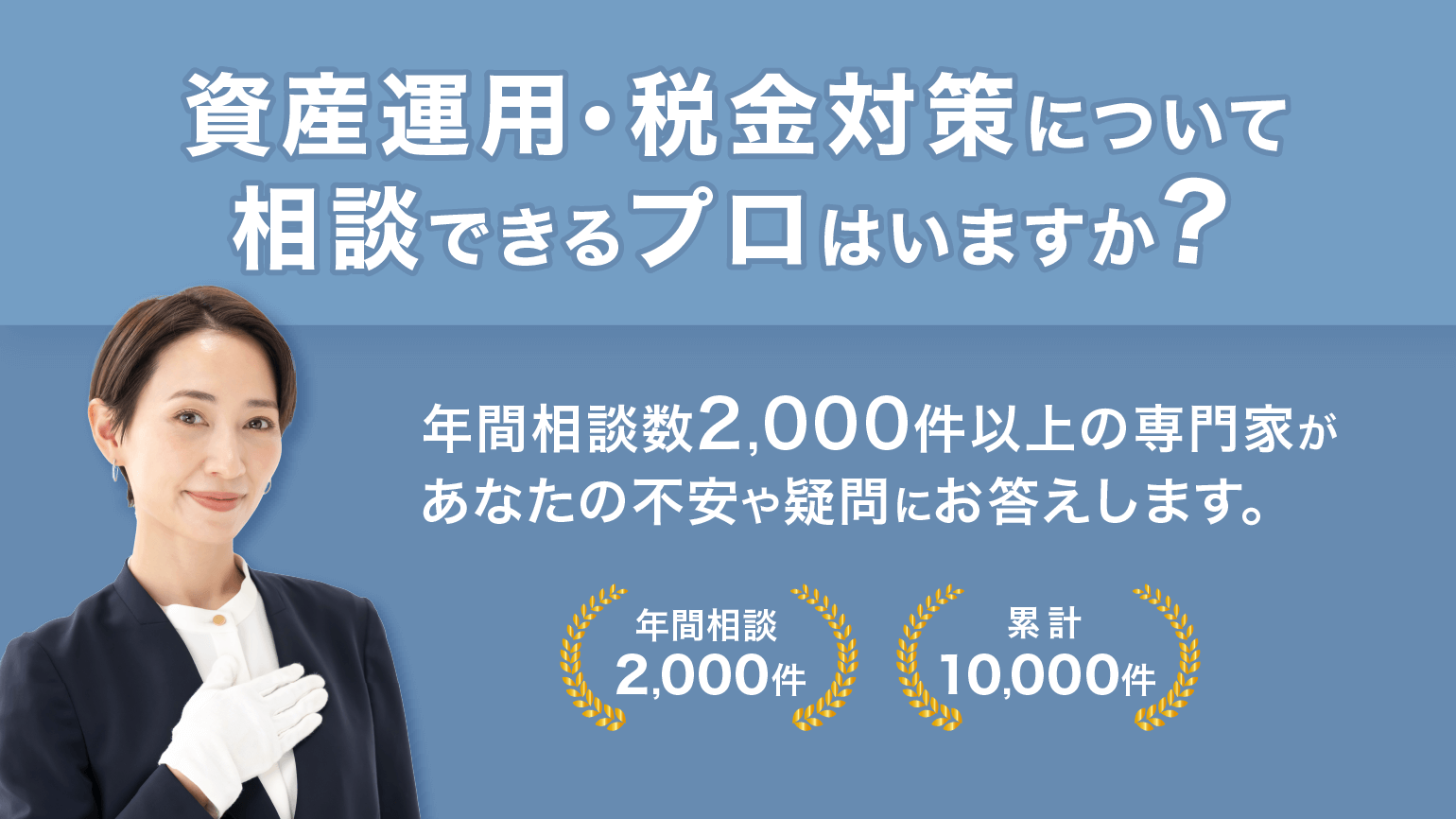
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用