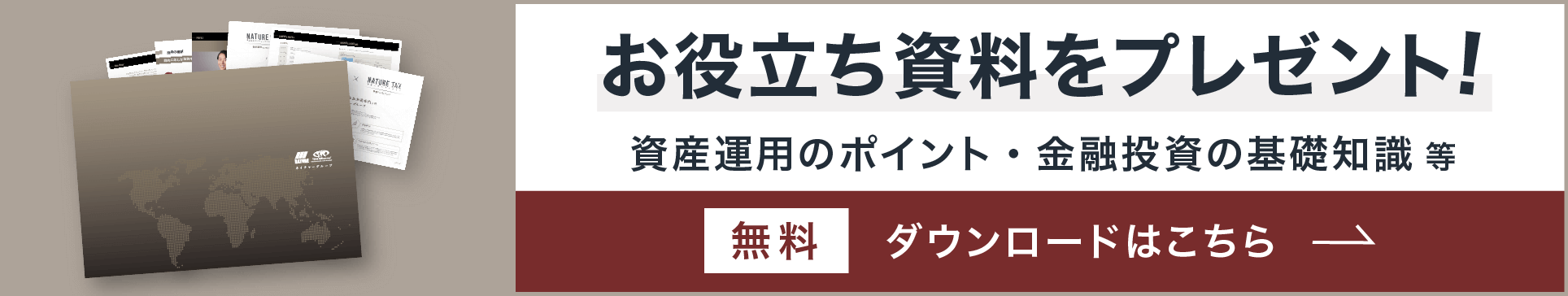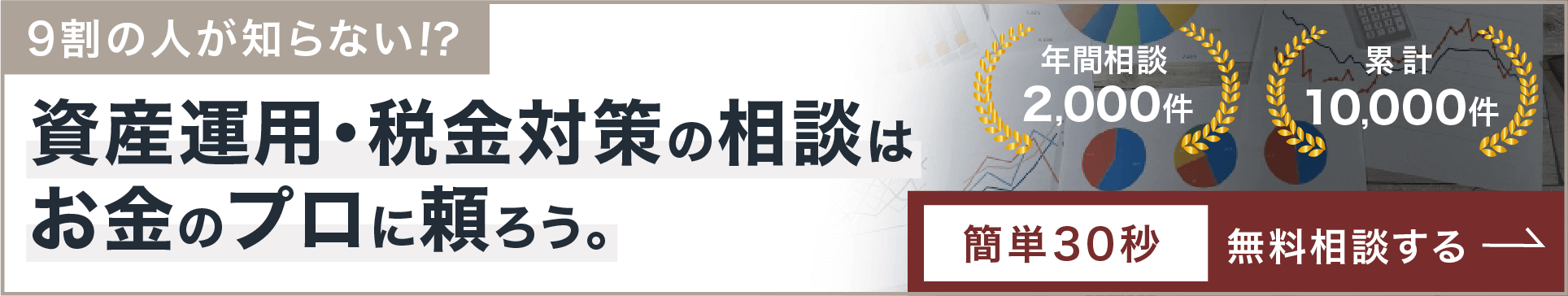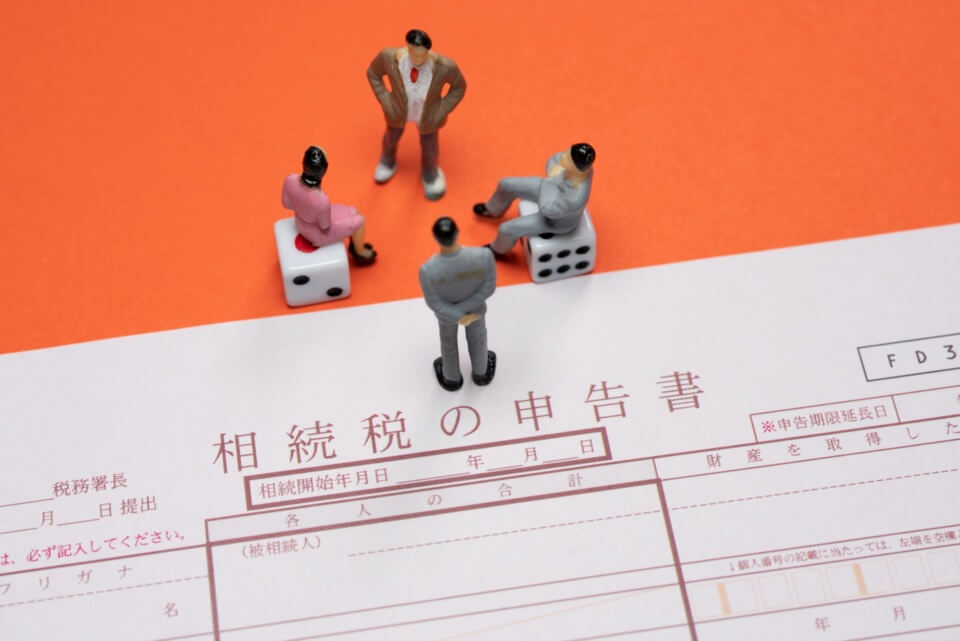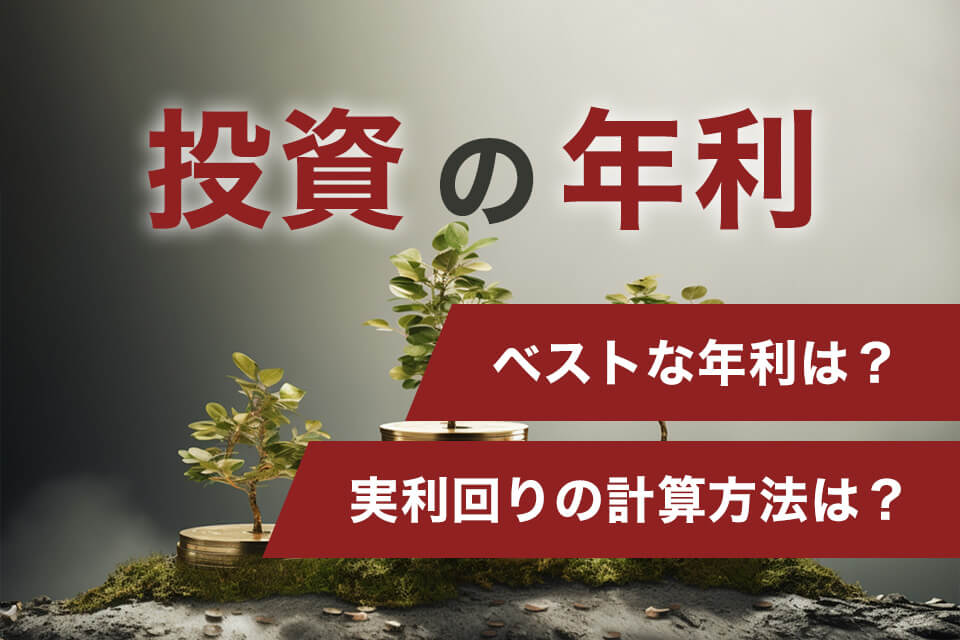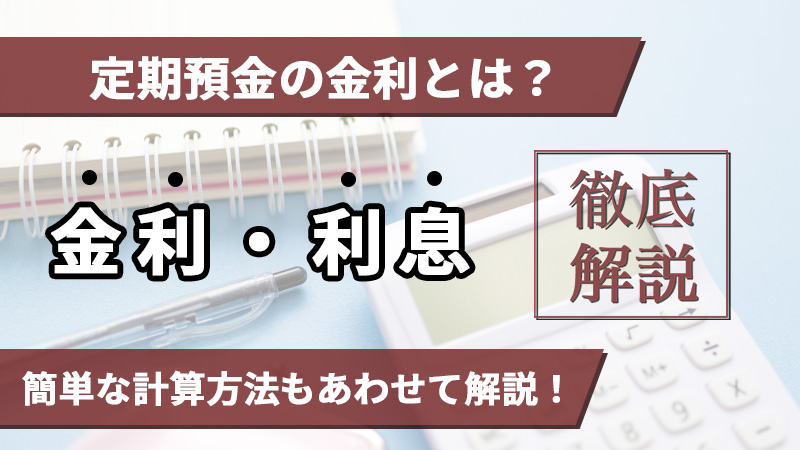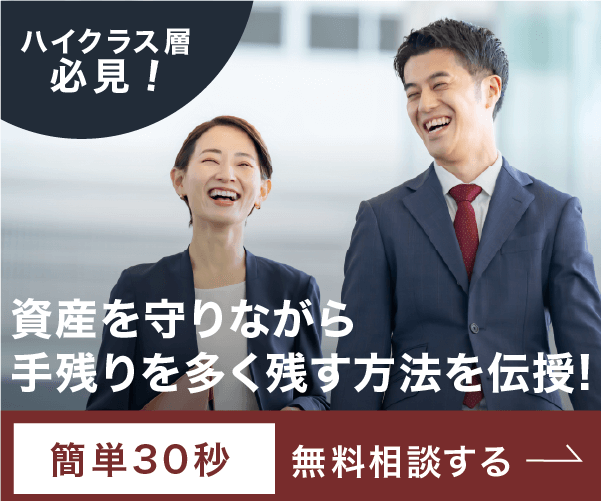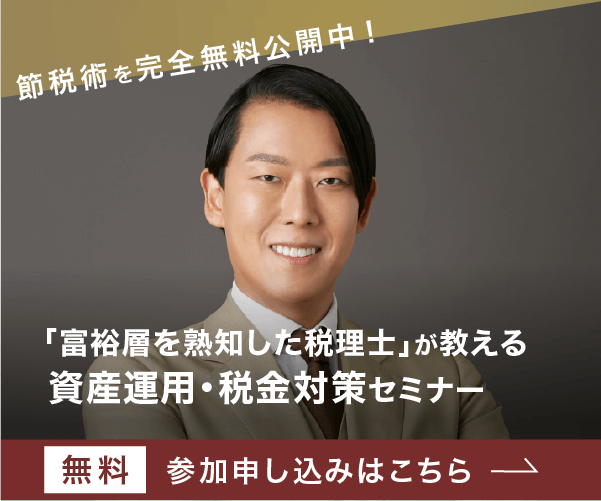![]() 2024年12月17日
2024年12月17日![]() 2025年6月16日不動産
2025年6月16日不動産
不動産投資で節税はできる?できない?仕組みを税務のプロが解説

不動産投資は節税できるとよく聞きますが、本当に節税できるのか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、不動産投資で本当に節税はできるのか解説します。仕組みやどの税金なら軽減できるのかといったことにも触れていきます。
また、節税効果のシミュレーション方法や注意点なども解説するため、本記事を読めば不動産投資の節税について網羅的に理解できるでしょう。
不動産投資で節税を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
※本記事の記載内容は2024年10月現在のものです。
目次
不動産投資をすれば節税できる
結論、不動産投資をすれば節税できます。
「あまり節税はできない」「節税目的の投資はやめた方がいい」と聞いたことがある方もいるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
節税できるかどうか不安に感じる方は、節税の仕組みがわからない方や、シミュレーション方法がわからない方がほとんどです。
仕組みがわかり、節税効果のシミュレーションが適切にできれば本当に節税できるのかという不安はなくなるでしょう。
不動産投資で節税できるのはなぜ?その仕組みとは
不動産投資で節税できる理由は、大きく4つあります。
- 減価償却を使える
- 損益通算ができる
- 不動産評価額を下げられる
- 法人化による節税が期待できる
仕組みを理解していれば、本当に節税できるのかと不安に感じることもなくなるでしょう。それぞれの詳細を確認していきます。
減価償却を使える
減価償却は、建物や設備などの資産を購入した際、一度で経費計上しないで何年にも渡り徐々に資産価値を減らしていくことです。うまく活用することで、節税を可能にします。
たとえば、不動産を買ったときにまとまって支払った費用をそれぞれの耐用年数に応じて毎年少しずつ経費として計上します。耐用年数は、減価償却が可能な期間のことです。
減価償却を使うことで毎年経費が増えて所得を少なくできるため、結果として税の負担を軽減できます。
損益通算ができる
損益通算とは、1年間で発生した利益からほかの事業で発生した損失を差し引ける制度です。
具体的には、不動産投資で発生した赤字を給与所得などのほかの収入と相殺して、所得を減少させます。結果、税負担は軽減されます。
不動産投資で赤字があるかどうかは、「家賃収入-必要経費」で計算可能です。必要経費には、ローンの金利や保険料、管理委託料、修繕費などが含まれます。
こちらの記事も読まれています:不動産投資で認められる経費とは?NGなものや気になるあの疑問も紹介
不動産評価額を下げられる
不動産評価額を下げられることで、節税効果を期待できます。これは、そのまま現金を持っているよりも不動産の方が評価額は低くなるからです。
特に贈与や相続時に効果を発揮するのですが、贈与税や相続税は相続税評価額に決められた税率を掛け合わせます。そして、その相続税評価額は時価の80%程度が一般的です。
たとえば、不動産1億円分であれば、課税対象額は8,000万円程度です。そのため、丸々1億円が課税対象となる現金よりも税金が抑えられます。
法人化による節税が期待できる
個人の所得税は累進課税であり、課税所得が一定のラインを超えると法人税よりも所得税の方が高くなってしまいます。
| 所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
法人税は最大でも23.2%であるため、課税所得が900万円を超えると個人の方が税負担は大きくなります。
そのため、900万円を超えたタイミングで法人化すれば、税負担を軽減可能です。
不動産投資で軽減できる税金
不動産投資で軽減できる税金は、次のとおりです。
- 所得税
- 住民税
- 相続税
- 贈与税
- 法人税
それぞれの詳細をみていきましょう。
所得税
所得税は、1年間で得た全ての収入からかかった経費や所得控除などを引いた金額に対して課される税金です。
所得控除には、次のようなものがあります。
- 配偶者控除
- 生命保険料控除
- 寄附金控除など
減価償却や損益通算を活用することで、さらに負担を軽減できます。
住民税
住民税は、都道府県民税と区市町村民税の総称で、所得に応じて納める税金です。
原則税率や算出方法に差はないため、条件が同じであればどこに住んでいても同じ金額になります。
所得税同様、減価償却や損益通算を活用することで税負担を軽減できます。
相続税
相続税は、相続が発生したときに課される税金です。絶対に課されるわけではなく、財産の相続税評価額の合計から基礎控除額を引いた金額がプラスになると発生します。
また、基礎控除額は法定相続人の数に応じて異なります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
資産を不動産で持っていることで、税負担の軽減が可能です。
贈与税
贈与税は、財産を譲り受けたときに発生する可能性がある税金です。日本では受け取った資産が110万円を超えると課税対象になります。
| 基礎控除後の課税価格 | 一般贈与の税率(控除額) |
|---|---|
| 200万円以下 | 10%(なし) |
| 300万円以下 | 15%(10万円) |
| 400万円以下 | 20%(25万円) |
| 600万円以下 | 30%(65万円) |
| 1,000万円以下 | 40%(125万円) |
| 1,500万円以下 | 45%(175万円) |
| 3,000万円以下 | 50%(250万円) |
| 3,000万円超 | 55%(400万円) |
| 基礎控除後の課税価格 | 特例贈与の税率(控除額) |
|---|---|
| 200万円以下 | 10%(なし) |
| 400万円以下 | 15%(10万円) |
| 600万円以下 | 20%(30万円) |
| 1,000万円以下 | 30%(90万円) |
| 1,500万円以下 | 40%(190万円) |
| 3,000万円以下 | 45%(265万円) |
| 4,500万円以下 | 50%(415万円) |
| 4,500万円超 | 55%(640万円) |
参照:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
特例贈与は18歳以上かつ親や祖父母などの直系尊属から財産をもらったときに適用されます。
相続税同様、資産を不動産にすることで税負担の軽減が可能です。
法人税
法人税は、その名のとおり法人の所得に課される税金です。
個人に課される所得税率が法人税率を超えるタイミングで法人化することで、税負担の軽減ができます。
自分の所得を計算して所得税の方が高くなる可能性がある場合は、法人化も検討しましょう。法人化の方法がよくわからない方は、専門家に相談するのがおすすめです。
不動産投資の節税効果が期待できるのは年間所得が900万円以上
不動産投資の節税効果が大きく期待できるのは、年間の所得が900万円以上の方です。年収でいうと1,200万円程度が目安です。
900万円未満の方も節税はできますが、900万円以上になると所得税が33%になり、節税の効果がより大きくなります。
減価償却、損益通算に加えて法人化するといった方法も有効になってくるため、より効果を実感できるでしょう。
不動産投資による節税効果のシミュレーション方法
不動産投資による節税効果をシミュレーションする手順は、次のとおりです。
- 経費を算出する
- 不動産収入を計算する
- 不動産所得を算出する
シミュレーションは非常に重要です。節税を考えている方はしっかりと目を通していきましょう。
経費を算出する
最初に、経費をピックアップしていきます。
主な経費は、次のとおりです。
- 減価償却費
- 火災保険料や地震保険料
- 固定資産税など
経費に該当するものの金額を正確に把握しましょう。ただ、経費になるかどうかを判断するのが難しい場合があります。
適当に判断して間違えると、後々トラブルに発展することがあります。もし判断に迷う場合は、専門家に相談してください。
不動産収入を計算する
経費の確認が終わったら、不動産収入を計算します。不動産の収入は家賃だけのように思われることもありますが、次の項目も収入に該当します。
- 礼金
- 更新料
- 駐車場代など
こちらも経費同様、収入に当たるかどうかの判断が困難なケースがあり、もし漏れがあると意図的ではなくても収入を隠していたと判断されかねません。
不安のある方は、最初から専門家へ相談しましょう。
不動産所得を算出する
最後に、不動産所得を計算します。ここまでに計算した不動産収入から経費を引いて求めた金額が所得です。
金額がプラスであれば、課税所得とみなされ課税対象になります。しかし、もしマイナスになればその分をほかの収入から引いて損益通算が可能です。
不動産投資で節税効果が高いのは木造の中古物件
高い節税効果を期待できるのは、木造の中古物件です。これは、減価償却期間が影響しています。
木造の減価償却期間は22年と決まっており、さらに中古物件は経過した年数を法定耐用年数から差し引けます。
では具体的に、築12年の木造中古物件の耐用年数をみていきましょう。
- 木造の法定耐用年数22年-築年数12年=10年
- 築年数12年×20%=2年
- 10年+2年=12年
※簡便法による計算
つまり、木造の場合、新築なら22年かけて減価償却していくのですが、中古物件であれば12年で済むのです。そのため、1年あたりの減価償却額が大きくなり、節税効果が高くなります。
不動産投資を節税目的で始めるときの注意点
不動産投資を節税目的で始めるときの注意点は、次の3つです。
- 不動産投資には大きな費用がかかる
- 物件を長く保有し過ぎるリスクがある
- 物件の売却を急ぎ焦ってしまうと支出が大きくなる
注意点を把握しておかないと、購入した後に後悔する可能性があります。後悔したくない方は、事前に確認しておきましょう。
不動産投資には大きな費用がかかる
不動産投資には大きな費用がかかります。「家賃収入を得たい」「節税したい」という思いが先走りすぎると、コストを無視しがちです。
一般的に不動産は安い買い物ではありません。数百万〜数千万円、一棟であれば億を超えるものもあります。
まず購入資金が大きくかかる可能性があるのは、理解しておくべきでしょう。
また、運用を続ける中で修繕費や管理費、毎年の固定資産税などの費用も発生します。購入できれば終わりではない点にも注意が必要です。
物件を長く保有し過ぎるリスクがある
不動産は長期間運用するのが一般的ですが、長く持ち続けていて耐用年数を超えると減価償却が引けなくなります。
減価償却できなくなると節税効果も薄くなるため、節税目的の方からすると魅力が低下するかもしれません。
また、耐用年数を超えた物件は、投資用だけではなく居住用としても欲しがる方が減ります。なかなか買い手が見つからないといった状況になることもあるでしょう。
物件の売却を急ぎ焦ってしまうと支出が大きくなる
長く持ち続けることに不安を感じ、物件を焦って売却すると支出が大きくなる可能性があります。
たとえば、取得から5年以内に売却する場合、5年を超えてから売却するケースと比べて税率は2倍です。
| 保有期間 | 税率 |
|---|---|
| 短期譲渡所得(保有期間:5年以下) | 30.63% |
| 長期譲渡所得(保有期間:5年以上) | 15.315% |
持ち続けるのが不安だからといって急いで売ると、税金を多く払うことになり、支出が大きくなってしまいます。
収支の変動リスクがある
収支変動のリスクがあることも忘れてはいけません。
不動産投資は安定した収入を得られるイメージが強いですが、空室が続いたり、経年劣化したりすると、収入が減ります。
結果、想定した収入が得られず収支が悪化する可能性があります。
また、節税効果が思ったように得られなかったり、ローンの金利が変動したりすることもあるでしょう。
そのため、最初のシミュレーションどおりにすべてがうまくいくと思うのは危険です。
不動産投資に失敗したときのこと、失敗を回避する方法を知りたい方は、合わせて下記の記事もご覧ください。
不動産投資で自己破産はする!?失敗した時の結果と回避する5つの対策を紹介
不動産投資を始めたら確定申告が必要になる
不動産投資は始めたらそれで終わり、うまく運用できていればいいというわけではありません。毎年確定申告が必要です。
節税したい方は毎年の収入および経費の計算をして、税務署に確定申告を提出します。
しかし、確定申告は正しく行えていないと、後々追加で税金を支払うことになったり、税務調査が入ったりする恐れがあります。不動産投資を行う方は、確定申告についても事前に勉強しておく必要があるでしょう。
節税も見据えた不動産投資の相談ならネイチャーグループへ
節税を見据えた不動産投資を検討している方はたくさんいるでしょう。
しかし、希望どおりの節税効果を得るのは簡単ではありません。なぜなら、何が収入になり、何が経費になるのかなどを判断するのは容易ではないからです。
さらに、確定申告も必要になります。所得控除や税額控除などを活用しながら、適切に申告しなければいけません。
そのため、不動産投資への知識が浅い方や確定申告のことがよくわからない方には、ややハードルが高いでしょう。
「じゃあ、どうすればいいの?」とお悩みの方は、ぜひネイチャーグループにお任せください。
私たちネイチャーグループは、日本最大級のコンサルファームです。資産運用と税務に特化しており、年間相談件数2,000件以上、累計相談件数1万件以上と実績も豊富です。
節税も見据えた不動産投資のことなら、ネイチャーグループにご相談ください。
海外不動産にかかる税金は多くて複雑!申告方法と節税ポイントも紹介
まとめ:不動産投資は節税だけでなく資産を増やす・守る目的も忘れずに
不動産投資をすれば節税可能です。減価償却や損益通算などをうまく活用することで、税負担を軽減できます。
特に1年間の所得が900万円以上の方はより大きな節税効果を得られるため、積極的に運用を検討したいところです。
ただし、不動産投資の本質は資産を増やすこと、守ることです。節税だけにとらわれず、資産を安定して増やせるのか、正しく資産を守れるのかといった広い視野を持って投資しましょう。
ネイチャーグループは、不動産投資への知識と経験が豊富なアドバイザーが在籍しています。資産を増やすことから節税のことまでしっかりとサポートいたします。
また、税務のプロでもあるため、確定申告についてのサポートも可能です。
「不動産投資を検討している」「節税したい」という方は、ネイチャーグループへお気軽にお問い合わせください。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
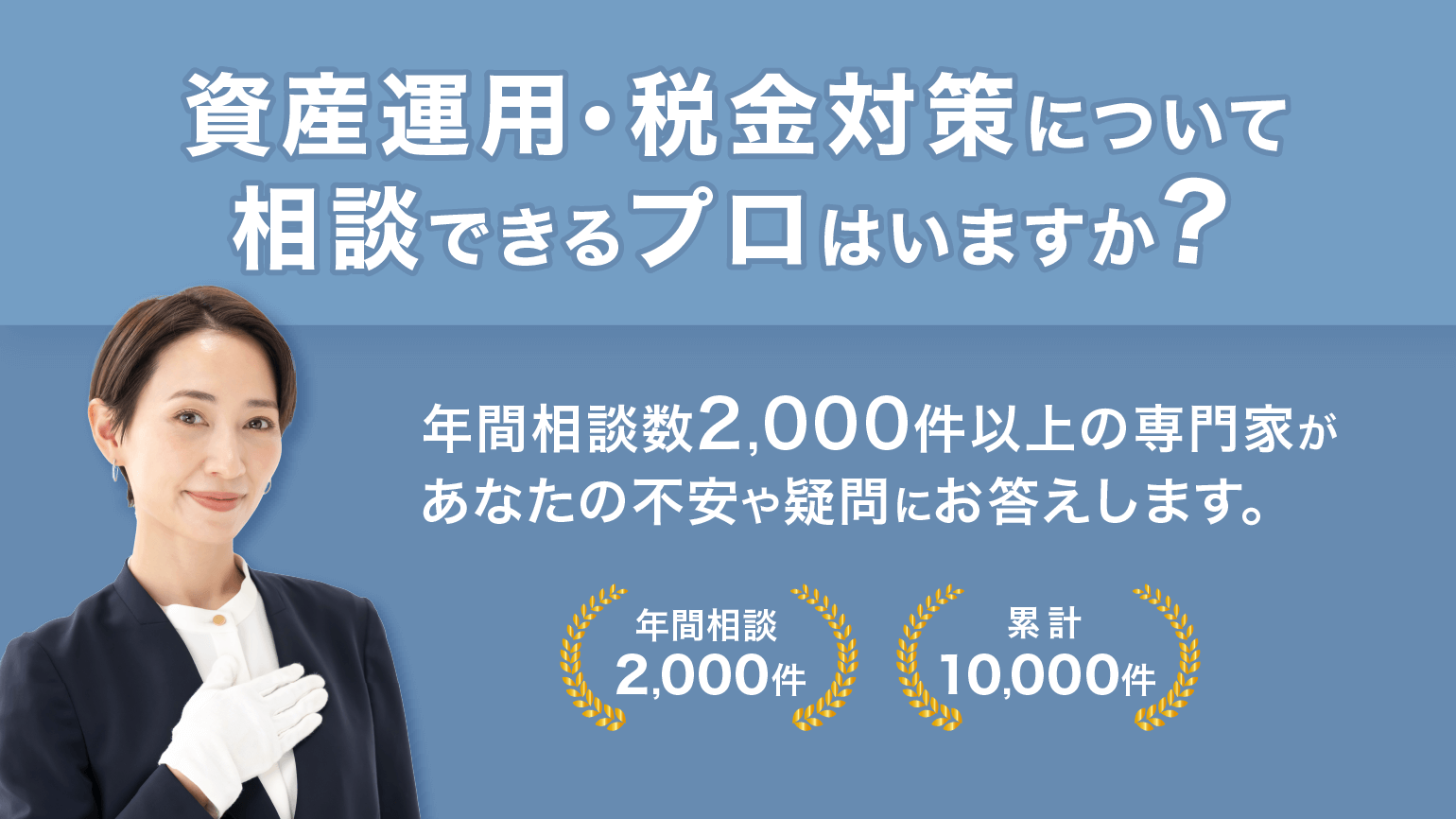
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用