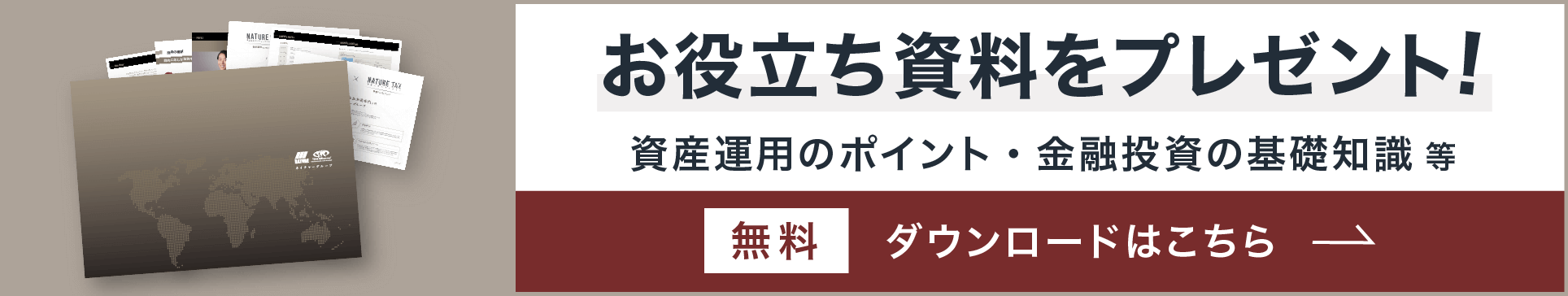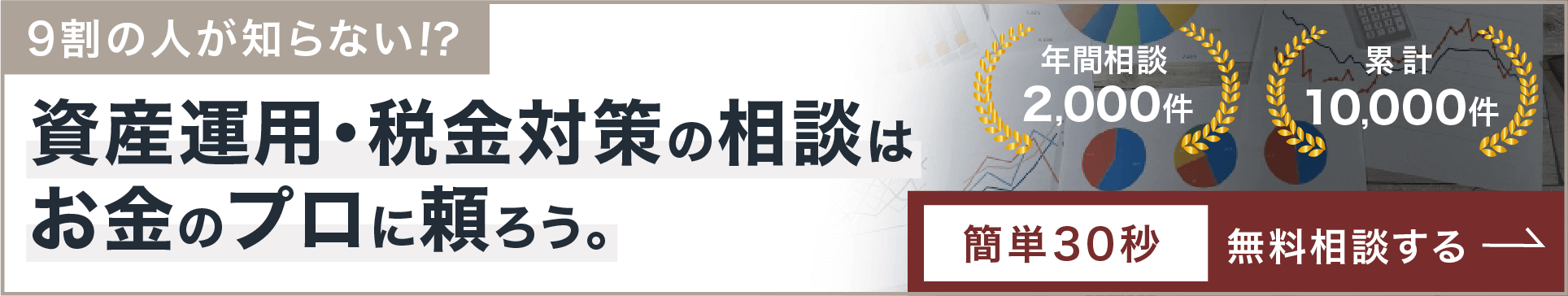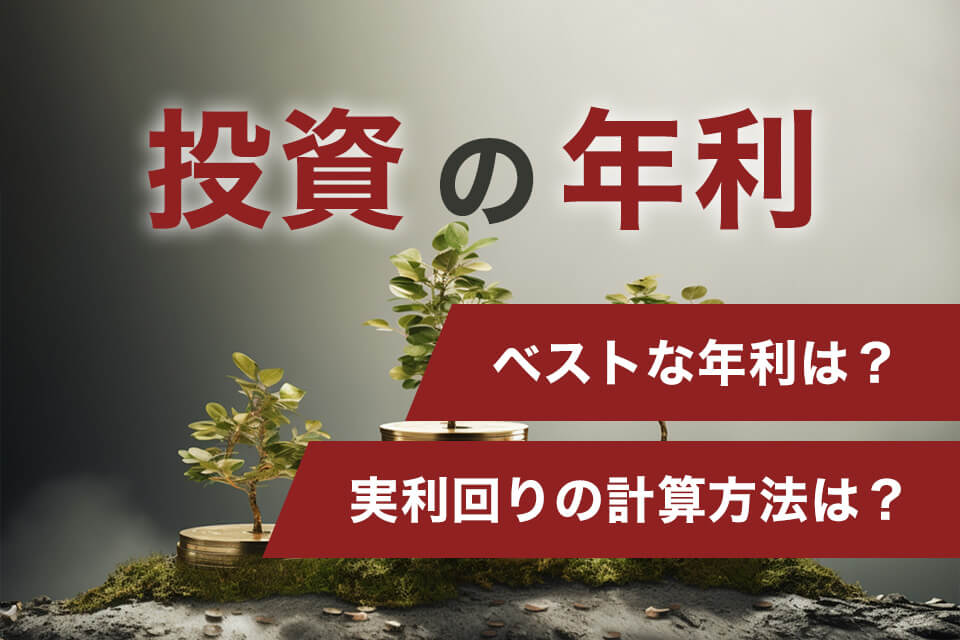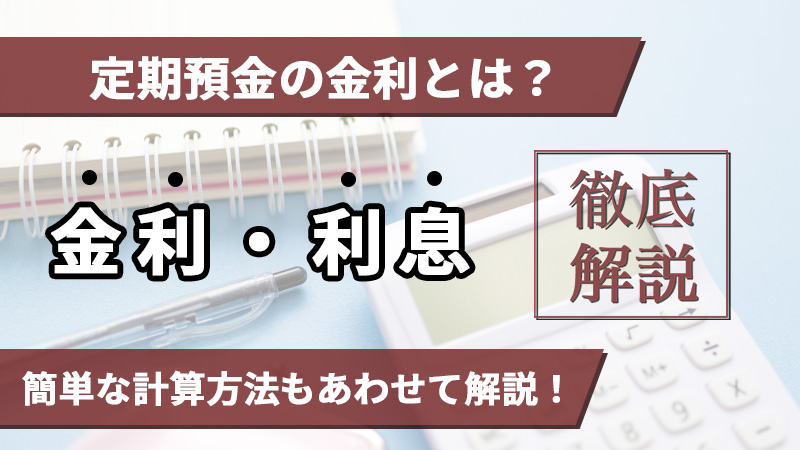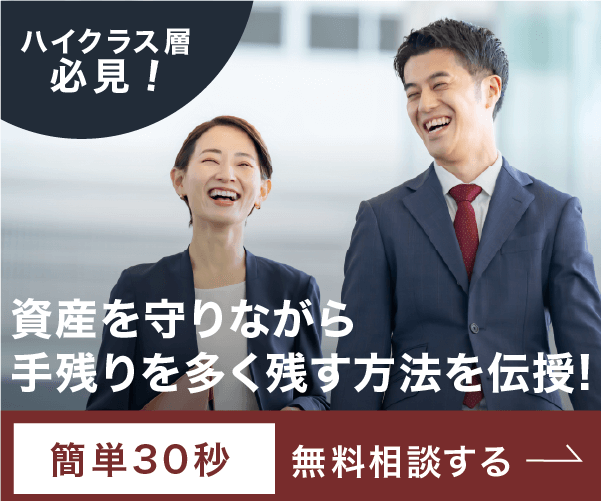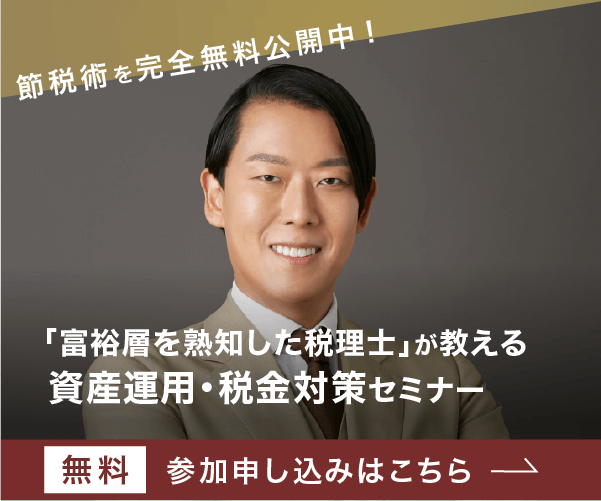![]() 2020年10月7日
2020年10月7日![]() 2025年4月24日資産運用
2025年4月24日資産運用
投資信託の確定申告完全ガイド|初心者もこれで安心!注意点も解説

勤務先から給与を得ている会社員の場合、個人的に確定申告を行う機会はほとんどありません。しかし、投資信託で副収入がある方は「利益が出たときに確定申告をしなくてよいのか」と疑問に感じることもあるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、投資信託における確定申告の取り扱い、行う際の注意点について詳しく解説します。
ケース別に確定申告が必要かどうかをご紹介しますので、自分が対象になっているかチェックしてみてください。
目次
- 【確定申告不要】投資信託の分配金の仕組みと課税ルールを解説
- 特定口座を利用した確定申告不要の仕組みを詳しく解説
- 投資信託の売却益と確定申告|源泉徴収口座なら手続き不要
- 投資信託で確定申告が不要になる8つのケース【条件別に解説】
- NISAとつみたてNISAの非課税枠を活用する際の注意点
- 初心者でも安心!確定申告に役立つ簡単ステップ
- 投資信託で確定申告が必要になるケースとその理由
- 投資信託の確定申告のやり方
- 投資信託の確定申告で気をつけるべきポイント【初心者必見】
- 投資信託の確定申告に関するよくある質問
- 投資信託の確定申告・税務に関するお悩みはネイチャーグループへ
- まとめ:投資信託の確定申告は原則不要!したほうがいいケースも把握しておこう
【確定申告不要】投資信託の分配金の仕組みと課税ルールを解説

投資信託で得られる利益には、分配金と売却益の2つに大別されます。そのうち分配金は、普通分配金と特別分配金の2種類にわけられます。
| 普通分配金 | 運用によって得られた、個別元本を上回る利益のこと |
|---|---|
| 特別分配金(元本払戻金) | 決算後の個別元本が決算前を下回っている際に、投資家へ差し戻される元本の一部のこと |
では、普通分配金と特別分配金はそれぞれ確定申告が必要になるのかみていきましょう。
普通分配金の確定申告は基本不要
投資信託で得られる普通分配金は、課税対象となります。
しかし、特別口座で源泉徴収を行っている場合、一般的に差し引かれた後の金額が入金されます。つまり、個人で税金を申告する必要はありません。
ここで、2024年1月現在の税率も確認しておきましょう。合計で20.315%の税金がかかります。
- 所得税(復興特別所得税を含む):15.315%
- 地方税:5%
なお、入金前の金額には税金も含まれているため、税率を反映させると実際に利益が算出できます。
特別分配金の確定申告は不要
特別分配金は、決済前の個別元本と比べて、分配金支払い後の元本が低い場合に補填する意味合いで投資家たちへ戻されるお金を指します。
つまり、元本の一部であり利益ではないため、税金は課せられません。
投資信託で保有資産のさらなる向上を望まれる方に、資産運用・税金対策に特化した個人専門のコンサルファームが正しい節税方法をお伝えしています。税務効果も考慮した資産運用について気になる方は、ぜひ一度ネイチャーグループへご相談ください。
\【期間限定】今だけAmazonギフトカードプレゼント!/
特定口座を利用した確定申告不要の仕組みを詳しく解説
投資信託で得られる利益に対しては税金が発生しますが、特定口座を利用することで確定申告が不要になるケースが多くあります。
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。「源泉徴収あり」の場合、証券会社が利益から税金を差し引いて納税まで行うため、原則として個人が確定申告をする必要はありません。これにより、特定口座は投資初心者や給与所得者にとって利便性の高い仕組みとなっています。
一方、「源泉徴収なし」の特定口座を選んでいる場合や、複数の口座で損益通算を行いたい場合には、利益や損失を自分で計算して確定申告を行う必要があります。
例えば、A証券で10万円の利益が出て、B証券で5万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで最終的な課税対象額は5万円です。この計算は「源泉徴収あり」の場合でも自動的には行われないため、確定申告が必要です。
特定口座を利用する際は、自分の投資スタイルや管理のしやすさを考慮し、源泉徴収の有無を適切に選ぶことが欠かせません。
投資信託の売却益と確定申告|源泉徴収口座なら手続き不要

投資信託を売却した際の利益は、譲渡所得として課税対象となります。申告分離課税であるため本来は確定申告が必要で、税額は分配金と同様20.315%の税率で算出可能です。
とはいえ、源泉徴収ありの「特定口座」を利用している方は、利益から自動的に税金が差し引かれるため、確定申告は必要ありません。
ただし、源泉徴収ありの「特定口座」で取引していても、複数の口座間で損益通算したい場合や、損失を翌年に繰り越したい場合には、確定申告が必要です。
投資信託で確定申告が不要になる8つのケース【条件別に解説】
投資信託で得た利益は、一定の条件に満たない場合に確定申告をする必要があります。しかし、実際には源泉徴収ありの特定口座を開設して運用している方が多いため、ほとんどの方が申告しなくてもよいと考えてよいでしょう。ここでは、確定申告が必要ない8つのケースをご紹介します。
源泉徴収ありの特定口座を利用している
投資信託の売却益は、株式の売却益と同様「譲渡所得」となり、申告分離課税によって課税されます。
しかし、取引に利用している口座が「源泉徴収あり」と設定されている特定口座の場合、利益が発生しても確定申告は必要ありません。信託先が分配金を入金する際、あらかじめ所得税や地方税を差し引いて振り込むためです。
ただし、複数の口座で損益を合算したいときや、損失を繰り越したいときには、申告しなければなりません。
一般口座で取引している方も別途申告が必要となるため、口座を開設する際は各口座の違いを十分確認しておきましょう。
「2,000万円以下の年間給与所得」で「投資などの利益が年間20万円以下」
勤務先から得ている給与収入と投資信託による利益が一定額以下であれば、確定申告は不要です。以下の条件を満たしているか確認しましょう。
- 給与収入が年間2,000万円以下
- 投資(投資信託)で得た利益が年間20万円以下
- 給与の支払いは1か所からのみ
この場合の利益とは、投資信託以外の資産運用による利益も含みます。複数の口座を所有している方は、合計金額で判断する点にも注意が必要です。
「400万円以下の年間年金収入」で「投資等の利益が20万円以下」の場合
公的年金等を受け取っている方は、給与収入ではなく年金額から確定申告の必要性を判断します。以下の2つに該当する場合は申告が不要です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
- 投資(投資信託)で得た利益が年間20万円以下
公的年金等の収入には、国民年金や厚生年金だけでなく、企業年金や確定給付企業年金、外国の社会保険に基づき支給される年金も含まれます。年金の金額が分からない場合は、以下の3つの方法で確認可能です。
- 日本年金機構のオンラインサービス「ねんきんネット」を利用する
- ねんきんダイヤル・年金事務所で照会する
- ねんきん定期便を確認する
ねんきん定期便は、毎年誕生日の前後に送られますが、作成時点でのデータであり最新の情報ではありません。具体的な情報を知りたい方は、他の2つの方法が確実です。
投資信託で損失が出ている
投資信託によって損失が出た場合は、配当所得や譲渡益は発生しないため申告の必要はありません。ただし損益通算や繰越控除を利用する場合は、確定申告を行いましょう。
また、1年間で得た所得が控除額を下回る方は、税金を申告することなく利益を受け取れます。基礎控除のみの場合、控除される金額は以下の通りです。
- 所得税:48万円
- 住民税:43万円
所得には、給与所得だけでなく投資信託の利益も含まれます。他の投資で多額の利益を得た場合は申告が必要になるため、全ての所得を明らかにして判断しましょう。
NISA口座を投資信託に利用している
NISAは、毎年一定の範囲内であれば、購入した金融商品で得られた利益が非課税となる制度です。
2024年(令和6年)から新NISA制度が始まりましたが、2023年までのNISAでは一般NISAで年間120万円まで、最大5年間非課税で保有できます。NISA口座で投資信託の取引を行っている方は、確定申告の必要がありません。
ただし、非課税枠120万円を超えて購入した金融商品に対する利益は一般口座で運用されるため、課税対象となります。
NISA口座を投資信託に利用している
NISAは、毎年一定の範囲内であれば、購入した金融商品で得られた利益が非課税となる制度です。
2024年(令和6年)から新NISA制度が始まりましたが、2023年までのNISAでは一般NISAで年間120万円まで、最大5年間非課税で保有できます。NISA口座で投資信託の取引を行っている方は、確定申告の必要がありません。
ただし、非課税枠120万円を超えて購入した金融商品に対する利益は一般口座で運用されるため、課税対象となります。
つみたてNISA口座を投資信託に利用している
つみたてNISAは2023年末までのNISAのひとつで、年間投資額40万円までの金融商品であれば、最大20年間非課税で運用可能です。
通常のNISA口座と同様、利益が発生しても確定申告の義務はありませんが、非課税枠を超えて投じた分の利益に関しては対象外です。
また、ETFの分配金を「株式数比例配分方式」以外で受け取る場合も、確定申告の必要があります。
確定申告を避けたい方は、登録配当金受領口座方式や従来方式を選択しないように注意しましょう。
iDeCoで投資信託を運用している
私的年金のひとつであるiDeCo(確定拠出型年金)は税制上の優遇措置があり、運用益は非課税のため確定申告が不要です。
ただし、下記に関しては確定申告が必要となる場合もあります。
- 掛金を支払ったとき(年末調整を受けられない場合)
- 年金として受け取るとき
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、所得控除の対象となります。控除を受けるには確定申告が必要ですが、年末調整を受けられる会社員等は不要です。また受け取り時に一時金を選択すると源泉徴収によって課税されますが、年金として受け取る際には確定申告の対象となります。
投資信託で利益確定(売却)を一度も行っていない
投資における所得税は、利益が確定したタイミングで課税されます。したがって、投資を始めてから一度も売却していない方は確定申告が必要ありません。
口座の種類や収入状況が確定申告の対象に該当する場合でも、売却して利益を得るまでは申告しなくてよいと考えましょう。
ただし、運用によって発生した分配金は課税対象となります。「源泉徴収あり」の特定口座を選択していない等、確定申告不要のケースに該当しない場合には、手続きが必要です。
NISAとつみたてNISAの非課税枠を活用する際の注意点
NISA(少額投資非課税制度)とつみたてNISAは、投資信託や株式投資によって得た利益が非課税になる制度です。NISAでは年間120万円、つみたてNISAでは年間40万円の投資分に対して非課税枠が設定されており、効率的に資産を運用できるメリットがあります。しかし、非課税枠を超えて投資した分は一般口座扱いとなり、通常の税率(20.315%)が適用されるため注意が必要です。
また、NISA口座では5年間の非課税期間が設けられており、期間終了後には「ロールオーバー」の手続きを行うことで非課税期間を延長できます。手続きを忘れると課税口座へ自動的に移行してしまうため、期限内に手続きを完了することが重要です。
つみたてNISAでは非課税期間が20年間と長期にわたるため、非課税枠をフルに活用する計画を立てることで、長期の資産形成が可能になります。制度の詳細を理解し、課税対象になるリスクを避けながら運用を行いましょう。
初心者でも安心!確定申告に役立つ簡単ステップ
投資信託で利益を得て確定申告が必要になった場合でも、手順を理解しておけば難しくありません。
まず、確定申告に必要な書類として、証券会社から送付される「年間取引報告書」や「配当金支払通知書」を準備します。給与所得者の場合は「源泉徴収票」も併せて確認しましょう。
次に、国税庁の「確定申告書作成コーナー」やe-Taxを利用することで、画面の案内に従って入力するだけで簡単に申告書が完成します。提出方法は「オンライン申請」「郵送」「税務署への持参」の3種類があり、提出期限は毎年2月16日〜3月15日です。
初めて確定申告を行う方は、早めの準備がポイントです。証券会社から送付される書類を正確に確認し、余裕を持って手続きを進めることでスムーズに申告を完了させられます。
投資信託で確定申告が必要になるケースとその理由

投資信託で分配金や売却益が得られても、基本的に確定申告は不要です。しかし中には例外がある上、確定申告することで税金を軽くできる場合もあります。ここでは、投資信託をしていて、確定申告したほうがよいケースについて解説します。
簡易申告口座や一般口座を使用している場合
投資信託の取引が可能な口座の種類は、以下の3つです。
- 一般口座
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 特定口座(源泉徴収あり)
上記の中で確定申告が不要なのは原則、「特定口座(源泉徴収あり)」のみです。一般口座や「特定口座(源泉徴収なし)」の「簡易申告口座」を利用している方で、以下の条件に該当する場合、確定申告が必要です。
- 給与収入が年間2,000万円を超えている
- 給与収入以外に年間20万円を超える所得がある
- 主たる給与以外の給与とそれ以外の所得が20万円を超えている
確定申告が必要な条件に当てはまるなら、以降で紹介するやり方で手続きを進めてください。
確定申告で損益通算・繰越控除を利用する場合
投資信託で取引した1年間で損失が生じると、税金は課されません。確定申告の義務もありませんが、申告することで以下のメリットが得られます。
- 損益通算:株式の売買や投資信託の損益を通算して相殺する
- 繰越控除:損益通算で相殺できない損失を翌年以降に繰り越す
損益通算は、複数の口座を所有して資産運用している方がメリットを得られる手続きです。
例えば、5万円の利益と3万円の損失を損益通算すれば、利益は2万円になります。課税対象が5万円から2万円に減るため、税額も減るという仕組みです。
また、損益通算しても相殺できない損失は、繰越控除によって最長3年間繰り越せます。翌年以降も利益を控除できるため、税金を節約するのに有益な方法といえるでしょう。
確定申告することで還付金を受け取れる場合
投資信託では多くの場合で確定申告をしなくても問題ありませんが、申告したほうがお得になるケースがあります。源泉徴収によって、余分な税金を支払っていることもあるためです。
例えば、給与所得と投資信託の分配金がともに課税対象となる金額以下であっても、源泉徴収ありの特定口座で取引していると税金が差し引かれます。これは本来納めなくてもよい税金です。源泉徴収された税金は確定申告すれば返金されます。
- 本来であれば税金が発生しない
- 源泉徴収ありの特定口座で投資信託を続けている
以上2つの条件に該当するなら、確定申告をして過払い分を還付してもらいましょう。税金が戻ってくれば、次回の投資信託に活用できます。
ただし、確定申告をすることにより、配当金等を他の所得と合算するため、社会保険関係や各種人的控除の金額に影響が出ることがあります。金額が大きい場合は専門家に相談することをおすすめします。
投資信託の確定申告のやり方

投資信託で分配金や売却益を獲得し、確定申告が必要であると判断した方は、必要な書類を準備して期限内に手続きを進めていきましょう。会社員など確定申告をしたことがなく慣れていない方は、ここで紹介する内容を参考に、余裕を持って準備を進めてみてください。
確定申告の申告先・期限を把握する
確定申告書は、納税者の住所地を管轄している税務署に提出します。毎年1月1日から12月31日までの1年間で生じた所得について、2月16日から3月15日までの間に確定申告して納税する決まりです。
必要書類を準備し、以下のいずれかの方法で提出します。
- 税務署に直接持参する
- e-Taxを利用する
- 郵便または信書便で税務署へ郵送する
- 税務署の時間外収集箱へ投函する
(参考:国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」 )
確定申告の必要書類を用意する
確定申告に必要な書類は、口座の種類によって異なります。
| 一般口座 | ・国内投資信託取引報告書 ・取引残高報告書(取引明細が記載されているもの) ・配当金等の支払通知書 ・売買証明書 |
|---|---|
| 特定口座 | 年間取引報告書 |
一般口座の場合は「取引報告書」や「収益分配金のご案内・再投資のご案内」をもとに年間の譲渡損益を計算し、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。
上記の書類提出は必要ありません。しかし、税務署から問い合わせがあったときに証拠として提示を求められる可能性があるため、しっかりと保管しておきましょう。
確定申告書の書き方
確定申告の際は、1月1日〜12月31日の取引内容を細かく記載しなければなりません。源泉徴収ありの特定口座や簡易申告口座の場合、信託先から年間取引報告書が送付されます。以下の項目が明確になるため、これを活用して金額を記入しましょう。
- 勘定の種類
- 源泉徴収税額
- 外国所得税額
- 売却取引の合計額
- 損失額
- 分配金額
金融機関によって報告書の項目は異なりますが、確定申告に必要な情報は網羅されています。そこで、紛失した場合は早めに問い合わせて再発行の申請をするといいでしょう。
なお、確定申告のやり方はこちらの記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみてください。
▽確定申告のやり方は?申告書の作成方法や注意点、基本的なポイントを徹底解説
投資信託の確定申告で気をつけるべきポイント【初心者必見】

投資信託で分配金や売却益を獲得し、確定申告が必要であると判断した場合は、余裕を持って準備を進め、期限内に手続きを完了させましょう。仮に申告が遅れた場合は、ペナルティを受けることになります。ここではペナルティの詳細も含めて、投資信託での利益を確定申告する際の注意点について解説します。
配当控除を利用する場合は確定申告が必要になる
投資信託で得られた分配金は、配当控除を受けられる場合があります。
ただし、配当控除を利用するには、総合課税として確定申告が必要です。
控除率は、株式組入比率と外貨建資産の組入比率によって異なり、それぞれ75%を超える場合は控除を受けられません。
| 非株式組入比率 | |||
|---|---|---|---|
| 50%以下 | 50%超75%以下 | ||
| 外貨建資産組入比率 | 50%以下 | 所得税5.0%(2.5%) 住民税1.4%(0.7%) |
所得税2.5%(1.25%) 住民税0.7%(0.35%) |
| 50%超75%以下 | 所得税2.5%(1.25%) 住民税0.7%(0.35%) |
||
※()内は課税総所得金額が1,000万円を超える場合
確定申告の未申告がばれるとペナルティが発生する
期限内に確定申告がない場合、申告漏れには加算税が、納税が遅れたときには延滞税が課せられます。
<無申告加算税>
原則は納税すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて算出されます。ただし調査前に自主的に申告した際は、5%です。また以下を満たす場合は、加算税は発生しません。
- 自主的な期限後申告が法定申告期限から1か月以内の場合
- 期限内申告の意思があったと認められる場合
延滞税の金額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて異なります。
投資信託の確定申告に関するよくある質問
投資信託の確定申告は利益がいくらから必要になりますか?
投資信託の確定申告は、利益が年間20万円を超える場合に必要となります。というのも、投資信託で得られる利益は、給与所得と別物として考える申告分離課税に該当するからです。
ただし、源泉徴収ありの特定口座を開設していれば、源泉徴収は自動で行われるため、自身で個別に確定申告する必要はありません。
サラリーマンの方であっても該当しますので、おさえておきましょう。
投資信託の確定申告の対象となる課税タイミングはいつですか?
投資信託における利益の課税タイミングは、主に以下の3つが挙げられます。
- 分配金(普通分配金)が支払われたとき
- 売却益を獲得したとき
- 運用期間が満期を迎えたとき
課税タイミングを把握しておけば、自分は課税される利益があるのかを確認できるため、スムーズな対応を取れるようになるでしょう。
海外ETFを含む投資信託の確定申告はどうなるの?
海外ETFを含む投資信託では、利益に対して外国税額控除が適用される場合があります。海外ETFの分配金や売却益は、現地で課税されることがあり、これに加えて日本国内でも課税対象となるため、二重課税のリスクが発生します。
例えば、アメリカのETFから分配金が支払われる際、現地で源泉徴収される税率は30%です。しかし、日米租税条約に基づき、日本居住者の場合は軽減税率10%が適用されます。この税金は確定申告時に「外国税額控除」を申請することで、日本国内の税額から控除される仕組みです。これにより、二重課税を避けることができます。
各国ごとに税率や控除の適用条件が異なるため、海外ETFの取引報告書や配当金明細を正確に保管し、確定申告時に必要な手続きを行うことが重要です。
複数の特定口座を持つ場合の注意点は?
複数の特定口座を利用している場合、それぞれの口座で発生した利益や損失を正確に把握しなければなりません。
例えば、A証券会社で10万円の利益、B証券会社で5万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで課税対象額を5万円に減らせます。この損益通算を適用するには、確定申告が必要です。
各証券会社から送付される「年間取引報告書」を基に正確に計算し、すべての口座を合算して申告を行うことで、余分な税金の支払いを防ぐことができます。複数口座の管理は煩雑になりがちなため、定期的に確認し、報告書を正確に保管することが重要です。
損益通算ができる他の金融商品には何がある?
投資信託の損失は、株式やETF、REIT(不動産投資信託)といった他の金融商品の利益と損益通算が可能です。
例えば、投資信託で10万円の損失が発生し、株式取引で15万円の利益が出た場合、損益通算によって課税対象額は5万円に抑えられます。
さらに、損失が通算しきれない場合は「繰越控除」によって、最長3年間損失を繰り越すことができます。
例えば、2024年に10万円の損失が出た場合、2025年以降に発生する利益と相殺することで税負担を軽減することが可能です。
繰越控除を受けるには、毎年継続して確定申告が必要である点にも注意しましょう。
投資信託の確定申告・税務に関するお悩みはネイチャーグループへ
自分で確定申告を進めたい場合は、国税庁の公式サイトにアクセスして該当ページを参考に作成しておきましょう。
そこでもし、計算ミスや記入漏れのリスクを避けたい方や、少しでも不安がある方は、国税庁「確定申告書作成コーナー」の活用や、資産運用の専門知識をもつ税理士法人への相談が向いています。
またこの他、資産運用のセミナー(税務関係)に参加して理解を深める方法も有用です。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、確定申告に必要な内容をはじめとして、資産運用に特化したセミナーを開催しています。資産運用についての疑問や不安を解決させたい方は、ぜひご相談ください。
\投資信託よりも確実に増やす方法とは?/
まとめ:投資信託の確定申告は原則不要!したほうがいいケースも把握しておこう

投資信託を行う投資家の多くは、確定申告を必要としません。
ただし、条件によっては申告しなければならないため、対象となる条件を把握しておくといいでしょう。利益が少なかったり損失が生じたりした場合は、申告することで得をするケースもあります。
確定申告に関して不安のある方は、専門家に相談して適切なアドバイスを求めましょう。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、資産運用に特化したサービスを展開する税理士法人です。現在投資を行っている方だけでなく、これから始めたい方もぜひ一度お問い合わせください。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
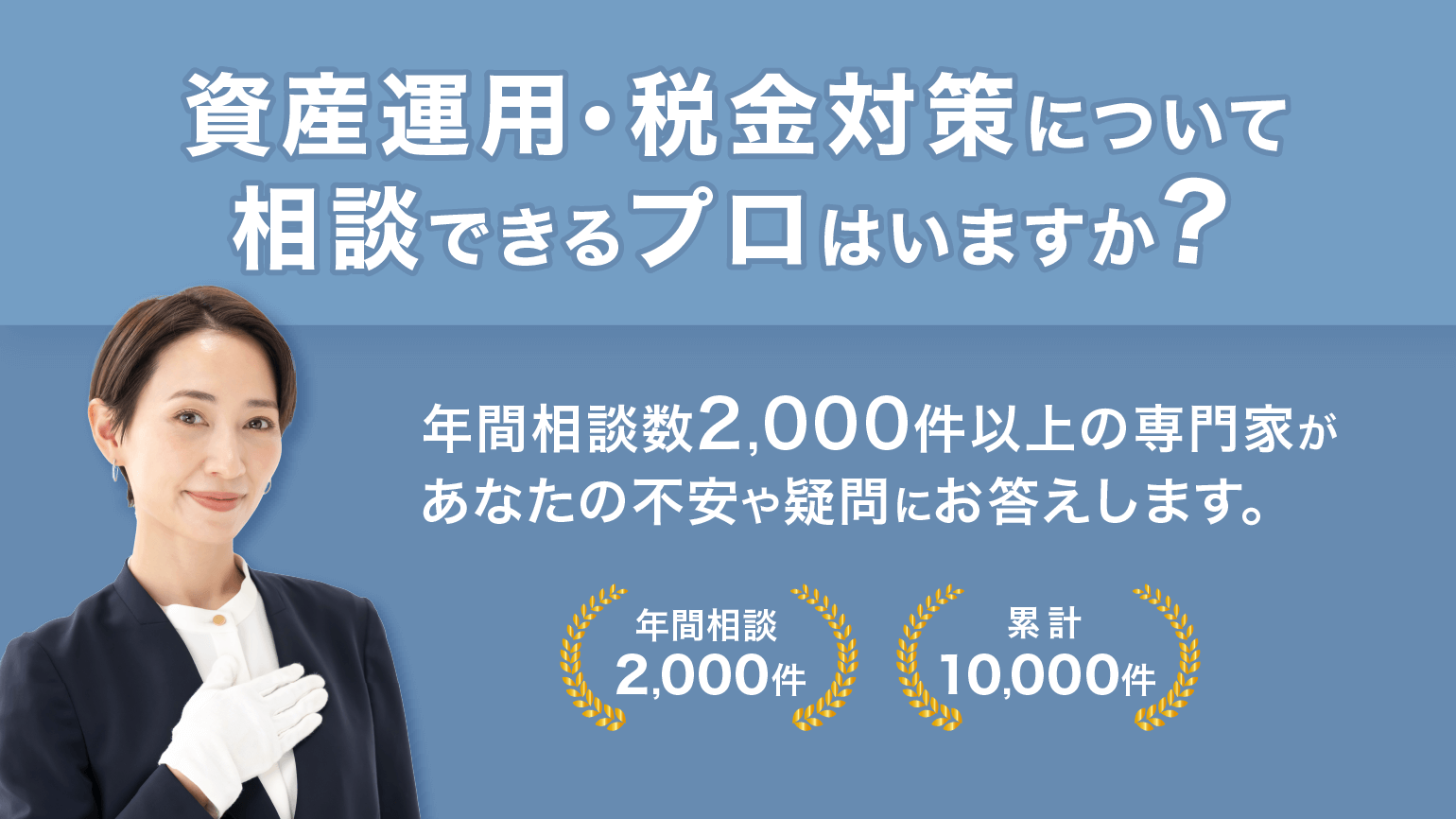
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用