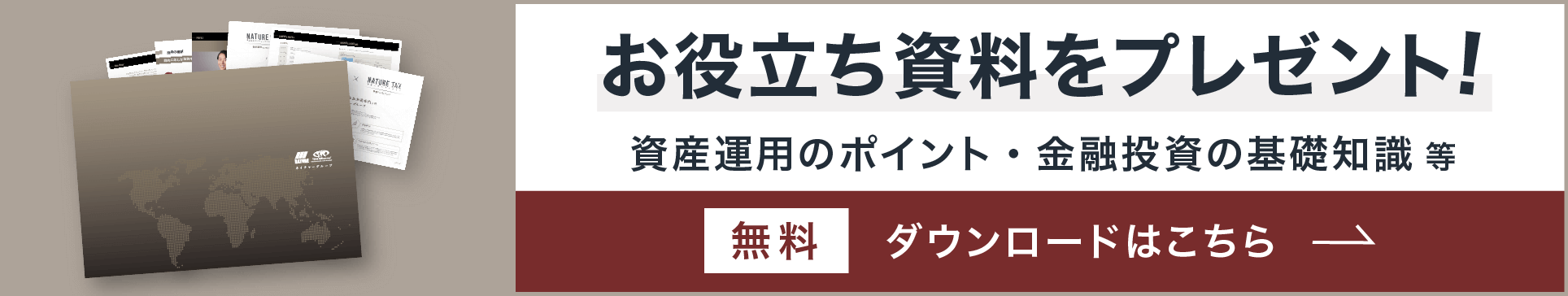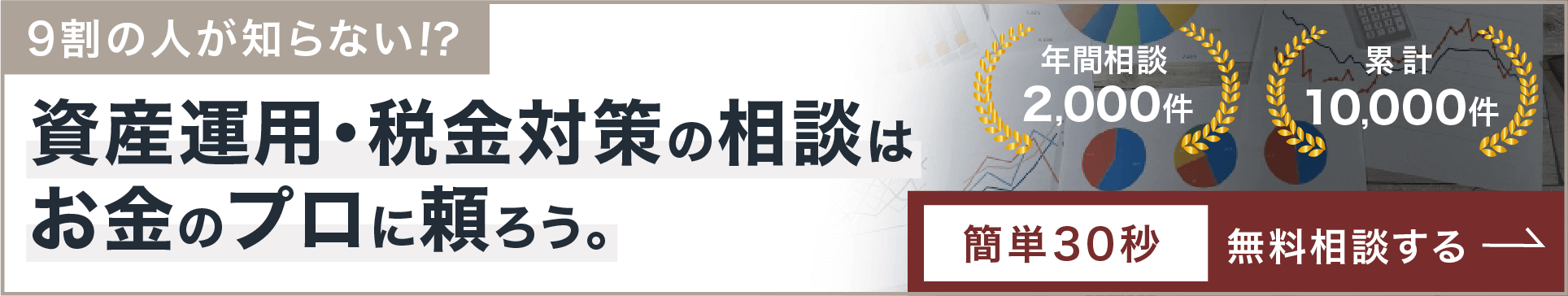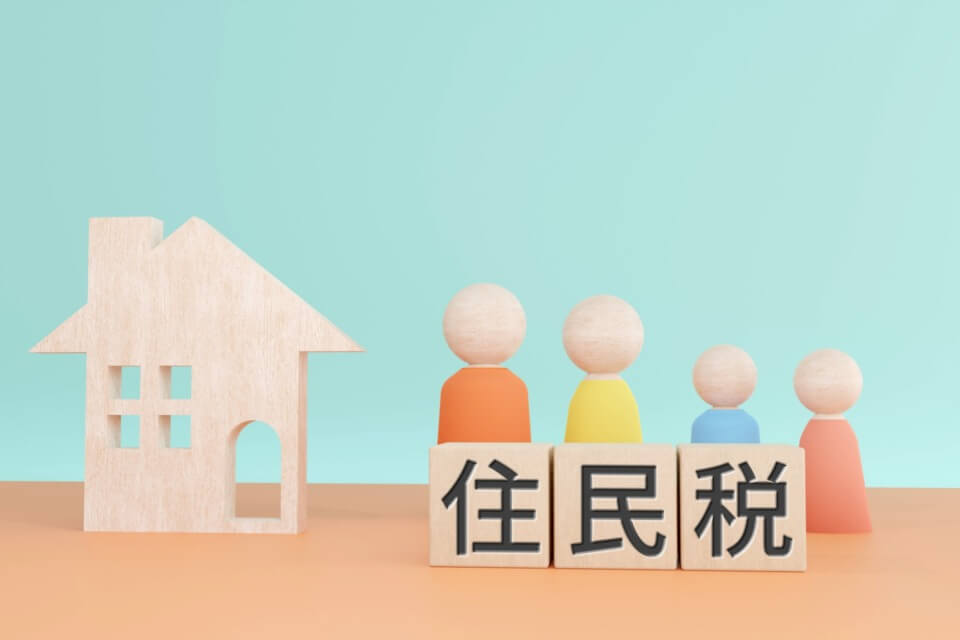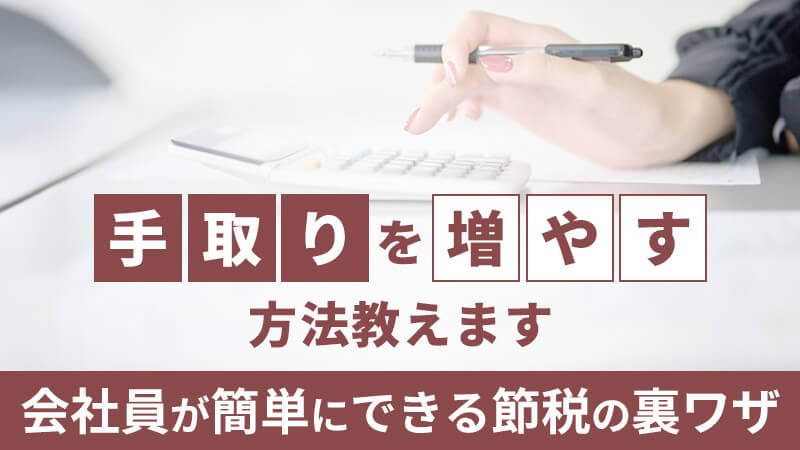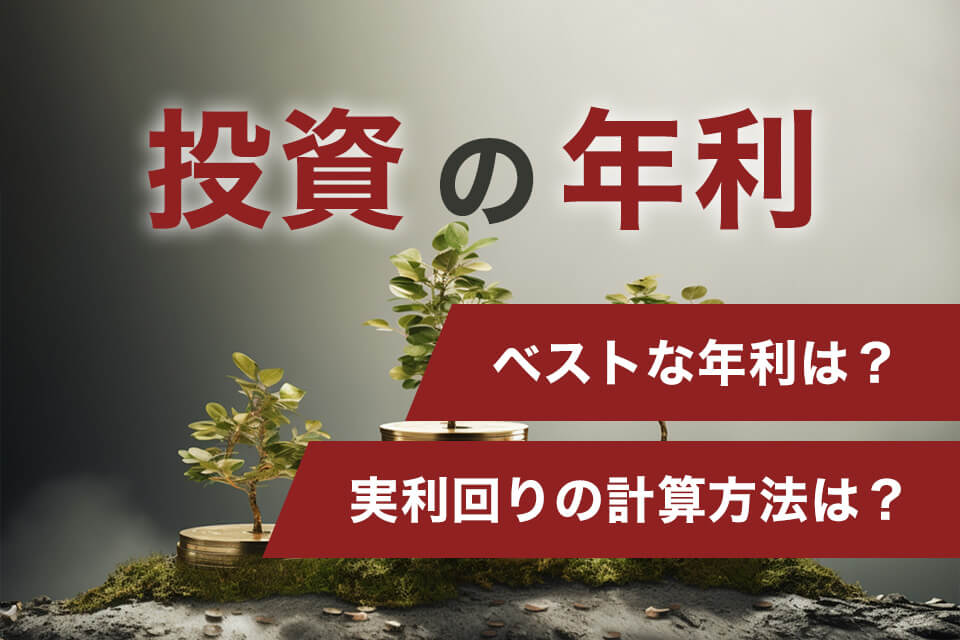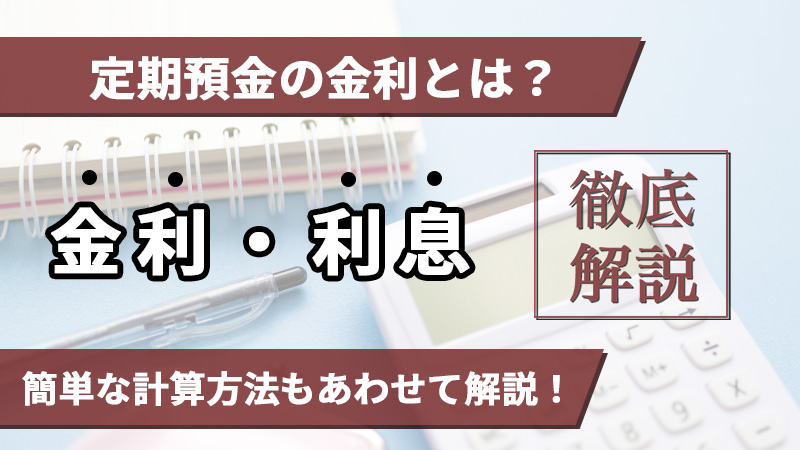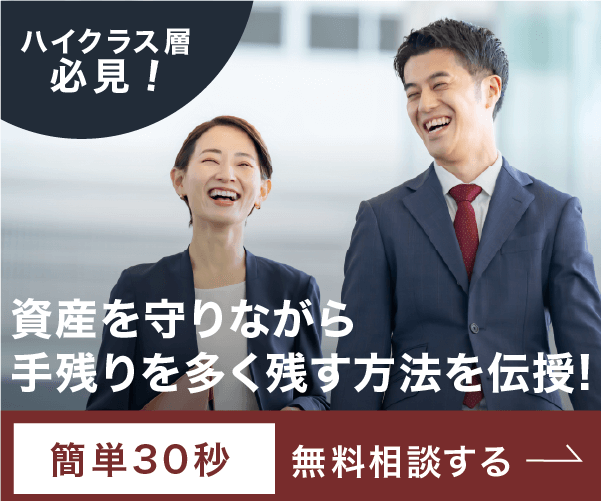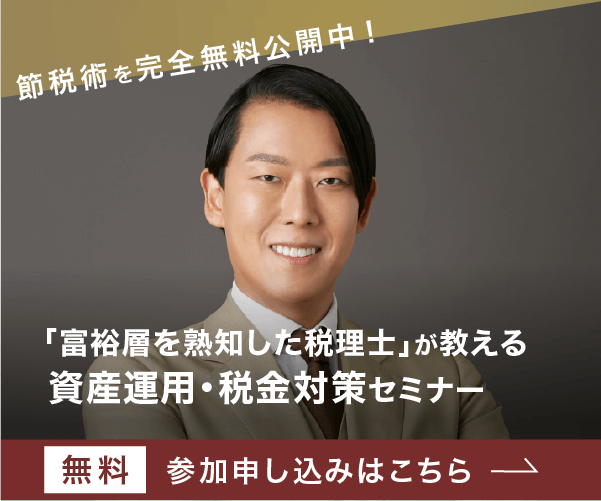![]() 2021年1月18日
2021年1月18日![]() 2023年1月10日税務
2023年1月10日税務
確定申告のやり方は?申告書の作成方法や注意点、基本的なポイントを徹底解説

毎年2月~3月は確定申告の時期です。確定申告は納税義務を果たすために必要ですが、相応の手間がかかるものであり、簡単ではありません。特に、初めての確定申告では分からないことが多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、書類の準備から納税までステップに分けて手続きを解説します。流れや青色申告と白色申告の違いなどを把握することで、自分に適したやり方が判断できるでしょう。
目次
確定申告が必要なケースとは?

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得にかかる税金を納めるための手続きのことです。申告納税方式といい、納税者自身が計算して申告します。ただし、会社員の方は年末調整が確定申告代わりになることが多く、一部の例外を除けば会社に任せておけば問題ありません。
所得税の納税が必要な場合
個人事業主やフリーランスの方は、確定申告で所得税を納付しなければなりません。次の手順で1年間の所得税額を計算しましょう。
- 1年間の全ての収入から経費を差し引き「所得」を把握する
- 所得から所得控除(雑損控除、医療費控除、生命保険料控除など)を差し引く
- 「2」の金額を所得税の速算表に従い、「所得税額」を求める
- 「3」の所得税額から税額控除(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除など)があれば差し引き、所得税を求める
なお、株式の譲渡などで収入が発生している場合で、特定口座を利用していない(源泉徴収を受けていない)場合は、他の所得とは分離して税額を計算する必要があります(申告分離課税)。
また、会社員であっても年末調整を受けていない方や、副業の稼ぎが20万円を超える方は確定申告をする必要があります。
(参考: 『所得税の税率|国税庁』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)
所得税の還付を受ける場合
1年間の収益が赤字の場合や源泉徴収によって納税が完了している場合には、所得税の納付義務はありません。したがって確定申告をする必要もありませんが、次のような状況に該当するときは、確定申告することで所得税の還付を受けられます。
・予定納税していた
・年の途中で退職し、年末調整を受けずにいる(源泉徴収税額を納め過ぎている)
・マイホームに特定の改修工事をした、災害などで資産に損害を受けたなどの各種控除がある
所得税の還付は自動で受けられるものではないため、忘れずに手続きを行いましょう。
確定申告はいつまでに申告すればよい?
毎年の確定申告には期限が定められており、原則、期間内に申告・納税を済ませなければなりません。具体的な期限は以下の通りです。
| 申告内容 | 期限 |
|---|---|
| 通常の申告 ※所得税を納税する場合 |
翌年の2月16日~3月15日 |
| 還付申告 ※所得税の還付を受ける場合 |
翌年の1月1日から5年間 |
※期限の末日が土日・祝日に該当する年は、翌開庁日の申告までが期限内扱い
なお、申告・納税が遅れると以下のペナルティーを受けることになります。
・無申告加算税
・重加算税
・延滞税
期限は正しく把握し、遅れることがないよう、余裕を持って申告・納税しましょう。
青色申告と白色申告の違いは?

確定申告する際に押さえておきたいのは、青色申告と白色申告の違いです。特別控除の有無や作成の難易度に関して異なるメリットがあります。適切な方法は申告者により変わるので、メリットだけでなくデメリットも確認しましょう。
白色申告のメリットと注意点
確定申告のうち、比較的簡単な方法が「白色申告」です。事前申請の必要がなく、単式簿記なので作成の負担が少なく済みます。記載する項目が少なく、計算が苦手な方でもスムーズな方法といえるでしょう。ただし、青色申告のような特別控除はありません。
| メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|
| ・事前に申請する必要がない ・収支内訳書の提出のみ ・記入項目が少ない(計算しやすい) |
・特別控除がない |
青色申告のメリットと注意点
青色申告の大きなメリットは、最高65万円の特別控除です。ただし、青色申告をするには申告する年の3月15日まで、または事業開始から2か月以内に開業届と青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません。また、複式簿記が必要で、簿記の知識に長けていないと難しい側面もあります。
| メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|
| ・最高65万円の「青色申告特別控除」が受けられる ・青色事業専従者給与を経費に計上できる ・損失の繰越しや繰戻しができる |
・事前の申請が必要 ・書類作成が難しい(項目が複雑) |
確定申告のやり方|納税までの流れや提出方法
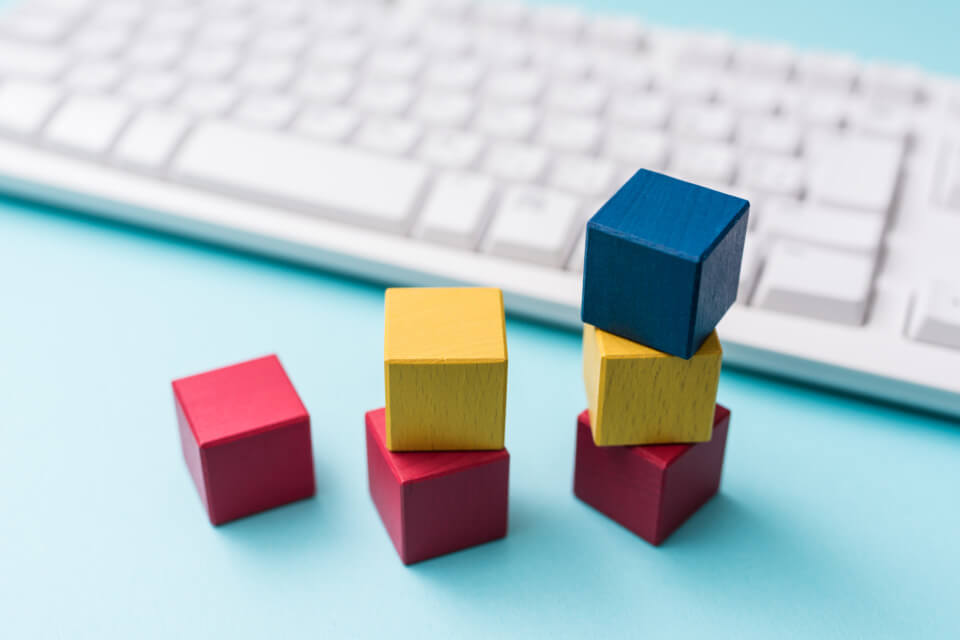
確定申告の際には、収入を記載する申告書の他に口座情報も必要です。申告書を作成する前に情報を整理し、具体的な流れを確認しておくことでスムーズな提出につながるでしょう。ここでは、納税までの流れや注意点について解説します。
1. 必要な書類の準備
確定申告には、確定申告書以外にも以下のような書類が必要です。あらかじめそろえておきましょう。
| 必要な書類 | 内容・役割 |
|---|---|
| 確定申告書 | 1年間の収入や経費を記載 |
| 収支内訳書・青色申告決算書 | 確定申告書とセットで提出 |
| 口座情報 | 還付金がある場合の入金先 |
| 帳簿・領収書(レシート) | 1年間の取引記録を証明 |
| 源泉徴収票(必要な場合) | 差し引かれた源泉徴収の内訳を証明 |
| 医療費控除の明細書(必要な場合) | 年間10万円を超える医療費に対する控除が適用される |
| 社会保険料控除証明書や寄附金受領証明書(必要な場合) | 所定の控除が適用 |
| マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された書類 | 個人番号の確認 |
2. 帳簿の整理
収入や借り入れ、交通費のような必要経費といったお金の出入りを記録した「帳簿」を整理します。帳簿の記帳方式は、白色申告は単式簿記、青色申告ならば複式簿記です。スムーズに整理するために、以下の書類を準備しましょう。
・クレジットカードの明細書
・請求書
・領収書・レシート
・受領書
収入や経費に関わる書類を全て集めて、ひとつずつ帳簿に反映します。量が膨大な場合、1週間や1か月単位に分けて整理するとよいでしょう。個人事業主は帳簿や書類を5年~7年保存します。
3. 確定申告書の作成
1月1日~12月31日の帳簿を整理できた後は、確定申告書類の作成へ進みましょう。かつては自分で計算して手書きで作成する方法が一般的でしたが、現在は専用ソフトを使ったりWebサイトで作成したりといった選択肢もあります。
・手書きで作成する
・税理士に代理を依頼する
・確定申告ソフトを活用する
・国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から作成する
自分に合った方法を選んで作成しますが、不安に感じる方は税理士に依頼するとよいでしょう。
4. 確定申告書の提出
確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書を作成した後は、必要書類と共に税務署に提出します。提出方法は以下の通りです。
・税務署の窓口に提出
・郵便や信書便で税務署へ郵送
・税務署の時間外収受箱へ投函
・国税庁のWeb納税システム「e-Tax」で提出
郵便の準備や手続きの時間が煩わしく感じる場合、外出することなく提出可能な「e-Tax」がおすすめです。
5. 納税
税金を納めれば確定申告は完了です。税の種類によって納付期限が異なります。以下の表を参考に、納税方法もチェックしておくと安心です。
| 納付期限 | 所得税 | 3月15日 |
|---|---|---|
| 消費税 | 3月31日 | |
| 納付場所・方法 | ・e-Tax上でダイレクト納付 ・インターネットバンキングによる納付(e-Taxの利用手続きが済んでいる場合) ・税務署の窓口で現金納付 ・振替納税 ・クレジットカードで納付 ・コンビニエンスストア(30万円以下)で納付 |
|
現金で納める際には、窓口の営業時間に注意しましょう。手続きが面倒なときは、あらかじめ引落口座を指定することで振替納税が利用できます。
確定申告のやり方|確定申告書の書き方
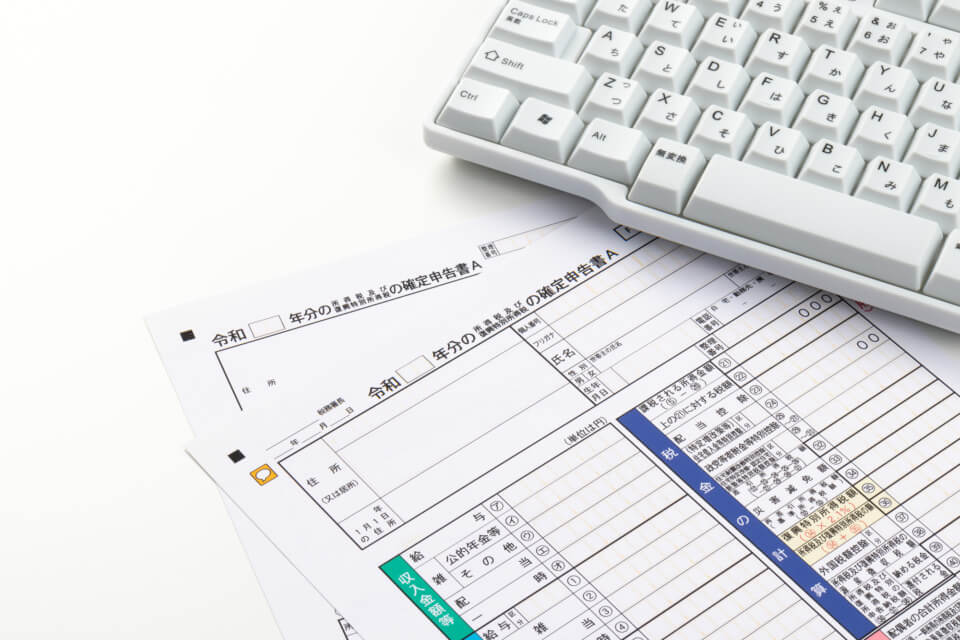
確定申告をするときには、いくつかの書類を用意しなければなりません。その中でも基本となるのが、確定申告表の第一表および第二表の2種類です。それぞれの書類に何を記入するのか、どのような流れで書き進めればよいのかを知れば、作成時のミスを減らせます。ここでは第一表・第二表それぞれの書き方を詳しく見ていきましょう。
確定申告書の第一表の書き方
第一表には申告者の基本情報や納める税額を記入します。以下の流れを参考に、帳簿整理といった準備を終えてから反映しましょう。
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 申告者の名前や住所、電話番号 |
| 収入金額等 | 1年間の収入金額 |
| 所得金額 | 収入金額から経費などを差し引いた金額 |
| 所得から差し引かれる金額(所得控除) | 基礎控除や社会保険料控除などの合計額 |
| 税金の計算 | 課税される所得金額や納める税金を算出 |
| その他 | 配偶者の合計所得金額(配偶者控除を受ける場合)や青色申告特別控除額(青色申告の場合) |
| 還付される税金の受取場所 | 還付金を受け取る口座情報 |
配偶者控除や医療費控除といった控除を受ける場合、記入する項目が多くなります。金額に間違いがないよう、入念に確認しましょう。
確定申告書の第二表の書き方
第二表には、所得に関する詳しい内訳や保険料などの控除額を記入します。主な項目は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 申告者の住所と名前 |
| 所得の内訳 | 収入金額の詳細 |
| 雑所得・配当所得・一時所得に関する事項 | それぞれの所得金額(該当する所得がある場合) |
| 所得から差し引かれる金額に関する事項 | 社会保険料控除や生命保険料控除、寄附金控除(ふるさと納税)といった控除に関する情報 |
| 住民税に関する事項 | 住民税に影響を与える情報(16歳未満の扶養家族がいる場合など) |
確定申告書には住民税に関する事項だけでなく、「事業専従者に関する事項」「事業税に関する事項」もあります。記入の必要性は申告者によって異なるため、事業内容や生活環境に応じて記入しましょう。状況によっては、第三表以降を必要とするケースもあります。
確定申告のやり方|確定申告書の提出はe-Taxがおすすめ

作成した確定申告書を提出する方法は、大きく分けて「税務署に持参」「郵送」「e-Tax」の3種類です。これらの中でも、メリットが大きいe-Taxで提出する方法をおすすめします。
e-Taxでの提出は、利便性が高いだけではなく控除額が大きくなるのもメリットです。ここからはそれぞれのメリットを詳しく解説します。
青色申告特別控除額が65万円になる
青色申告している方は、e-Taxで確定申告書を提出すれば65万円の青色申告特別控除を受けられます。e-Taxを使わなかった場合の青色申告特別控除額は55万円までです。提出方法を変えるだけで所得控除が10万円増えることを考えると、特別な事情がない限りe-Taxで提出するほうがよいでしょう。
なお、複式簿記によらない簡易な帳簿付けでも最大10万円の控除を受けられますが、これを受けている場合はe-Taxを利用しても控除額は上乗せされません。
手間とコストを削減できる
e-Taxはオンラインを利用するため、自宅にいながらいつでも確定申告ができます。税務署へ持参するにはそこに行くまでの時間やコストがかかりますし、郵送での提出も基本的に同じです。
その点、e-Taxであれば確定申告にかかる手間やコストを削減できる点が魅力でしょう。空いた時間はビジネスやプライベートに充てられます。
スマホからでも申告できる
e-Taxを使用した確定申告は、スマホからも可能です。国税庁が用意している確定申告書作成コーナーもスマホから利用できますが、一部の作業に制限があったり、スマホ専用の表示レイアウトになっていなかったりと、多少の不便を感じるかもしれません。
おすすめは、スマホ対応済みの会計ソフトを利用することです。見やすく表示されている上、確定申告の作業を手助けする機能が搭載されています。操作の慣れは必要ですが、簿記に明るくない方でも扱いやすく設計されているでしょう。
確定申告をしない・税金を納めない場合のペナルティ

所得税の納付義務があるのにもかかわらず確定申告をしなかったり、税金をきちんと納めなかったりするとペナルティを受けます。ここでは、主なペナルティである「延滞税」と「無申告加算税」の2種類を解説します。
延滞税
延滞税は、期日までに納税しなかったことに対するペナルティです。2022年時点においては以下の割合で延滞税が課されます。
| 状況 | 延滞税の割合 |
|---|---|
| 納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年7.3%もしくは延滞税特例基準割合+1%のうち、低い割合 |
| 納期限の翌日から2か月を経過した日以降 | 年14.6%もしくは延滞税特例基準割合+7.3%のうち、低い割合 |
振替納税の場合、本来の納期より引き落とし日のほうが遅いものの、期日に口座から引き落とせれば延滞税は発生しません。ただし、期日に引き落とせなかったときは、法定納期限の翌日から延滞税が発生してしまいます。
無申告加算税
確定申告義務があるのにもかかわらず期限までに申告しないと、無申告加算税というペナルティを受けます。2022年時点において、無申告加算税の割合は以下の通りです。
| 納付すべき税額 | 無申告加算税の割合 |
|---|---|
| 50万円まで | 15% |
| 50万円を超える | 20% |
きちんと申告しないと納める税金が大幅に増えるため、毎年の確定申告は期限内に済ませましょう。
確定申告を第三者に依頼する方法もある
確定申告は納税者本人が申告するのが原則ですが、税理士に依頼することも可能です。税理士に確定申告を任せることには、以下のメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・確定申告の手間を削減できる ・日々の帳簿作成も任せられる ・申告の正確さを高められる |
・税理士費用が発生する |
税理士に依頼するとある程度の費用がかかりますが、それを上回るリターンに期待できます。税理士費用は全額経費に計上できるため、複雑な税務を一任するためにも、ぜひ税理士への依頼をご検討ください。
確定申告のご相談はネイチャーグループへ
確定申告の作成は、収入源が多く項目が増えるほど負担が増えます。書類作成や手続きが不安な方は、ぜひネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー・株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお任せください。
さまざまな種類の税金に精通しており、安心して確定申告を任せられる税理士が在籍しています。また、税務に関する総合的なコンサルタントや、資産運用の相談も実施しています。
年間2,000件、累計1万件を超える相談実績があり、税金対策に関するノウハウを生かしたサポートが可能です。確定申告の相談や依頼をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
まとめ

所得税の納付義務がある方は、確定申告を行う必要があります。しかし、確定申告は帳簿の作成や税金の計算、申告、納付などのさまざまな作業が必要です。難しい上、手間がかかるため頭を抱えている方もいるのではないでしょうか。
申告の正確性を高めて予期せぬペナルティを防ぐためにも、信頼できる税理士に一任するのがおすすめです。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)であれば、さまざまな分野の税務に精通した税理士が在籍しています。確定申告をはじめとした税務に関するお力になれるため、ぜひ一度お問い合わせください。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
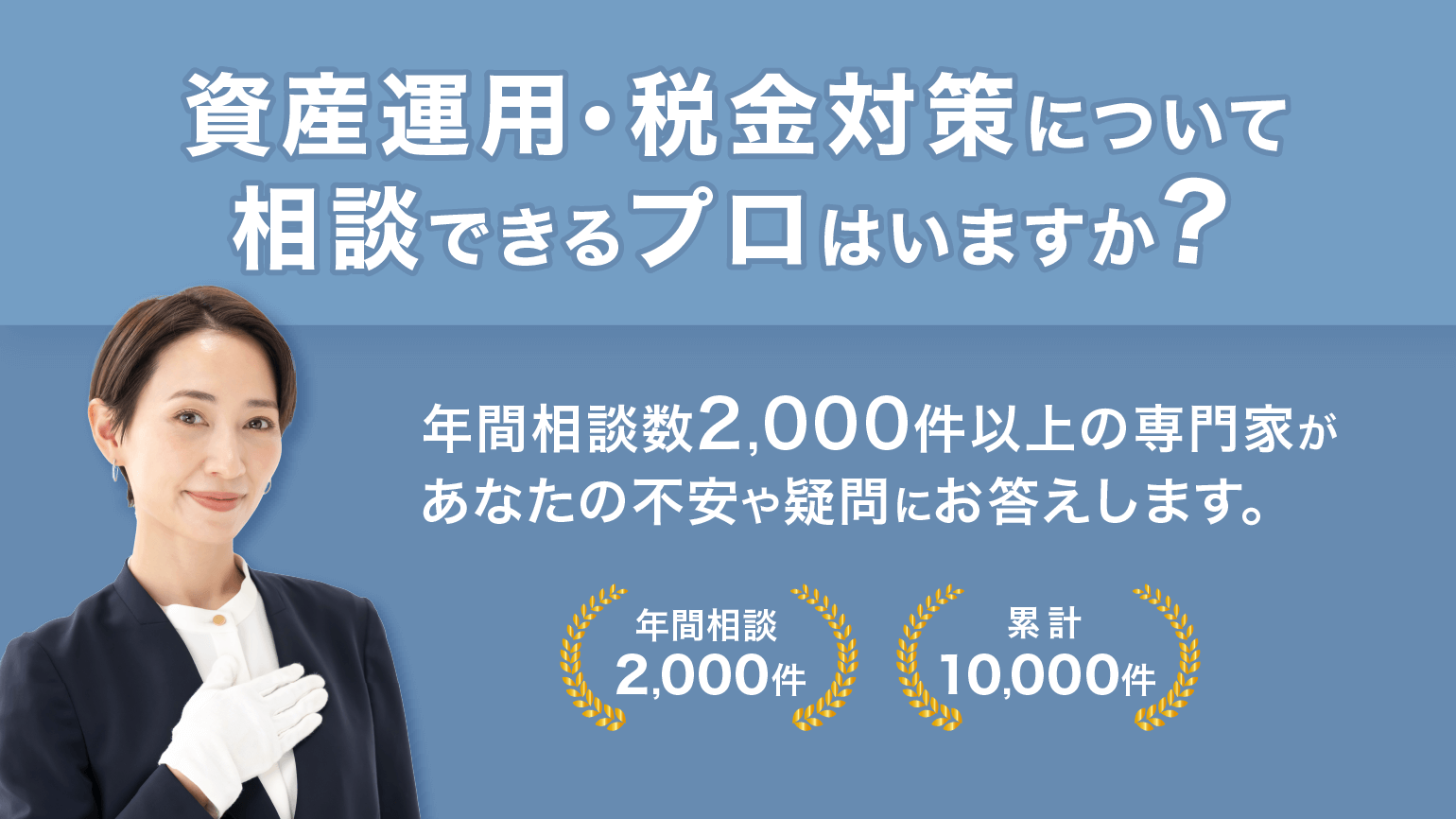
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用