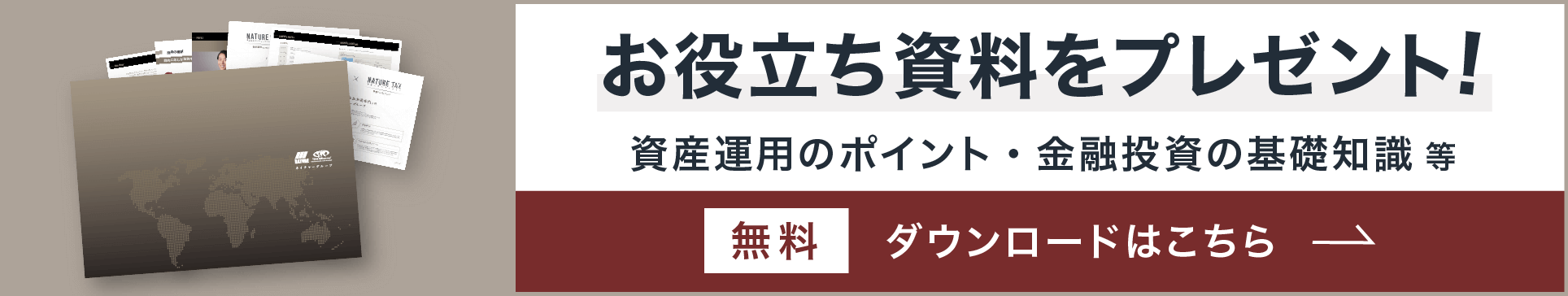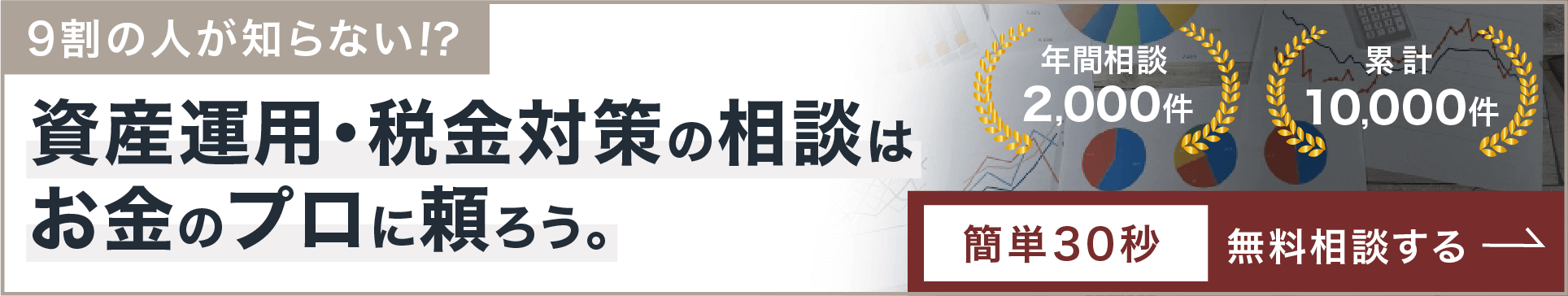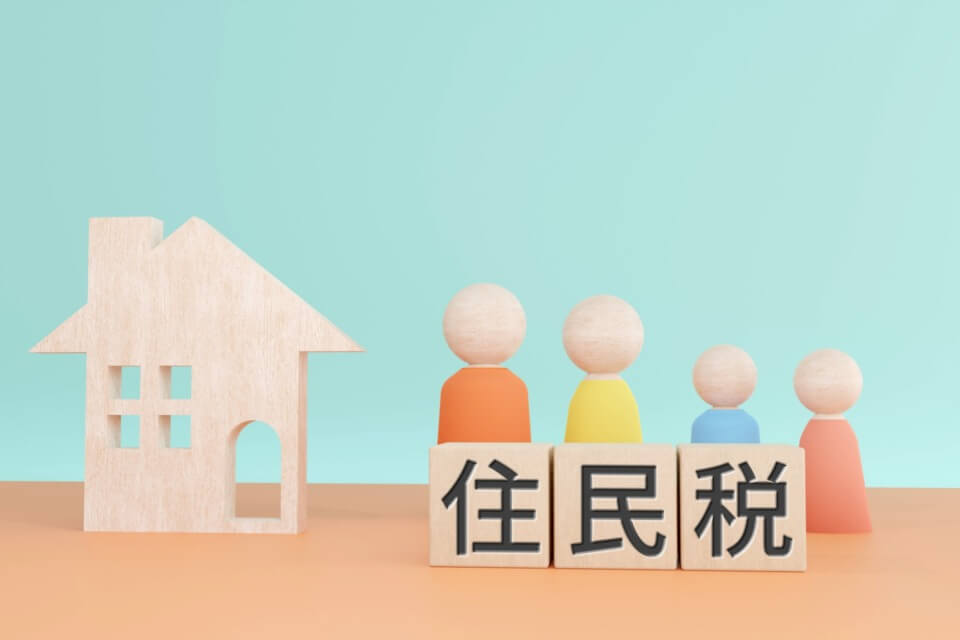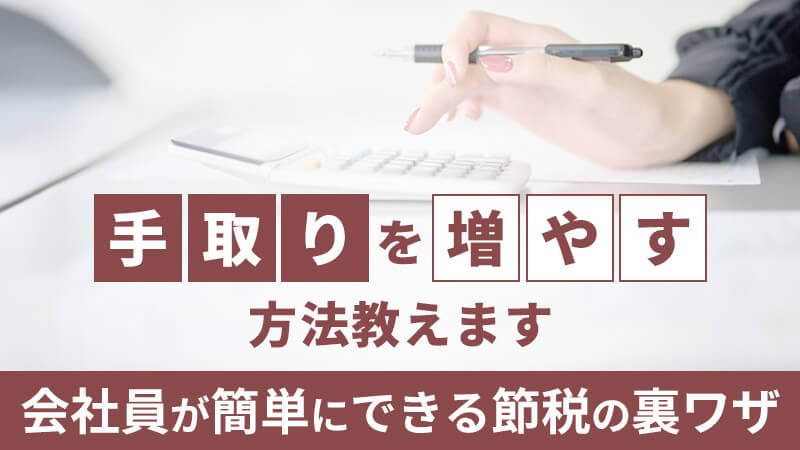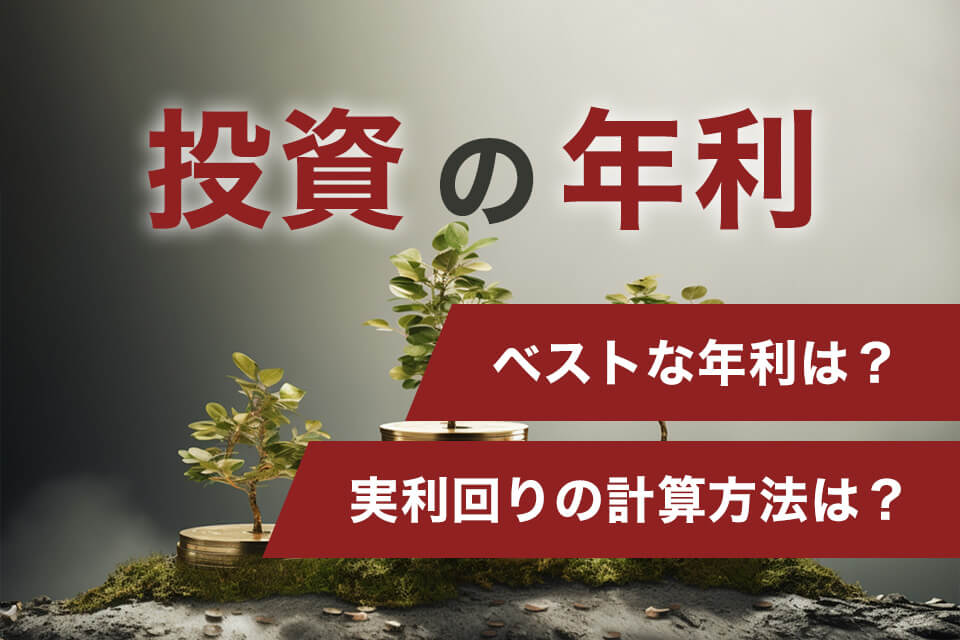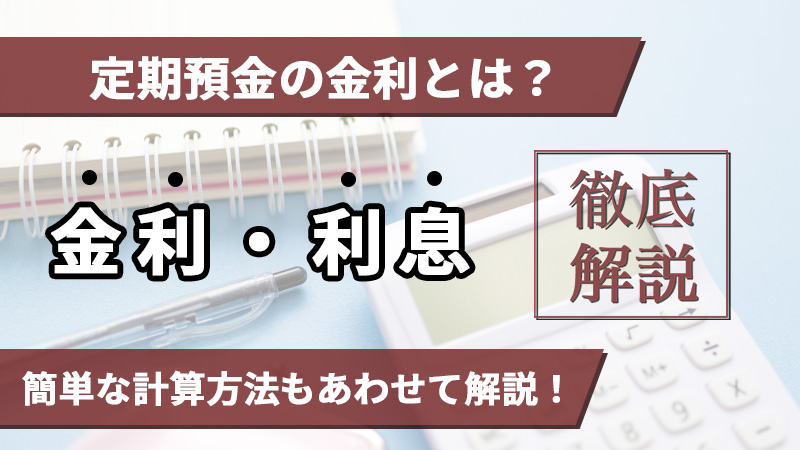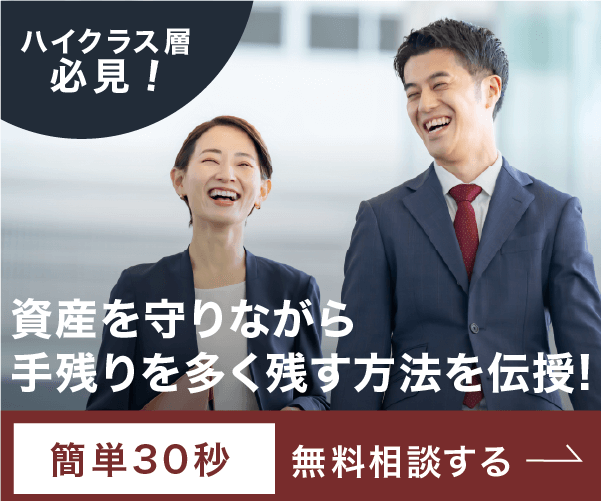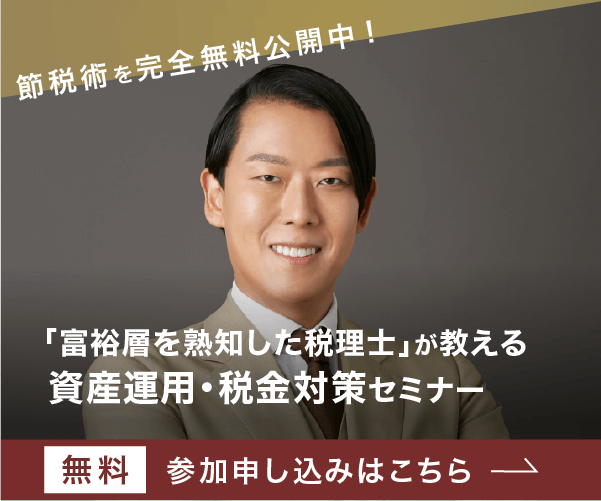![]() 2020年11月4日
2020年11月4日![]() 2023年3月15日税務
2023年3月15日税務
【詳しく分かる】贈与税の税率と計算方法 贈与税がかからない制度も徹底解説!
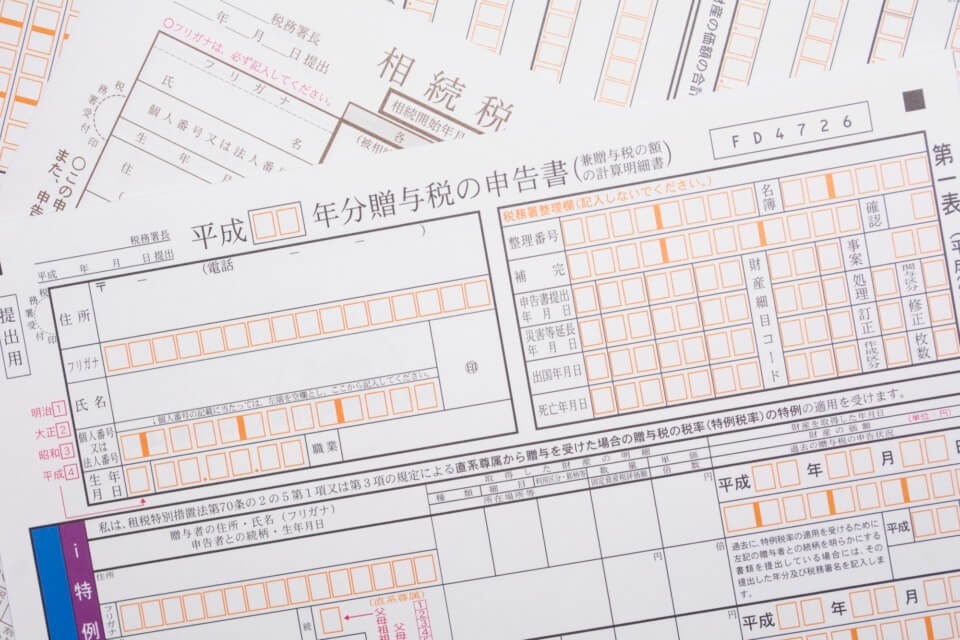
現金や不動産など、個人から財産をもらうと贈与税がかかります。「贈与税は税率が高い」と聞くものの、具体的にいくらかかるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、贈与を検討している方や贈与を受ける可能性のある方に向けて、贈与税の基礎知識や税率・計算方法を解説します。贈与税に関する特例や注意点、相続税との比較など、贈与に関わる方が知っておきたい内容も併せて確認しましょう。
目次
贈与税の課税方法と基礎控除

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方式があり、選択する方式によっては基礎控除が受けられます。また「どのように財産の受け渡しをするか」によって、贈与税を算出する際の税率が異なることがポイントです。まずは贈与税の課税方式の違いについて知識を深めましょう。
暦年課税
一般的な課税方式は、暦年課税です。受贈者(財産をもらう方)が1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に対して課税されます。暦年課税の基礎控除は一人あたり年間110万円で、110万円を超えた金額に対して課税される仕組みです。
例えば、子供が父母からそれぞれ110万円(合計220万円)を受け取った場合、1年間で受けた贈与が基礎控除を上回ります。基礎控除額を上回った分の贈与税を申告して、税金を納めなければなりません。
暦年課税では、一定の生前贈与が相続財産の対象となる点に注意が必要です。贈与者の死亡時に受贈者が財産を相続した場合、相続開始前3年以内の生前贈与は相続財産に加算されます。なお、現行では「相続開始前3年以内」が対象ですが、令和6年1月1日から「相続開始前7年以内」へ延長される見込みです。
(参考: 『国税庁 No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)
相続時精算課税
相続時精算課税とは、財産の受け渡しがあっても、累計で2,500万円を超えるまでは贈与税の対象とならない課税方式です。累計2,500万円を超えた場合、超えた金額×20%の贈与税が課されます。
贈与者が死亡して相続開始となったときは、制度を利用して贈与された財産の価額を相続財産に加えて相続税額を計算する仕組みです。相続時精算課税を選択するには、受贈者が届出書を提出する必要があります。
| 対象の受贈者 | 18歳以上の方 |
|---|---|
| 対象の贈与 | 以下いずれかの贈与 ・親から子供 ・祖父母から孫 |
| 条件 | ・贈与者が60歳以上である ・受贈者が贈与を受けた翌年2月1日から3月15日に届出書を提出する |
なお、相続時精算課税を選択する際は、以下2点にご注意ください。
・暦年贈与の基礎控除(110万円)は適用されない
・一度選択すると、暦年贈与へ変更できない
ただし、令和5年度の税制改正で、現行2,500万円の控除額とは別枠で毎年110万円の控除が認められる見込みです。
(参考: 『国税庁 No.4103相続時精算課税の選択』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm)
贈与税の税率

贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係性によって異なります。贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子供や孫が両親・祖父母から受ける「特例贈与財産」と、特例贈与財産に該当しない贈与である「一般贈与財産」の2種類です。ここでは、それぞれの税率を紹介します。
特例贈与財産の税率
特例贈与財産の税率は、以下に該当する贈与で適用されます。
受贈者:18歳以上の子または孫
贈与者:父母または祖父母
18歳以上の受贈者とは、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の方です。令和4年3月31日以前の贈与では対象年齢が20歳以上となる点にご注意ください。
「特例」という名称の通り、特例贈与財産の税率は一般贈与財産の税率よりも低く設定されています。
【特例贈与財産の税率】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
(参考: 『国税庁 No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)
一般贈与財産の税率
特例贈与財産に該当しない贈与では、一般贈与財産の税率が適用されます。夫婦間・兄弟間の贈与や、未成年の子供が両親から受けた贈与などが対象です。
【一般贈与財産の税率】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
一般贈与財産の税率は、特例贈与財産の税率よりも高く設定されています。例えば、基礎控除後の課税価格が900万円の場合、特例贈与財産の税率は30%、一般贈与財産の税率は40%です。
(参考: 『国税庁 No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)
贈与税の税率の計算方法
贈与財産が1,000万円の場合を例にして、一般贈与財産・特例贈与財産それぞれの税額の計算方法を紹介します。贈与税(暦年課税方式)の計算方法は以下3つのステップです。
STEP1:贈与財産の合計金額を確認する
STEP2:基礎控除額(110万円)を差し引いて課税価格を決定する
STEP3:課税価格を基準に税額を求める
贈与税は、課税価格に対して課される税金です。課税価格とは、贈与財産の合計金額から基礎控除額を引き算した金額を指します。
1,000万円(贈与財産)-110万円(基礎控除)=890万円(課税価格)
基礎控除後の課税価格が890万円の場合、それぞれ次の税率と控除額が適用されます。
| 税率 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般贈与財産 | 40% | 125万円 |
| 特例贈与財産 | 30% | 90万円 |
上記の税率と控除額を用いて計算すると、一般贈与財産の税額は231万円、特例贈与財産の税額は177万円です。
890万円× 40%-125万円=231万円(一般贈与財産の税額)
890万円× 30% – 90万円=177万円(特例贈与財産の税額)
贈与税の課税対象となるケース・ならないケース

贈与税は、贈与された目的や金額によって、課税対象となるケースとならないケースがあります。「知らないうちに脱税していた」ということを防ぐためにも、この機会に贈与税の課税対象についての知識を深めましょう。
贈与税の課税対象となるケース
贈与という意識がなくても、目的によっては課税対象となることがあります。以下に具体例をまとめました。
・1年間で一人が受けた贈与額が110万円を超えたとき
贈与税の基礎控除額110万円を超えた場合は課税対象です。
・親に自分の借金を返済してもらったとき
肩代わりしてもらった親に子供がお金を返済しない場合が該当します。
・妻は資金を出していないのに家の名義を夫婦共有にしたとき
夫だけが資金を出している状況で、お金の受け渡しがない妻との共有名義に変更した場合が該当します。
贈与税の課税対象とはならないケース
財産によっては、受け渡しがあっても課税対象になりません。以下に一例を挙げています。いずれも課税対象として完全に除外するわけではなく、所得税や住民税が課されるケースもあるため、留意しましょう。
・扶養義務者から渡された生活費や教育費
日常生活に必要な生活費や教育費を扶養義務者(親子、夫婦、兄弟姉妹)から渡された場合は、贈与税の対象になりません。ただし、このお金を生活費や教育費以外に使用した場合は、課税対象となります。例えば使用せずに預金したり、投資に充てたりした場合です。
・金銭や不動産などの財産を法人から受け取った場合
法人から受け取った場合は、贈与税ではなく所得税の課税対象となります。
・祝物や見舞品など、社会通念上相当と認められる金品の場合
季節ごとの贈答や花輪代、香典などは課税対象になりません。
贈与税には非課税制度がある

贈与税には非課税制度があります。制度の内容を知った上で正しく活用すれば、納める税金を賢く抑えられるでしょう。ここでは、贈与税の非課税制度や利用できる方の条件について紹介します。タイミングや利用できる状況を把握しましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与を考える方もいます。このとき「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出すれば、1,000万円まで課税対象になりません。結婚費用の場合は300万円までとなります。以下は要件の一例です。
・贈与者について:受贈者の父母や祖父母(直系尊属)であること
・受贈者について:18歳以上50歳未満であること
・期間:平成27年4月1日から令和5年3月31日までにされた贈与であること
・受贈者が金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設すること
(参考: 『国税庁 No.4511直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm)
教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与は、学校の入学金や授業料など教育資金の範囲内であれば、1,500万円まで非課税となる制度です。贈与を受けた資金の使途が学習塾や習い事などの場合(学校への支払い以外)は、500万円が限度額となります。以下は要件の一例です。
・贈与者について:受贈者の父母や祖父母(直系尊属)であること
・受贈者について:年齢が30歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・期間:平成25年4月1日から令和5年3月31日までにされた贈与であること
・受贈者が金融機関で「教育資金口座」を開設すること
ただし、30歳を過ぎて、贈与された教育費の残額がある場合、残額分は課税対象です。また、一括贈与を受けた財産を使用する場合は、領収書を作成するなど記録しておきましょう。
(参考: 『国税庁 No.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm)
住宅取得等資金の贈与
子供や孫が住宅を建てたり、改築したりするときの資金を両親や祖父母から贈与されることもあるでしょう。その場合、一定金額の贈与であれば非課税です。限度額は、住宅用の家屋の種類や新築などに関連する契約の締結日によって異なります。以下は要件の一例です。
・贈与者について:受贈者の父母や祖父母(直系尊属)であること
・受贈者について:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であり、贈与を受けた年の所得税に係る所得の合計が2,000万円以下であること
・期間:平成27年1月1日から令和5年12月31日までにされた贈与であること
(参考: 『国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm)
夫婦間で住宅や住宅用の資金を贈与したときの配偶者控除
夫婦間で「居住用不動産」や「居住用不動産を購入するための資金」をやりとりした場合、贈与税の配偶者控除が受けられます。この特例は「おしどり贈与」といわれ、基礎控除とは別に2,000万円まで非課税になります。
夫婦間での居住用不動産や住宅資金に関する贈与は、配偶者の老後に備えて行われるケースが珍しくありません。また、夫婦の財産は互いに協力して形成されると考えられるため、このような制度が設けられています。以下は制度を利用する要件の一例です。
・婚姻後20年を過ぎた後に贈与のやりとりがされている
・居住用不動産または居住用不動産を購入するために金銭を贈与されたこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者が居住用不動産やその金銭で購入した居住用不動産に実際に住んでおり、今後も住む予定であること
・贈与税の申告をすること
(参考: 『国税庁 No.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm)
贈与を受ける際の3つの注意点

贈与は、親から子、祖父母から孫など親族間で行われるケースが一般的です。「子供や孫を驚かせたい」という理由で、手続きを内密に進めようと考える方もいるのではないでしょうか。しかし、贈与の方法によっては受贈者に大きな負担がかかるかもしれません。トラブルを避けるために、3つの注意点を確認しておきましょう。
贈与から3年以内に亡くなると相続財産になる
暦年課税方式による贈与のうち、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。暦年贈与には年間110万円の基礎控除がありますが、生前贈与の年額が基礎控除額以下でも相続財産への加算対象となる点に注意が必要です。
ただし、相続税には「贈与税額控除」があり、すでに贈与税を納めている場合はその税額が控除されます。
相続財産への加算は「贈与者が亡くなった際、受贈者が財産を相続した場合の取り扱い」です。生前贈与を受けた方が相続しない場合、加算の対象となりません。
また、現行では「相続開始前3年以内」ですが、令和5年度の税制改正大綱には「7年以内への延長」が盛り込まれています。改正内容は令和6年1月1日以降の贈与から、順次適用される見込みです。相続財産に加算される生前贈与の範囲が広がるため、今後、贈与を検討している方はご注意ください。
(参考: 『国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm)
定期贈与と見なされることがある
定期贈与とは、計画的に分割して贈与することです。例えば、「2,000万円を20年に分けて贈与する(100万円×20年)」といったケースが挙げられます。結果的に2,000万円を贈与したのではなく、「あらかじめ2,000万円を贈与すると決めていた」という贈与を指します。
暦年贈与では、毎年110万円以下の贈与である上記の例では税金がかかりません。しかし、定期贈与と見なされた場合、初年度に2,000万円の贈与があったとして高い税率で課税されます。
贈与税の基礎控除を利用して少額ずつ贈与したい方は、以下のポイントを押さえておきましょう。
・贈与契約書を作成すること
・定期、定額の贈与を避けること
税務署に定期贈与と見なされないためには、贈与の事実を明確にし、「計画的な贈与ではない」という記録を残すことが大切です。
名義預金では贈与が成立しない場合も
名義預金とは、口座の名義人と事実上の管理者が異なる預貯金を指します。例えば、祖父母が孫名義の口座を開設し、入金やキャッシュカードを祖父母が管理するケースです。「口座が孫名義であれば、孫に贈与したことになる」と考える方は多いでしょう。
しかし、名義人が口座の存在を知らない場合や名義人以外が口座を管理している場合、贈与と認められない恐れがあります。
民法上の贈与は「当事者の一方が財産を与える意思表示をし、その相手方が受諾することで成立するもの」と定められています。したがって、贈与には当事者による「あげます」「もらいます」という意思表示が必要です。
贈与と見なされない場合は贈与者の相続財産となり、贈与者の死亡時に相続税の対象となる可能性があります。トラブルを防ぐために、入金や口座の管理を名義人が行うといった対策を取りましょう。
(参考:『e-GOV法令検索 民法』/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
贈与税と相続税ではどちらのほうが得なのか

贈与税と相続税のどちらのほうが得なのかは、贈与の方法や非課税制度の利用などによっても変わります。どちらも超過累進税の方式であるため、課税される額が少なくなるよう相続税・贈与税対策をすることが重要です。ここでは、贈与税と相続税の比較や最新の税制改正を踏まえた課税の動向について解説します。
贈与税と相続税の税率の違い
税率だけを考えれば、贈与税の税率は相続税よりも高いため、相続税のほうが得ということになります。
【相続税の税率】
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
また、相続税は相続した財産の合計金額が基礎控除額を超える場合に課される税金です。相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で、贈与税の基礎控除額110万円と比較して負担が軽いといえるでしょう。
ただし、実際にどちらが有利になるかは対象となる財産や相続人の数、利用できる特例などによって異なります。早めに状況を確認し、時間をかけて検討することが大切です。
(参考:『国税庁 No.4155 相続税の税率』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)
暦年贈与や非課税制度を活用すれば贈与税のほうが得なことも
税率だけを見れば相続税が有利なものの、一概に判断はできません。暦年贈与を選択し、一定条件のもと贈与税の基礎控除額を上回らない範囲で贈与を続けたり、贈与税が非課税となる制度を活用したりすれば、相続財産を減らすことにつながります。
また、資産価値の上昇が見込まれる不動産を所有している場合、生前贈与したほうが結果的に賢い選択となることも考えられるでしょう。このように状況によって最適な選択は異なるため、不安がある方やより効果的に税金対策をしたい方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
税制改正により富裕層は慎重な判断が必要
少子高齢化の影響で国の財政が悪化する中、富裕層への課税が強化の一途をたどっています。令和5年度の税制改正大綱には、相続財産に加算する贈与の対象期間の延長の他、「1億円の壁問題」対策として超富裕層への課税を強化する内容が盛り込まれました。
「1億円の壁問題」とは、所得税率の違いによって高所得者ほど税金の負担割合が低くなる問題です。所得税は累進課税(最高45%)である一方、株式の売買などで生じた譲渡所得税は一律15%です。
富裕層であるほど譲渡所得を含む金融所得の比率が高く、所得が1億円を超えると課税負担の割合が低くなる現象が起こります。税負担の公平性を適正化するため、一定所得を超える方の所得税の負担が増えることになりました。
富裕層の税負担は今後さらに厳しくなると考えられます。適切な税金対策をするには、最新の改正内容を踏まえて検討することが大切です。
贈与時の税金対策のご相談はネイチャーグループへ
贈与・相続のどちらが有利であるかの判断には専門知識が必要です。対象となる財産の種類や金額、親族の状況によって取るべき対策が異なります。最終的には贈与を受ける方や相続する方に影響するため、慎重に判断する必要があるでしょう。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、専門知識と豊富な実績を有するプロ集団です。贈与税対策のようにケースバイケースの判断を要する際は、税理士の経験が要となります。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では年間で約2,000件のご相談を承っており、特に贈与・相続対策の実績が豊富です。贈与・相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
まとめ

多くの資産を贈与するほど高額な贈与税がかかります。忘れてならないのは、税金を納めるのは財産をもらう受贈者であることです。贈与を受ける方の負担が重くならないためにも、制度を上手に活用して税金対策をしましょう。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、相続対策の実績が豊富な税理士がお話を伺います。個人での判断が難しい贈与・相続についてプロの目線でご提案しますので、ぜひお問い合わせください。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
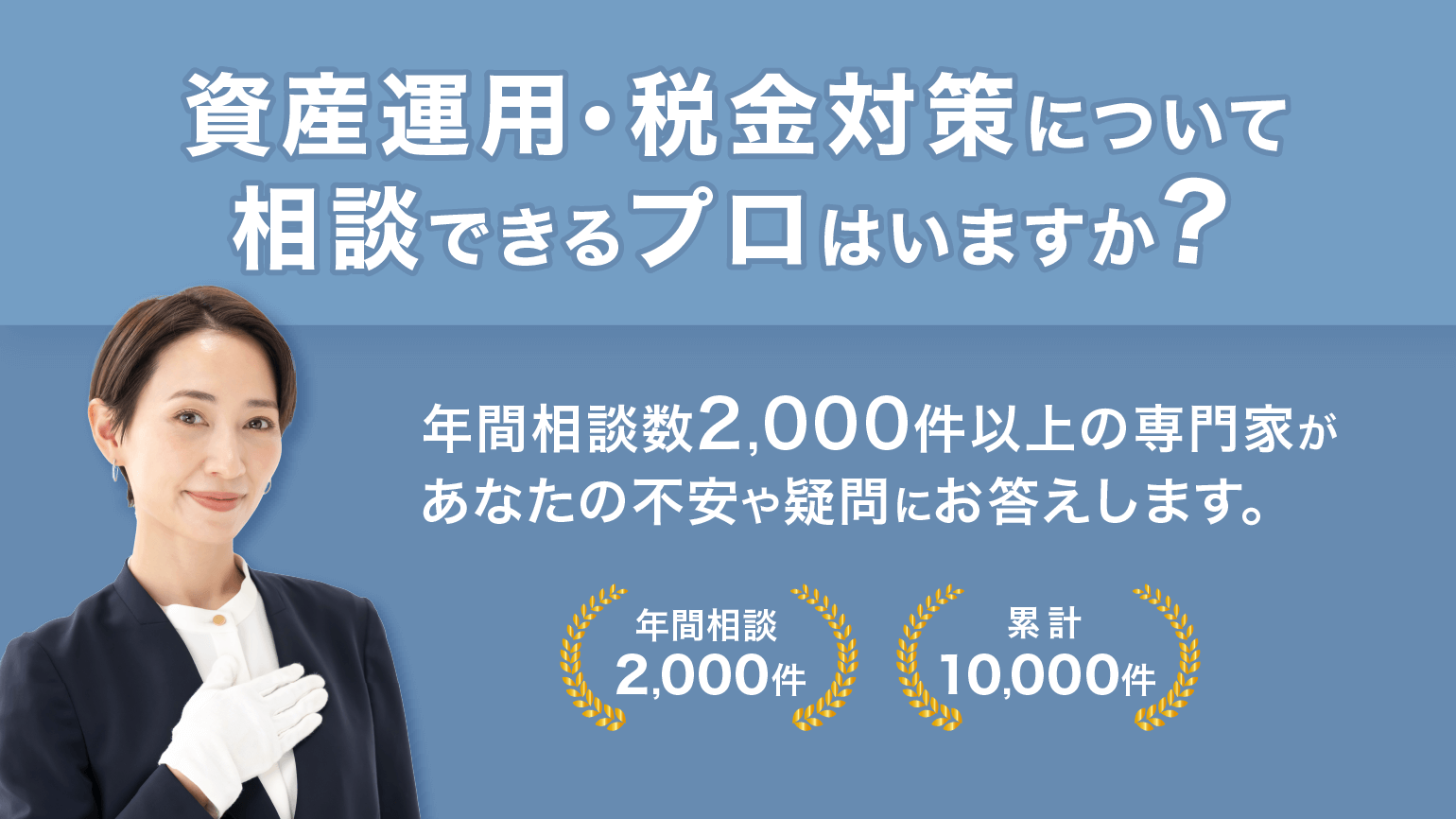
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用