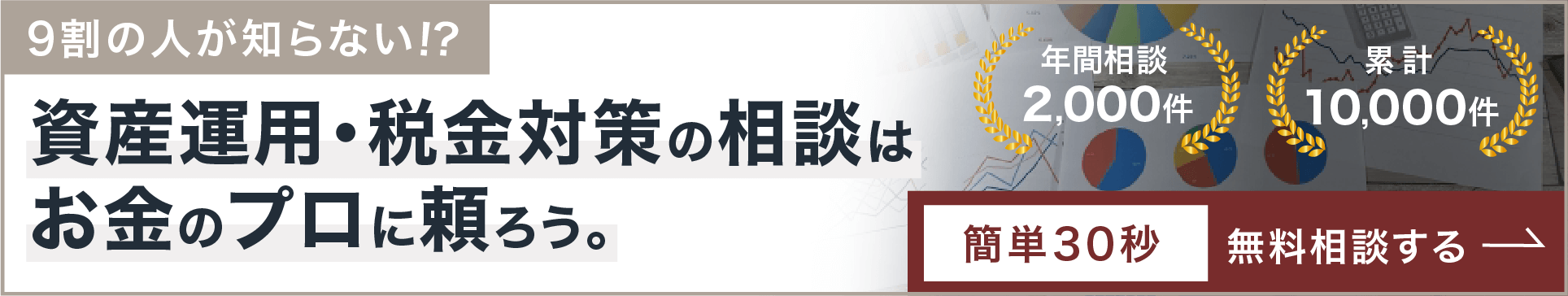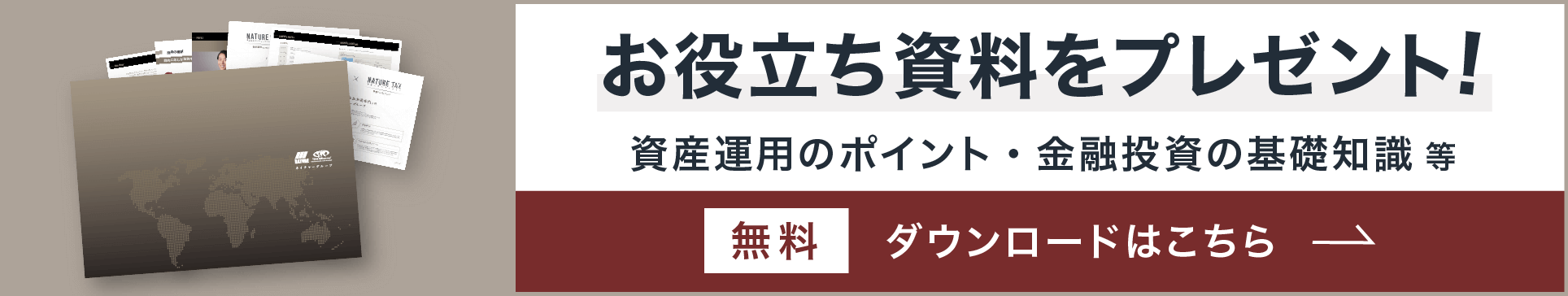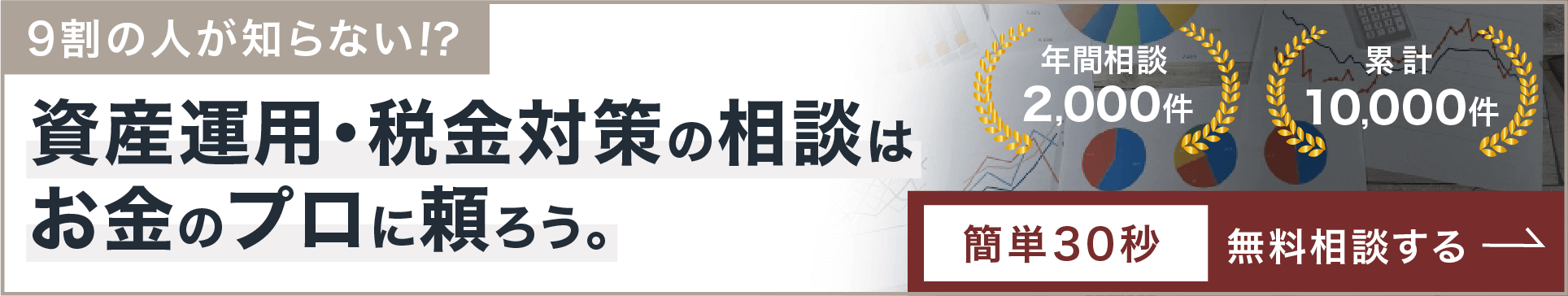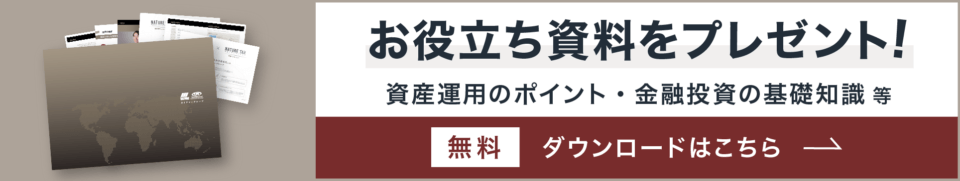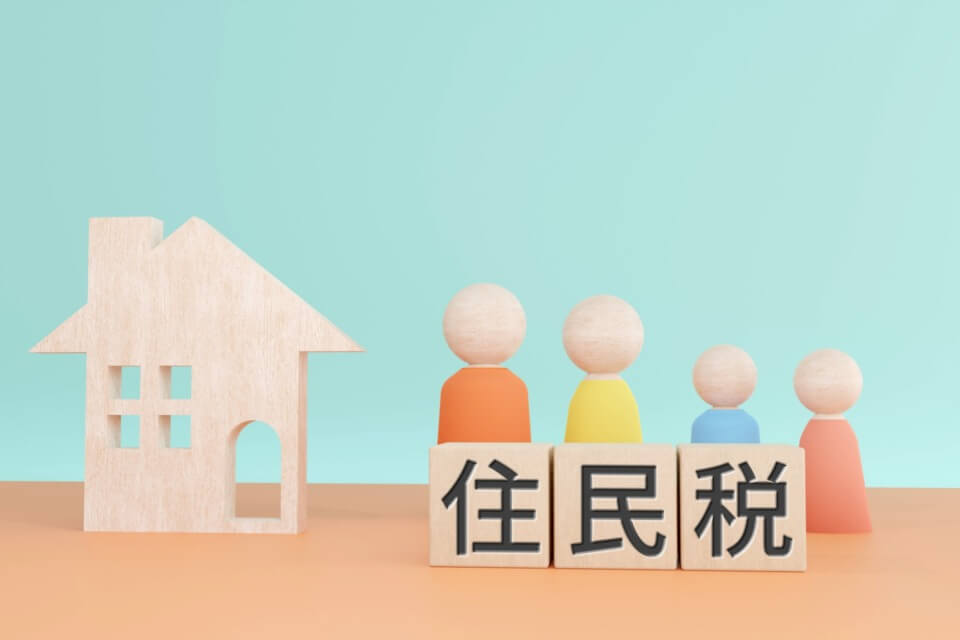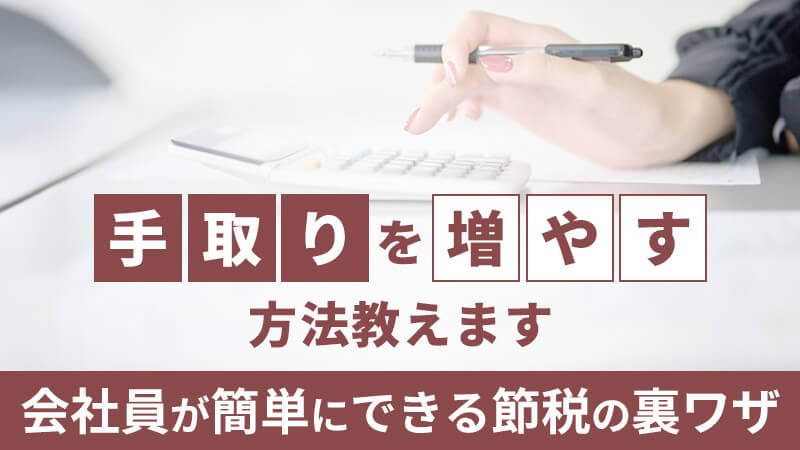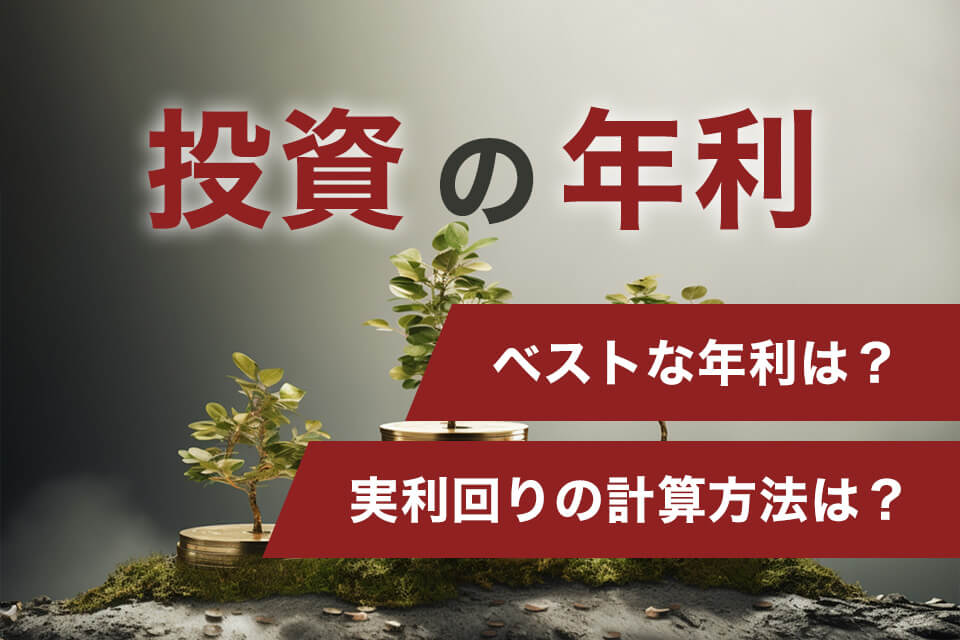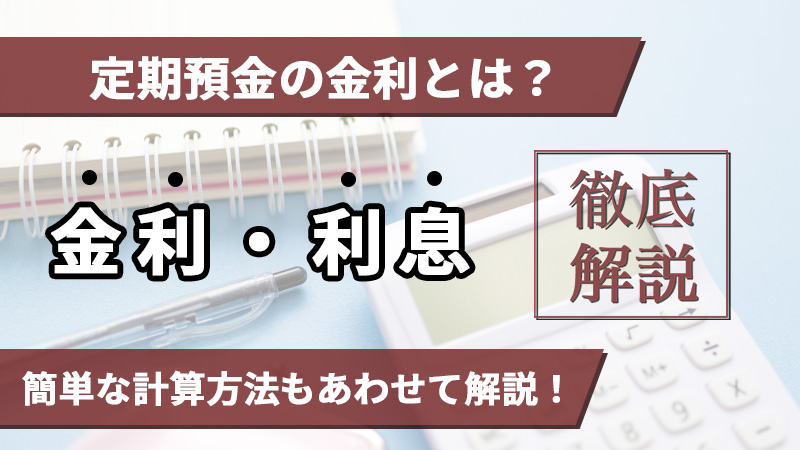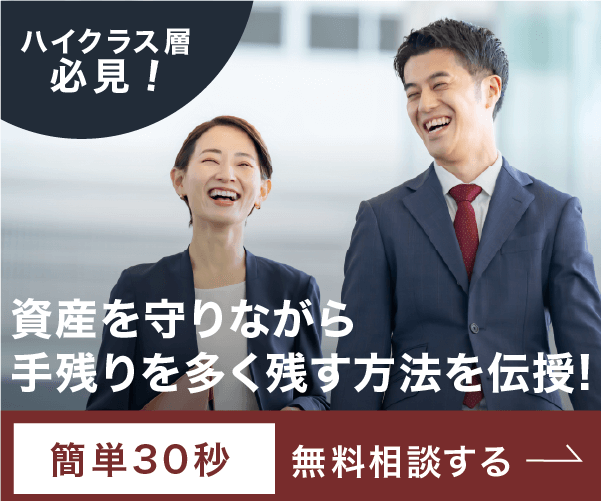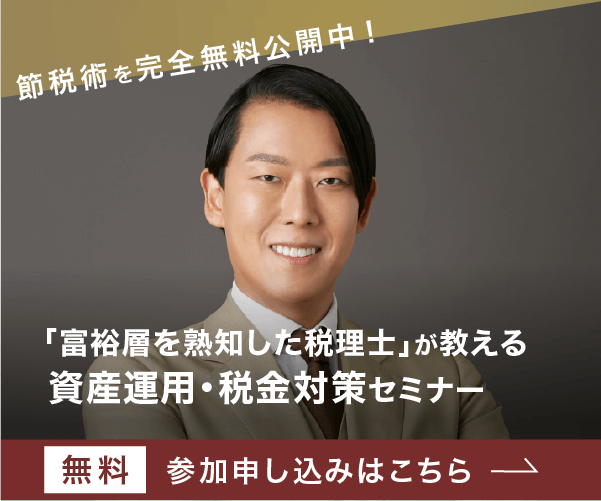![]() 2022年2月25日
2022年2月25日![]() 2023年4月10日税務
2023年4月10日税務
法人税率は何%?対象の所得金額や申告方法を解説

法人税は企業が得た所得に対して課される税金です。法人税率は会社の資本金の規模や所得金額によって定められていますが、「詳細まではきちんと把握していない」という方もいるのではないでしょうか。
法人税率は複数の税法が絡んでいるため難しさを感じる分野でもあります。基本情報をしっかりと確認し、理解を深めることが大切です。
そこでこの記事では、法人の種類ごとに法人税率を解説します。法人税の概要の他、法人税率と所得税率との違いや節税方法についても分かるような内容にまとめました。自身の納める税額が知りたいときや税負担の軽減を目指す方はぜひ参考にしてみてください。
目次
法人税率とは?

法人税率は、法人税額の計算に用いる数値です。法人税額がいくらになるのか気になる方は、基本を確認しておきましょう。また、法人税と所得税では税率の仕組みが異なります。ここでは、法人税率の特徴について、所得税率との違いに触れながら解説します。
法人税の概要
法人税とは、法人が事業経営により得た利益に対して課される税金です。以下のように大きく分けて3つの税金が課されます。
・法人税
・法人住民税
・法人事業税
「法人税」と広く呼ばれているのは、法人の所得に対して発生する税金です。利益から経費を差し引いた所得が黒字になる際は、納税の義務が発生します。
また、法人税は直接税です。税金を納める人と負担する人が同一であるときは、直接税に分類されます。直接税は、個々の経済状況や利益の額に応じた税率が課されるのが特徴です。法人税においても、法人の規模や種類によって異なる税率が採用されています。
法人税率は何%か
法人税率は、法人税額の計算に用いる数値です。適用される税率は、法人の規模や開始事業年度などによって異なります。
【中小企業の法人税率(令和4年4月以後開始事業年度)】
| 課税所得金額 | 税率 | |
|---|---|---|
| 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
| 適用除外事業者※ | 19% | |
| 年800万円超の部分 | 23.2% | |
※資本金1億円以下の場合
※適用除外事業者:対象の事業年度開始日より、3年以内に終了した事業年度の所得金額が、平均15億円を超える法人など
一般的な企業の法人税率は原則23.2%です。ただし、中小企業には軽減税率が適用され、年800万円以下の所得までは15%(または19%)となります。15%の特例は令和5年3月31日まででしたが、令和5年度税制改正大綱に2年延長されることが盛り込まれました。
(参考: 『国税庁No.5759 法人税の税率』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm)
(参考: 『経済産業省 令和5年度税制改正のポイント』/https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/index.html)
法人税と所得税は税率が異なる
法人税と所得税は、税率の決まり方が異なります。法人税では「比例税率」が採用されており、法人の区分や資本金額に応じて定められた一律の税率が適用される仕組みです。一方、所得税は5%から45%の「超過累進税率」が採用されており、所得金額が増えるほど税率が高くなります。
個人事業主としてある程度の利益が出ているようなら、法人化して法人税を納めたほうが節税できるケースがあります。例えば年間所得金額が800万円の場合は、所得税が「800万円×23%-63万6,000円=120万4,000円」であるのに対し、法人税は「800万円×15%=120万円」です。
ただ、法人税の計算は個人の所得税の計算と比較し複雑なので、法人税申告に不安のある方は税理士に相談することをおすすめします。
(参考: 『国税庁 No.2260所得税の税率』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)
【法人税率の推移】日本の税率は引き下げられている
日本の法人税率は原則23.2%です。平成21年から「中小法人の軽減税率の特例」が設けられており、資本金1億円以下の中小企業において、年800万円以下の所得は法人税率が15%に軽減されます。
ただし、税制度は社会情勢や経済状況といった時代の変化に合わせて、随時見直されるものです。法人税においても、今後も同じ税率が続くとは限らず、上下する可能性があります。
【日本の法人税率の推移】
| 基本税率 | 中小企業の軽減税率(年800万円以下) | 中小企業の軽減税率の特例(年800万円以下) | |
|---|---|---|---|
| 昭和56年 | 42 | 30 | |
| 昭和59年 | 43.3 | 31 | |
| 昭和62年 | 42 | 30 | |
| 平成元年 | 40 | 29 | |
| 平成2年 | 37.5 | 28 | |
| 平成10年 | 34.5 | 25 | |
| 平成11年 | 30 | 22 | |
| 平成21年 | – | – | 18 |
| 平成24年 | 25.5 | 19 | 15 |
| 平成27年 | 23.9 | – | – |
| 平成28年 | 23.4 | – | – |
| 平成30年 | 23.2 | – | – |
法人税が減税されているのはなぜ?
法人税が減税されている背景には、国内から海外への企業流出を防ぐ、企業における経営状況の改善を促すといった政府の狙いがあります。
国際競争力が激しさを増す中、日本が成長し続けるには優良企業の存在が欠かせません。しかし、グローバル化が進み、誰もが国同士を行き来できる現代では「企業が国を選ぶ時代」です。日本の税率が他国よりも高いと、拠点を海外へ移す企業が増えてしまいます。企業の海外流出を防ぐには、税率を国際基準に設定する必要があるという理屈です。
また、法人税の負担を軽減させて投資に回すお金が増えれば、既存事業の拡大や新規事業への参入の促進を期待できるでしょう。
将来性のある多くの企業が日本国内に残れば、海外の企業や投資家による日本企業への注目度が増し、投資マネーが集まりやすくなります。
法人税の減税は、国や企業の成長促進や国内に良質な雇用を生み出すために重要な政策です。
法人税の種類と計算方法

法人税と呼ばれる税金は大きく分けて3種類です。ここでは、法人税の種類ごとに制度内容と計算方法を紹介します。自社に課される税額が気になる際は、以下の計算方法を参考にシミュレーションしてみましょう。計算方法や税制度の概要に関する理解を深めることで、自身のケースに合った節税方法も分かるようになります。
法人税
法人税は、国に納める税金です。確定申告にて、企業が1年の間に得た所得金額を計算し、国に申告・納税します。利益よりも損失のほうが大きくなるケースでは、法人税は発生しません。
法人の得た所得が黒字であるときは、各事業年度の所得金額に規定の税率を乗じて計算します。所得金額の計算式は、「益金-損金」です。益金・損金とは課税を公平に決めるための法人税法上の概念であり、帳簿上の収益・費用とは区別して考えなければなりません。
例えば、受取配当金や税金の還付金などは帳簿では収益に含まれますが、益金には含まれません。また、減価償却費や交際費など、一定の限度額を超えた金額は損金に含まないというルールもあります。以上から、益金・損金と収益・費用が不一致になるケースは珍しくありません。
法人事業税
法人事業税率は地方税の一種です。企業の所在地である自治体(都道府県)で事業を営む際は自治体の行政サービスを受けることになるため、その費用を負担することを目的として課税されます。
法人事業税の計算式は、「所得×法人事業税率」です。税率は事業所得の金額や自治体により異なります。法人事業税も所得が赤字のときは、原則課税されません。ただし、付加価値割や資本割があるケースでは課税されることもあります。
法人事業税の申告期限は会計期末から2か月以内です。法人税と一緒に確定申告にて計算し申告・納税します。
法人住民税
法人住民税は、事業所のある自治体に納める地方税の一種です。法人であっても、地方公共団体の公共サービスを受ける「住民」として、都道府県に対し住民税を納めなければなりません。
地方税は、法人税申告によって計算された法人税額に基づき算出されます。法人住民税の計算式は、「(法人税額×税率)+均等割」です。税率は自治体や資本金額といった条件によって異なります。
法人税や法人事業税は企業の利益がゼロの場合は課税されませんが、法人住民税においては「均等割」と呼ばれる定額の税金がかかる点に注意が必要です。事業を営んでいる限りは課税の対象となります。地方自治体への申告・納税を忘れないようにしましょう。
会社が負担する法人税の実効税率
「実効税率」は、所得に対して実質的に負担する法人税の割合です。法律に従って計算した税額と実質的に納める税額が異なるため、このような考え方があります。
法人税のうち「法人事業税」は、損金算入が認められています。税金を納めるものの、翌年度の所得から控除されるため実質的な負担が軽減されている仕組みです。法人事業税の損金算入を考慮した税率が「実効税率」です。また、損金算入を考慮せず単純に税率を合計したものを「表面税率」と呼びます。
実効税率=(A+B+C)÷(1+C)
表面税率=A+B+C
A法人税率など:法人税率+(法人税率×地方法人税率)
B法人住民税率:法人税率×法人住民税率
C法人事業税率など:法人事業税率+(法人事業税率×特別法人事業税率)
【具体例】
実効税率33.58%=(25.59%+1.62%+9.59%)÷(1+9.59%)
【条件】
| 税金の種類 | 税率 | |
|---|---|---|
| A | 法人税 | 23.2% |
| 地方法人税 | 10.3% | |
| B | 法人住民税(法人税割) | 7% |
| C | 法人事業税(所得割) | 7% |
| 特別法人事業税 | 37% |
※普通法人(資本金1億円以下)を想定(簡略化のため法人税の軽減税率は考慮していません)
※小数点第3位を四捨五入しています
※税率は令和5年3月に開始する事業年度を参考にしており、Bは標準税率です
形態によって異なる?ケース別で見る法人税率

法人税率は、法人の種類や資本金、所得金額により区分されます。所得金額に税率を乗じて計算するため、赤字の場合に法人税は発生しません。なお法人税が課されない法人として、地方公共団体や日本政策金融公庫などの公共法人が挙げられます。これは、公共性のある目的を持って運営される法人であるためです。
普通法人の場合
普通法人とは、協同組合等、人格のない社団等、公益法人等、公共法人以外の法人であり、通常の営利目的で運営される法人です。株式会社や合名会社、合資会社、医療法人などが該当します。普通法人の税率は、次の通りです。
| 資本金の金額 | 所得金額 | 開始事業年度ごとの法人税率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年4月以後 | 平成30年4月以後 | 平成31年4月以後 | 令和4年4月以後 | ||
| 1億円以下 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15%※ | 15%※ |
| 年800万円超の部分 | 23.4% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | |
| 1億円超 | – | 23.4% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
※3年以内に所得金額の年平均額が15億円を超える法人等は、年800万円以下の部分に19%の税率が適用
協同組合等の場合
協同組合等とは、共通の目的のために集まった個人や中小企業がその目的を達成するための組織です。農業協同組合や漁業協同組合などの協同組合をはじめ、商店街振興組合や信用金庫も該当します。協同組合等の税率は、次の通りです。
| 所得金額 | 開始事業年度ごとの法人税率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成28年4月以後 | 平成30年4月以後 | 平成31年4月以後 | 令和4年4月以後 | |
| 年800万円以下の部分 | 15%※ | 15%※ | 15%※ | 15% |
| 年800万円超の部分 | 19%※ | 19%※ | 19%※ | 19% |
※協同組合等が連結親法人に該当するときは、年800万円以下の部分は16%、年800万円超の部分は20%の税率がそれぞれ適用
公益法人等の場合
公益法人等とは、営利目的ではなく公益の向上を目的として運営される法人です。公益法人等は、一定の目的のもとに集まって人によって成り立つ公益社団法人や、一定の目的のもとに拠出された財産の集まりである公益財団法人の他、宗教法人や学校法人、社会福祉法人が該当します。
法人の性格上、公益目的事業から生じた所得は課税対象となりません。あくまで収益事業から生じた所得にのみ法人税がかかります。公益法人等の税率は、次の通りです。
| 区分 | 所得金額 | 開始事業年度ごとの法人税率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年4月以後 | 平成30年4月以後 | 平成31年4月以後 | 令和4年4月以後 | ||
| 公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人、公益法人等とみなされるもの | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 年800万円超の部分 | 23.4% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | |
| 上記以外の公益法人等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% | |
人格のない社団等の場合
人格のない社団等とは、人や財産が同じ目的のもとに集まってできた団体であるもののうち、法人格がなく代表者や管理人の定めがある団体をいいます。人格のない社団等に該当する団体は、PTAや同窓会、同業者団体などです。
収益事業があるときは、その所得に対し法人税が課税されます。人格のない社団等の税率は、次の通りです。
| 所得金額 | 開始事業年度ごとの法人税率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成28年4月以後 | 平成30年4月以後 | 平成31年4月以後 | 令和4年4月以後 | |
| 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 年800万円超の部分 | 23.4% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
特定の医療法人の場合
特定の医療法人とは、医療の普及向上や社会福祉に大きく貢献しており、公的に運営されていることを国税庁長官に承認された医療法人です。特定医療法人として承認された場合は、通常23.2%の法人税率が19%に軽減されます。
| 所得金額 | 開始事業年度ごとの法人税率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成28年4月以後 | 平成30年4月以後 | 平成31年4月以後 | 令和4年4月以後 | |
| 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15%※ | 15%※ |
| 年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% |
※適用除外事業者に該当する法人の税率は、年800万円以下の部分については19%(特定の医療法人が連結親法人は20%)
なお、特定の医療法人が連結親法人に該当するケースでは、年800万円以下の部分は16%、年800万円超の部分は20%の税率がそれぞれ適用されます。
法人税に関わる税額控除や租税特別措置

「税額控除」や「租税特別措置」は、法人税の負担軽減のための制度です。これらの多くは自動的に適用されるものではなく、申告によって利用できるものです。つまり、制度を知っているかどうかで税金の負担が変わります。
制度を上手に活用すると大きな節税効果を期待できるため、各種制度について知っておくとよいでしょう。
法人税における税額控除
税額控除とは、所得金額を基に計算した税額から一定金額を控除できる制度です。法人税における税額控除には、二重課税の防止を目的とした控除と政策に関する控除があります。
例えば「所得税額控除」は、預金や一定の要件を満たした債権の利子などを受け取った場合に、所得税の全額または一定金額を控除できる制度です。
個人が受け取った利子(利子所得)には、源泉分離課税が採用されています。源泉分離課税とは、お金を受け取る前に所得税が源泉徴収される課税方式です。法人が受け取った利子も、個人と同様にあらかじめ所得税が源泉徴収されます。
しかし、法人には所得税が課税されないため、源泉徴収分を調整するために税額控除が認められています。
(参考:『国税庁 所得の種類と課税方法』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/01/1_03.htm)
法人税における租税特別措置
租税特別措置とは、事業の効率やサービスの質を上げるための投資、賃上げなど一定の要件を満たした企業が利用できる制度です。中小企業向け租税特別措置の対象は、過去3年間における課税所得の平均が15億円以下の企業となります。
さまざまな観点から政策が打ち出されているため、利用できる制度があるかどうか確認しておくとよいでしょう。以下は中小企業における租税特別措置の具体例です。
※下記はあくまでも制度の一例であり、各制度の適用には多数の条件があります
【中小企業経営強化税制】経営力向上のための設備投資を後押しする制度
例:一定の設備を取得した場合、取得価額×10%の税額控除
【中小企業投資促進税制】生産性を高めるための設備投資を支援する制度
例:一定の機械装置などを取得した場合、取得価額×7%の税額控除
【中小企業における賃上げ促進税制】賃上げに積極的な企業の税額を軽減する制度
例:従業員の給与を前事業年度よりも1.5%以上増加させた場合、一定金額を税額控除
法人税を節税するには

法人税額が多く、負担を感じている方もいるかもしれません。納める税金が減れば、その分事業のためにお金を使用できます。
法人税額を減らすには、損金として扱われる費用を活用することが有効です。ここでは一般的な節税方法を紹介します。自社の経営状態や資産状況に合う節税方法を検討しましょう。
赤字を繰り越す
所得金額が赤字だった場合は、その赤字を次年度以降に繰り越すことが認められています。繰越期間は原則10年です。次年度が黒字となれば、繰り越した赤字分を控除できます。
例えば、2021年度に発生した300万円繰越欠損金(赤字所得)があるとしましょう。2022年度の所得として200万円の黒字が発生すると、「200万円-300万円=-100万円」となり、課税所得は0円です。この事例では、繰越控除を利用しなければ200万円の黒字所得に対して税金が課されていたため、大きな節税メリットを享受できたといえます。
貸倒引当金を計上する
貸倒引当金とは、回収する見込みのない売掛金などに対し、損失が発生するかもしれない金額を予想し事前に計上するものです。税務上の要件を満たすことで、回収困難な売掛金に対し貸倒引当金を計上できます。利益から差し引きできる損金が増えるため、課税所得や法人税の減額につながるという仕組みです。
ただし、金銭債権として認められないものは貸倒引当金の対象にならないので注意しましょう。貸倒引当金に含まれる費用と含まれない費用の一例として、以下が挙げられます。
| 含まれる費用 | 売掛金、貸付金、未収入金など |
|---|---|
| 含まれない費用 | 未収配当金、未収の預貯金利子、手付金、保証金など |
中小企業倒産防止共済を利用する
中小企業倒産防止共済とは、取引先が倒産したときに積み立てた掛金総額の10倍(最高8,000万円)を上限に、回収困難な売掛金などの額まで貸付けが受けられる制度です。中小企業倒産防止共済の掛金は、全額が損金として扱われます。
掛金は5,000円~20万円の間で自由に設定可能です。また、「40か月以上掛金を払い込めば積立額が全額戻ってくる」「取引先が倒産していなくても借り入れができる」といったメリットもあります。中小企業倒産防止共済に加入するための条件は以下の通りです。
・1年以上事業を継続していること
・資本金や従業員数の規定をクリアしていること
| 業種 | 資本金の額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業 ※一部を除く | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
社員旅行の費用を計上する
旅行期間や参加人数といった所定の要件を満たせれば、旅行費用を福利厚生費として計上できます。福利厚生と認められるための条件は以下の通りです。
・旅行期間(海外旅行では現地の滞在期間)が4泊5日以内であること
・社員全体の50%以上が参加していること
福利厚生費と認められれば、宿泊費用や移動費用、食事代のような旅行にかかる費用の全額を損金算入できます。また、旅行が年度末に実行され支払いが翌月になるようなケースでも、当期の経費として計上可能です。
不要な商品の在庫を処分する
不要な商品を処分したときは、廃棄損として損金に算入できます。また、「在庫管理にかかる維持費や人件費も削減できる」「帳簿記入の手間が省ける」といった点もメリットです。在庫として余っている商品を安易に値下げすると、ブランド力の低下を招く恐れもあります。不用品があれば、思い切って処分することも検討しましょう。
ただし、在庫処分した費用を経費計上するためには、確定申告時に廃棄処分をした証明書や請求書の提出が必要です。処分時は、産業廃棄物業者が発行する廃棄証明書を受領し、きちんと保管しましょう。
30万円未満の減価償却資産の購入費用を一括で計上する
減価償却とは、固定資産を耐用年数で割り、数年~数十年かけて経費計上する会計方法です。通常、10万円を超える固定資産は減価償却の対象となります。
しかし、青色申告している中小企業の場合、30万円未満の減価償却資産を購入時に一括で損金として計上可能です。1回で経費に参入できる金額が増えれば課税所得が減るため、節税効果を期待できます。少額減価償却資産の特例を受ける際の要件は以下の通りです。
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の青色申告法人であること
・常時使用する従業員の数が500人以下であること
・連結法人に該当しないこと
詳しい条件は、国税庁のホームページにて確認できます。少額減価償却資産の特例を利用する際は参考にしてみてください。
(参考: 『国税庁 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm)
法人税の申告・納税

法人として経営をしている企業には法人税申告の義務があります。法人税申告とは、申告書に所得の金額を明記して、納める税金の金額を国に申告するための手続きです。法人税における2種類の申告方法「確定申告」と「中間申告」について、概要や申告期限、注意点を紹介します。
確定申告
法人税の確定申告は、確定した決算に基づいて行われます。法人税確定申告の申告期限は、決算日の翌日から2か月以内です。個人事業主の所得税のように「2月16日から3月15日まで」と一律ではないため混同しないようにしましょう。
申告期限を守らないと、延滞税や加算税といったペナルティが課されます。ただし、災害や会計監査のために2か月以内に決算が確定しない場合は、届出によって申告期限の延長が可能です。
ちなみに、災害の影響で決算が確定しない際は申告と同様に納税期限も延長されますが、会計監査による場合は納税期限の延長はありません。
中間申告
中間申告とは、事業年度の中間でその年度の税金を前払い(予定納税)するための申告です。申告は、その事業年度開始後6か月を経過した日より2か月以内に行わなければなりません。
申告方法は、前期の実績額を基礎とする予定申告と、半期を1事業年とみなして計算する仮決算の2種類があります。
なお、法人税の中間申告が対象にならないケースもあります。前事業年度の確定法人税額が赤字または20万円を超えない場合です。また前事業年度を基準とするため、合併の場合を除き、設立1年目の新しい会社も中間申告(予定申告)は不要です。
申告・納付方法と申告先
法人税申告では、事業所の所在地が管轄する税務署に必要書類を提出します。法人税申告で提出が義務付けられている書類は以下の通りです。
・法人税申告書(申告書、別表)
・決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
・勘定科目明細書
・法人事業税等の申告書
・法人事業概況説明書
申告書に必要事項を記入し、添付書類をそろえて提出しましょう。なお、法人税申告の申告方法や納税方法は複数あります。自身の申告・納税しやすい方法を選び、期限に遅れないよう、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
| 申告方法 | ・税務署の窓口で申告する ・インターネットからe-Taxで申告する ・書類を税務署に郵送する |
|---|---|
| 納税方法 | ・税務署や金融機関の窓口で納付する ・インターネット上で電子納付する ・クレジットカードで納付する |
法人税以外にもある!会社が納める税金一覧
法人には、法人税以外にも複数の税金が課されます。代表的な税金を課税の性質別にまとめました。
【法人税と合わせて納める税金】
地方法人特別税:法人税の納税義務がある法人に課される税金
特別法人事業税:法人事業税と合わせて地方へ納める税金
【取引や資産に応じて課される税金】
印紙税:各種契約書や領収書などに貼付する収入印紙代
登録免許税:各種登記にかかる税金
固定資産税:土地や建物、機械など固定資産に課される税金
【間接税※】
消費税:免税事業者以外の事業者が消費者の代わりに納める税金
※負担する人(消費者)と納める人(事業者)が異なる税金
上記のうち注意すべき税金は「消費税」です。令和5年10月より、インボイス制度が始まります。これまで消費税の免税事業者であった方の中にも、新たに課税事業者となる方もいるのではないでしょうか。インボイス制度開始によって、これまで以上に税金対策の重要性が高まります。
法人税対策ができていますか?申告はネイチャーグループにお任せください!
法人税申告は、多くの専門知識を必要とする複雑な手続きです。失敗のない法人税申告をするためにも、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。豊富な知識や経験を持つプロに相談することで、計算内容や記載内容に不備のない申告書を作成可能です。また、自社の経営状態に合った節税方法に関する相談もできます。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、各種税務申告や税務顧問を行う税務コンサルティングの他、投資に関するアドバイスも実施しており、税金対策から資産運用までをトータルサポートいたします。法人税に関してお悩みの方はぜひご相談ください。
まとめ

法人税は会社規模によって一定の税率が定められており、最高で23.2%です。資本金1億円以下の中小企業における年800万円以下の所得については、「中小法人の軽減税率の特例」により15%の税率が適用されます。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、1万件以上の実績とノウハウを生かしたご提案が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
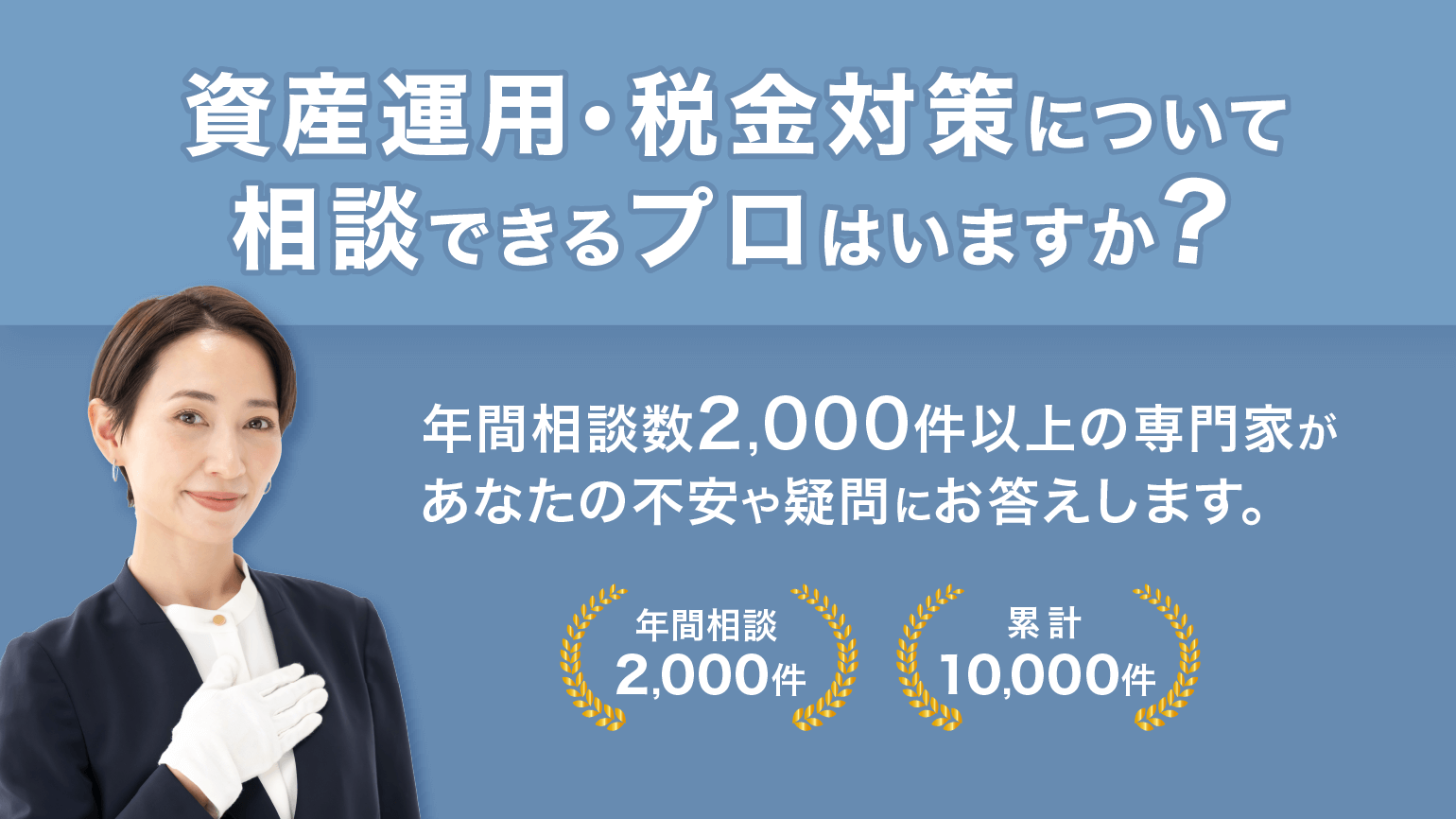
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用