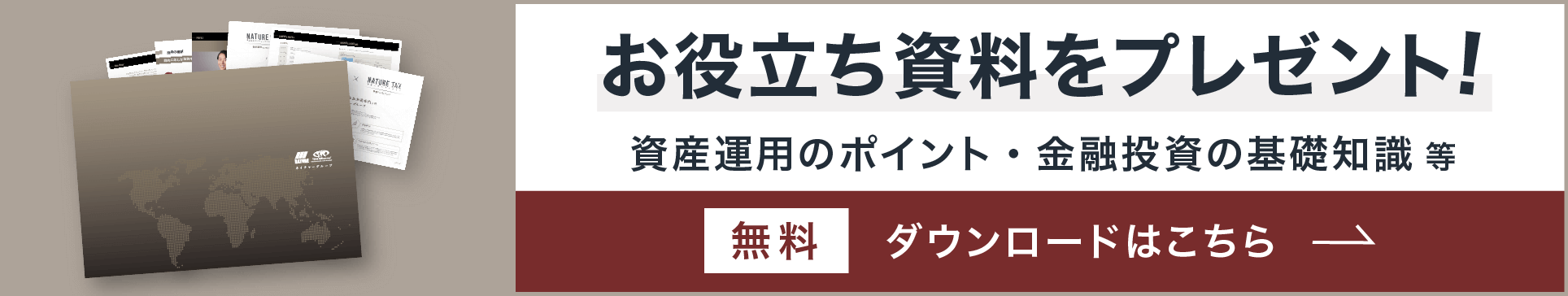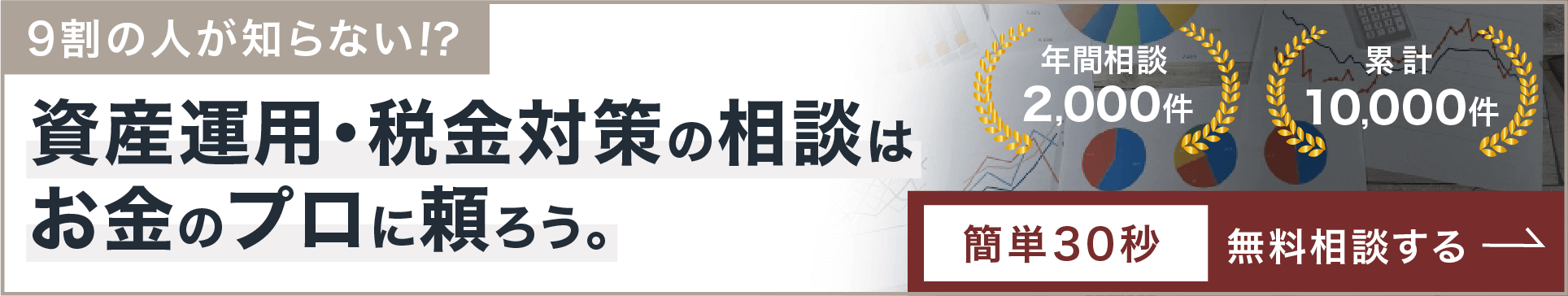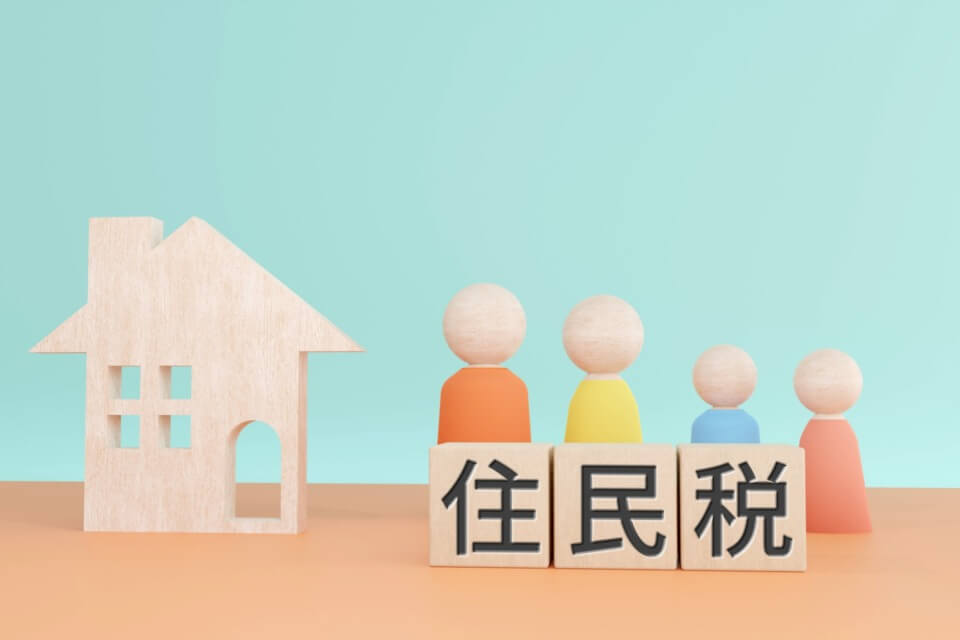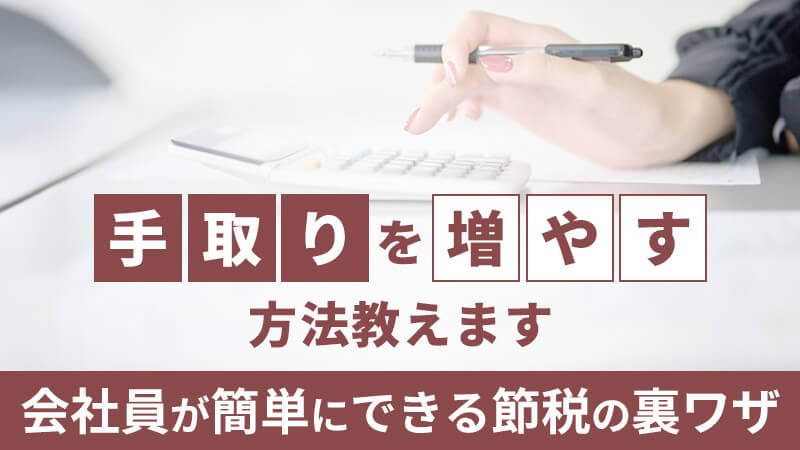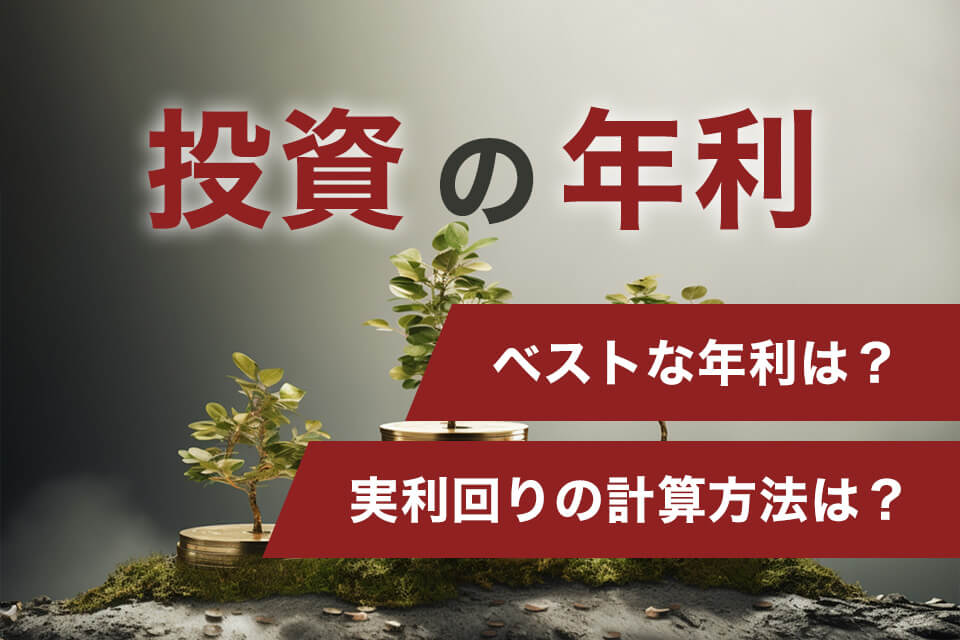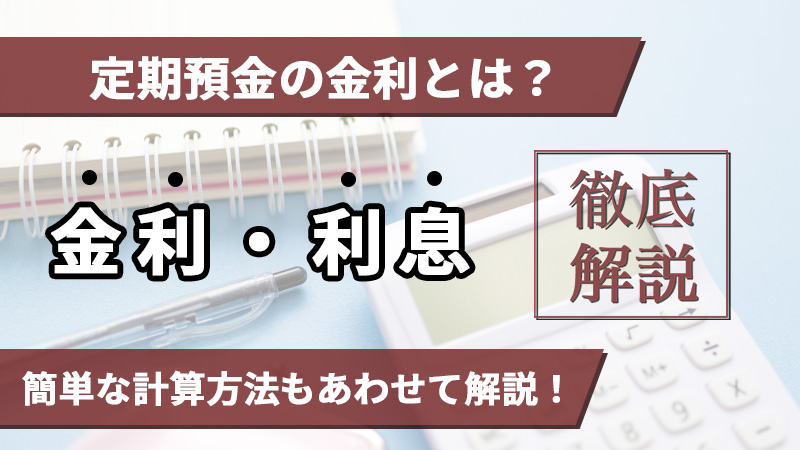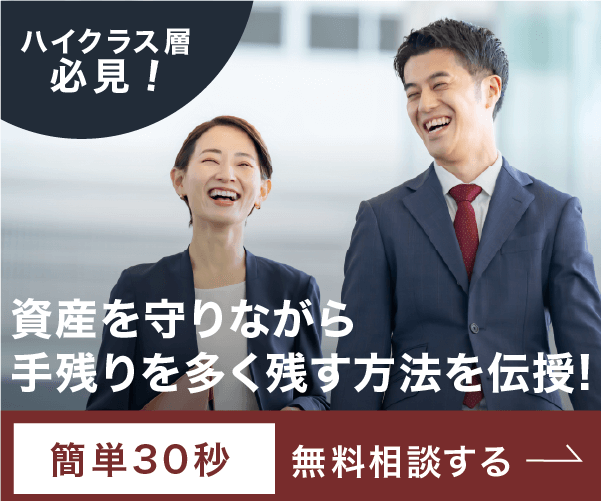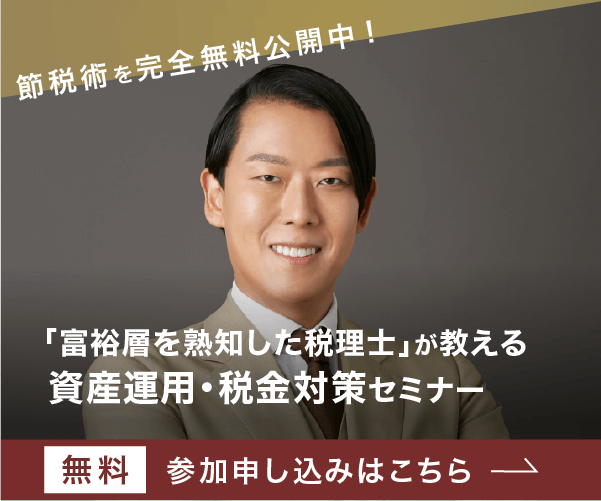![]() 2022年6月22日
2022年6月22日![]() 2024年3月15日税務
2024年3月15日税務
所得税対策におすすめの方法を全解説!知らないと損をする節税手法

所得税は個人の所得に課される税金です。「給与から差し引かれる所得税を減らせないだろうか」「せっかくの収入が税金の支払いで減ってしまう」と悩まれている方もいるのではないでしょうか。所得税の控除制度など税金の仕組みを理解することで、所得税対策が可能です。
そこでこの記事では、個人が取り組める所得税対策としておすすめの方法を紹介します。自分に合った対策方法を選ぶことで効果的に節税できるでしょう。所得税対策の注意点や、よくある質問にも焦点を当てました。
目次
所得税対策は年収が多いほど有効
所得税対策が必要かどうか気になっている方もいるのではないでしょうか。一般的には、所得が多い方ほど所得税対策を取り入れるべきとされています。
では、なぜ所得税対策は年収が多い方ほど有効なのでしょうか。その理由について詳しく見ていきましょう。
所得税率と住民税率の合算が大きくなる
日本の所得税の税率は、所得が大きくなるほど適用される税率が高くなる累進課税制度が採用されています。課税所得によって以下のように適用税率が異なります。
|
課税される所得金額 |
所得税率 |
|---|---|
|
1,000円~1,949,000円まで |
5% |
|
1,950,000円~3,299,000円まで |
10% |
|
3,300,000円~6,949,000円まで |
20% |
|
6,950,000円~8,999,000円まで |
23% |
|
9,000,000円~17,999,000円まで |
33% |
|
18,000,000円~39,999,000円まで |
40% |
|
40,000,000万円以上 |
45% |
(参考: 『所得税の税率|国税庁』)
所得に課されるのは所得税だけではありません。上記に加え10%の住民税が課されます。そのため、900万円を超えた所得に対しては所得税33%に住民税10%が加えられることで半分程度が税金として徴収されることになるのです。
生活レベルが上がることで手残りが増えにくくなる
年収が高い方ほど生活レベルが上がることで手残りが増えにくいです。例えば、住居費が他の方よりも高額になる、子どもの教育費に多額の資金を費やすなどです。また、所得が多い方ほど各種手当の受給が制限されるケースが増えます。
税負担の増加、生活レベルが上がることによる支出増加、各種手当を受けられないことで金銭的なゆとりがないという状況になる方も少なくありません。所得税対策をすることで手残りが増えるため、金銭的な余裕ができるでしょう。
所得税対策(節税対策)のおすすめ10選|活用したい税金制度

おすすめの所得税対策として紹介するのは、税金の制度を活用した方法です。iDeCoやNISA、ふるさと納税をはじめ、所得税の所得控除を利用することで節税効果が期待できます。ここでは、10個の所得税対策を紹介します。それぞれの特徴を理解して、取り組みやすい方法を選びましょう。
iDeCo(イデコ)
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、掛け金を積み立てて運用することで、60歳以降にまとまったお金を受け取れる私的年金制度です。株式や債券、REITなどの金融商品の中から運用するものを選べます。受け取り時は年金または一時金のどちらかを選択可能です。
加入者が積み立てる毎月の金額は全て所得控除となります。運用益が非課税になったり、受け取り時に控除を受けられたりと、節税メリットの大きい制度です。
NISA(ニーサ)
NISAは個人が株式や投資信託などの金融商品に投資する場合において税制上の優遇措置を受けられる制度です。2024年からNISA制度の抜本的な見直しが実施され、以下のような内容に変更となりました。
|
つみたて投資枠 |
成長投資枠 |
|
|---|---|---|
|
年間投資限度額 |
120万円 |
240万円 |
|
非課税保有期間 |
無期限化 |
無期限化 |
|
非課税保有限度額(総枠) |
1,800万円 |
|
|
1,200万円(内数) |
||
|
口座開設期間 |
恒久化 |
恒久化 |
|
投資対象商品 |
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
上場株式・投資信託等 |
|
対象年齢 |
18歳以上 |
18歳以上 |
通常は投資で得られた利益は課税対象です。しかし、NISAを利用することによって一定の条件下において利益が非課税となります。
ふるさと納税
ふるさと納税とは、都道府県や市区町村など各自治体への寄附の一種です。寄附金控除として、所得税と住民税においてそれぞれ控除が適用されます。返礼品が受け取れることもメリットのひとつです。
寄附金は、2,000円を超える部分のうち一定限度額まで、ふるさと納税を行った年の所得税とふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。控除限度額は所得税率を利用して計算するため、自身の所得によって異なる点に注意しましょう。
住宅ローン控除
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得や増改築をした場合は、年末のローン残高の0.7%を所得税額から最大13年間控除できます。なお令和4年度税制改正により、適用措置や要件について多くの点が変更され、以下のような内容となりました。
|
新築/既存等 |
住宅の環境性能等 |
借入限度額 |
控除期間 |
|
|---|---|---|---|---|
|
令和4・5年入居 |
令和6・7年入居 |
|||
|
新築住宅 買取再販 |
長期優良住宅・低炭素住宅 |
5,000万円 |
4,500万円 |
13年間 |
|
ZEH水準省エネ住宅 |
4,500万円 |
3,500万円 |
||
|
省エネ基準適合住宅 |
4,000万円 |
3,000万円 |
||
|
その他の住宅 |
3,000万円 |
0円 |
||
|
既存住宅 |
長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 |
10年間 |
|
|
その他の住宅 |
2,000万円 |
|||
住宅ローン控除には要件が設けられています。新築住宅や中古住宅、リフォーム、増改築によって要件は異なるため、詳しくは国税庁のHPを確認することをおすすめします。
(参考: 『一般住宅の新築等をした場合|国税庁』)
(参考: 『認定住宅の新築等をした場合|国税庁』)
(参考: 『中古住宅を取得した場合|国税庁』)
(参考: 『増改築等をした場合|国税庁』)
医療費控除
医療費控除とは、原則として1年間で10万円を超える医療費を支払った場合に適用される所得控除です。納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象になります。
・医療費控除の計算式
その年に支払った医療費-保険などの補てん金額-10万円(※)
※総所得金額200万円未満の場合はその5%相当額
医療費控除の対象になる医療費とは、医療機関に支払った治療費だけではありません。治療のために購入した市販薬や病院への交通費なども含まれます。なお医療費の領収書は、5年間保存する必要があります。
セルフメディケーション税制
納税者本人や生計を一にする配偶者・親族のために、1万2,000円以上の対象医薬品を購入した場合は、セルフメディケーション税制が受けられます。医療費控除との併用はできないため、医療費控除の対象となる費用が10万円に満たない場合は、セルフメディケーション税制の利用を検討するとよいでしょう。
また適用を受けるには、健康の維持や疾病の予防に関する一定の取り組みを行っている必要があります。一定の取り組みとは、健康診断や予防接種、メタボ健診、がん検診などです。
生命保険料控除
生命保険料控除とは、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払ったときに利用できる所得控除のひとつです。
計算方法や控除限度額は、平成24年1月1日以後に契約した保険(新契約)と、平成23年12月31日以前に契約した保険(旧契約)で異なります。それぞれの控除額の計算方法は下表の通りです。
新契約・・・・・・平成24年1月1日以後に契約した生命保険、介護医療保険、個人年金保険
|
年間の支払保険料 |
控除額 |
|---|---|
|
2万円以下 |
支払保険料の全額 |
|
2万円超 4万円以下 |
支払保険料×1/2+1万円 |
|
4万円超 8万円以下 |
支払保険料等×1/4+2万円 |
|
8万円超 |
一律4万円 |
旧契約・・・・・・平成23年12月31日以前に契約した生命保険、個人年金保険
|
年間の支払保険料 |
控除額の計算方法 |
|---|---|
|
2万5,000円以下 |
支払保険料の全額 |
|
2万5,000円超 5万円以下 |
支払保険料等×1/2+1万2,500円 |
|
5万円超 10万円以下 |
支払保険料等×1/4+2万5,000円 |
|
10万円超 |
一律5万円 |
生命保険料控除の控除限度額は、生命保険と介護保険、個人年金保険の3つにかかるものを合わせて12万円です。旧契約のみの場合は、10万円が控除限度額です。
地震保険料控除
地震保険料控除は、納税者本人が地震保険契約や経過措置が適用される長期損害保険契約の保険料を支払った場合に適用されます。それぞれの控除額は、次の通りです。
|
年間の支払保険料 |
控除額 |
|---|---|
|
5万円以下 |
支払金額の全額 |
|
5万円超 |
一律5万円 |
・経過措置が適用される長期損害保険料
|
年間の支払保険料 |
控除額 |
|---|---|
|
1万円以下 |
支払金額の全額 |
|
1万円超 2万円以下 |
支払金額×1/2+5,000円 |
|
2万円超 |
1万5,000円 |
地震保険料と長期損害保険料の両方の支払いがある場合は、その合計(上限5万円)が控除額となります。
扶養控除
控除対象となる扶養親族がいる場合は、所得控除のひとつである扶養控除の適用が可能です。控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無などによって異なります。
|
区分 |
概要 |
控除額 |
|---|---|---|
|
一般の扶養親族 |
16歳以上の扶養親族 |
38万円 |
|
特定扶養親族 |
19歳以上23歳未満の扶養親族 |
63万円 |
|
老人扶養親族(同居老親等以外) |
70歳以上で同居老親等に該当しない扶養親族 |
48万円 |
|
老人扶養親族(同居老親等※) |
70歳以上で同居老親等に該当する扶養親族 |
58万円 |
※老人扶養親族のうち納税者本人や配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、常に同居している方
基礎控除
基礎控除とは、所得金額が2,500万円以下である場合に差し引ける所得控除です。以前は全ての納税者が一律38万円の控除を受けられる制度でしたが、改正により所得金額ごとに控除額が分かれました。
|
納税者本人の合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
|
2,400万円以下 |
48万円 |
|
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
|
2,500万円超 |
0円 |
サラリーマン(給与所得者)は「特定支出控除」を利用できる
特定支出控除とは、給与所得者が業務のために支払った費用が多い場合に控除できる制度です。特定支出控除を利用することで、経費として支払った金額を所得金額から差し引ける可能性があります。
特定支出控除を適用できるのは、特定支出に当たる支出が給与所得控除の1/2を超える場合です。「給与所得控除×1/2」を超えた金額を、給与所得控除後の所得金額から差し引けます。
特定支出に該当する費用は、通勤費や職務上の旅費、転居費、資格取得費などです。なおいずれの費用であっても、勤務先が証明したものに限られる点に注意しましょう。
特殊なケースで利用できる所得税対策の裏ワザ3選
以下の特殊なケースに該当する方は、税負担を軽減できる可能性があります。
- 株取引で損失が発生した
- 配偶者と離婚または死別した
- 災害・盗難にあった
それぞれの特殊なケースを詳しく見ていきましょう。
株取引で損失が発生した
上場株式などの取引で損失が発生した場合には、その年の配当所得と損益通算することが可能です。損益通算とは、利益と損失を相殺することです。
利益と損失を合算して所得計算することで利益を減らせるため、税負担を軽減できます。損益通算で控除しきれない損失がある場合、翌年から3年間は繰り越して控除することが可能です。
配偶者と離婚または死別した
配偶者と離婚または死別した場合、寡夫控除で節税することが可能です。寡婦控除とは、夫と死別、離婚したものの再婚しておらず、親などの扶養親族や生計を一にする子がいる人の税負担を軽減するというものです。
寡婦になった理由が離別または死別なのか、年齢によって控除額が変わります。
災害・盗難にあった
災害や盗難などにあった場合、雑損控除や災害減免法による税金の軽減・免除の2種類の控除を受けられます。
雑損控除とは、災害関連の支出を控除できるというものです。例えば、災害により住宅の取り壊しが必要になった場合、かかった費用は災害関連支出として控除対象になります。
また、盗難や横領などの被害にあった場合も雑損控除の対象です。ただし、通常の生活に必要な財産に限られているので注意が必要です。
災害減免法による税金の軽減・免除とは、住宅や家財の時価が災害によって2分の1以上の損失を受けた場合に直接税金を軽減・免除してもらうというものです。
雑損控除と災害減免法のどちらを受けるかは自身で自由に選択できます。
個人事業主の所得税対策のポイント

所得税は、収入から経費を差し引いた所得金額を基準にして税額を計算します。個人事業主の節税は、所得金額をいかに減らすかがポイントのひとつです。ここでは、所得金額を減らす方法の他、節税対策としての法人化についても解説します。
青色申告をする
青色申告とは、確定申告の手法のひとつであり、多くの税制上のメリットが受けられる制度です。青色申告制度を利用するには、「正規の簿記の原則」による記帳をしている必要があります。「正規の簿記の原則」とは、年末時点で損益計算書や貸借対照表を作成できる複式簿記による処理を求めるものです。
青色申告のメリットには、最大65万円の青色申告特別控除(所得控除)や青色事業専従者給与があります。青色事業専従者給与とは、配偶者や親族に支払う一定の給与を必要経費に計上できる制度です。
経費を漏らさず計上する
事業を営む上で支払った費用は必要経費として計上できます。経費を漏らさず計上することで、所得金額の減額が可能です。必要経費として計上できる主な費用には、次のようなものがあります。
|
勘定科目 |
例 |
|---|---|
|
租税公課 |
消費税や個人事業税、固定資産税 |
|
荷造運賃 |
商品発送のための段ボールや運送料 |
|
水道光熱費 |
水道代や電気代 |
|
旅費交通費 |
電車やバスの費用、宿泊費 |
|
通信費 |
電話代やインターネット料金 |
|
広告宣伝費 |
新聞やテレビによる広告費用 |
|
接待交際費 |
取引先との飲食代やお中元・お歳暮の費用 |
|
消耗品費 |
文房具など消耗品購入費用(10万円未満) |
|
減価償却費 |
事業用の建物や機械装置などの減価償却資産にかかるもの |
|
福利厚生費 |
会社が支払った従業員の食事代や健康診断の費用 |
小規模企業共済を利用する
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主が利用できる積立型の退職金制度です。積み立てた掛金は、退職金または年金の形式で受け取れます。掛金は月額1,000円~7万円の間で自由に決められ、全額が所得控除の対象です。
ただし、240か月未満で任意解約した場合は解約手当金が支払った掛金の額を下回るといったデメリットもあります。特に1年未満での任意解約では解約手当金が受け取れないため、注意が必要です。小規模企業共済を利用する際は、長期的な視野で慎重に検討する必要があります。
少額減価償却資産の特例を利用する
事業用に高額な資産を購入した場合、減価償却資産として扱われることが原則です。減価償却資産は種類ごとに耐用年数が定められており、耐用年数内で一定額を減価償却費として経費計上します。
ただし青色申告をしている場合は「少額減価償却資産の特例」を利用することで、30万円未満の減価償却資産について、その購入額の一括計上が可能です。なお、青色申告をしていない場合でも、10万円未満の資産であれば一括計上できます。
法人化を検討する
一般的に事業の利益が800万円を超えたときが、法人化するタイミングであると言われています。事業利益が多い方は、所得税よりも法人税として納めるほうが節税できる可能性があるためです。
ただし、事業以外の所得がある場合や利用する所得控除によっては、適切なタイミングが異なることもあります。法人化を検討する際は、税理士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
所得税対策をするときの注意点

所得税対策をするのはよいですが、いくつか注意したい点があります。誤りのない申告をするために、あらかじめ確認しておきましょう。専門的な税務知識が必要になるため、不安を感じる方は税理士に相談することをおすすめします。
サラリーマンは年末調整だけでは利用できない制度がある
サラリーマンの場合、年末調整で所得税の申告が完了することが多くありますが、確定申告をしなければ利用できない制度があります。医療費控除やセルフメディケーション税制、特定支出控除、寄附金控除などは、確定申告が必要です。また住宅ローン控除についても、適用を受ける初年度に限り確定申告の必要があります。
共働きは収入の高いほうが扶養控除を利用する
夫婦共働きの場合、より収入が高いほうが扶養控除を利用したほうが高い節税効果を得られる可能性があります。これは、所得金額が高いほど所得税率も高くなるためです。扶養控除は、年末調整時に提出する「扶養控除等(異動)申告書」へ必要事項を記入することで適用が受けられます。
過度な節税対策で不要な出費を増やさない
所得税対策は状況に合った取り組みを行う必要があります。節税のために過剰な住宅ローンを契約したり、控除限度額を超えるふるさと納税をしたりするのは、本末転倒になりかねません。十分な効果を見込める節税対策なのか、慎重に検討した上で取り組みましょう。
所得税対策に関するよくある質問

多くの所得税対策では確定申告が必要ですが、間違った申告をした場合には「延滞税」や「加算税」を納付しなければならない可能性があります。正しい申告のために、不明な点は事前に確認しておきましょう。ここでは、所得税対策に関するよくある質問を紹介します。
Q.所得税の計算方法は?
A.所得税の計算には、大きく分けて4つの段階があります。それぞれの段階による計算方法は、次の通りです。
(1)「所得金額=収入-必要経費」
所得税は、その年の収入全てに課せられるわけではありません。収入を得るために必要になった経費を、収入から差し引きましょう。
なお、所得は性質ごとに10種類に分かれており、それぞれ収入や必要経費の範囲などが定められています。
(2)「課税所得=所得金額-所得控除額」
所得金額から、基礎控除や配偶者控除などの所得控除額を差し引いた金額が、課税所得です。
(3)「所得税額=課税所得×税率-速算表上の控除額」
課税所得を基準として、所得税の速算表で適用される税率を乗じ、同じく速算表上の控除額を差し引きます。なお、所得税の税率は、所得額が増えるほど高くなる超過累進税率です。
(4)「納税額=所得税額-税額控除」
最後に、計算した所得税額から住宅ローン控除などの税額控除の金額を差し引いて納税額を求めます。
Q.サラリーマンは所得税をどのように納付すればいいですか?
Aサラリーマンの所得税は、「源泉徴収制度」によって本人に代わり勤務先が申告納税しています。源泉徴収は、毎回確定した税金を納めているわけではなく、払いすぎた分については年末調整で払い戻される仕組みです。
源泉徴収が行われているサラリーマンの多くは、年末調整によって所得税の申告・納付の手続きが不要になります。
Q.確定申告の申告期間や申告方法を教えてください
A.確定申告は、原則として2月16日から3月15日までが申告期間です。申告期限を過ぎても確定申告は可能ですが、「無申告加算税」や「重加算税」といった罰則金の支払いが発生する可能性があります。また青色申告をする方が2年連続で申告期限を過ぎた申告をした場合は、青色申告の承認が取り消されるため注意しましょう。
確定申告書は、税務署の窓口に直接提出する以外にも、e-Taxと呼ばれるインターネットでの申告や郵送でも提出が可能です。
Q.富裕層(個人)におすすめの所得税対策は何ですか?
A.不動産投資は節税効果の大きい所得税対策と言えます。不動産は築年数の経過とともに資産価値が減少します。これを減価償却と言いますが、減価償却期間中は会計上の赤字を計上することで所得を減らすことによって所得税の負担を軽減できるのです。所得の多い富裕層ほど受けられる恩恵が大きいでしょう。
Q.保険加入は所得税対策になりますか?
A.保険に加入した場合は、生命保険料控除や地震保険料控除などの各種控除を利用すれば所得税対策になります。しかし、所得税対策を目的とする保険加入はおすすめしません。保険に加入する必要がある方にのみおすすめする所得税対策と言えます。
Q.不動産投資(アパート経営)は所得税対策になりますか?
A.所得税対策になります。「Q.富裕層(個人)にお勧めの所得税対策は何ですか?」でも触れましたが、減価償却という会計上の赤字を計上することで所得を減らすことによって所得税の負担を軽減できます。
節税を意識した資産運用で資産を増やす
所得税では所得金額が増えるほど税率が高くなる累進課税制度が採用されているため、収入が多い方ほど所得税対策の効果は高くなります。高所得の経営者や会社員、所得が多い個人事業主の方は、所得税対策に取り組むと多くのメリットを得られるでしょう。
例えば不動産投資は、不動産の譲渡所得にかかる税率と所得税率の差を利用することで節税効果が生まれるため、高所得の方に適した節税対策のひとつとして知られています。
所得税対策ならネイチャーグループにお任せください!
資産運用に取り組むことで、より効率良く所得税を節税できる可能性があります。ただし資産運用による所得税対策には、多くの専門知識が必要です。難しい場合は、専門家である税理士のサポートを受けてみてはいかがでしょうか。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、資産運用に特化した税理士グループです。各種申告書の書類作成や提出も行っていますので、節税対策や資産運用を検討されている方はぜひお声がけください。
まとめ:所得税対策をして将来の生活に備えよう

所得税対策としておすすめするのは、iDeCoやNISAなどの税金の制度を活用した方法です。その他にも所得税の所得控除制度を利用することで、節税効果が期待できます。個人事業主における節税対策としては、所得金額をいかに減らすのかがポイントです。青色申告の利用や、漏れのない経費計上を心掛けるとよいでしょう。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、確定申告などの申告手続きから資産運用まで幅広いご相談を承っています。所得税対策で悩まれている方は、ぜひこの機会にお問い合わせください。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
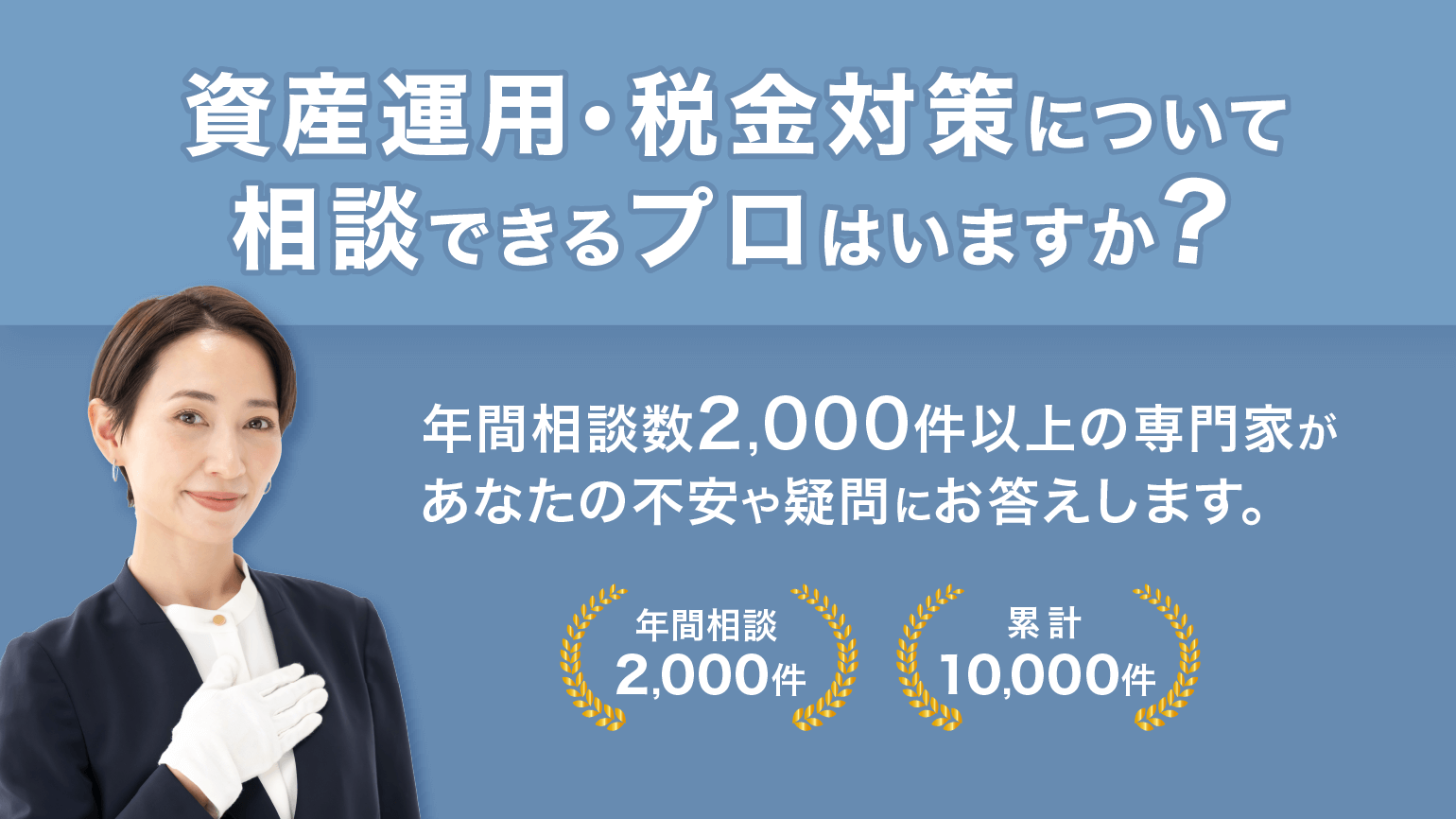
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用