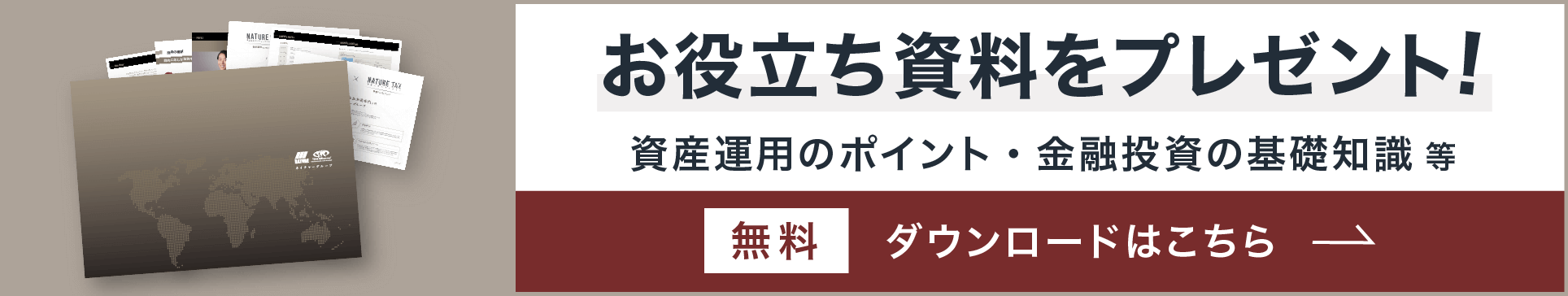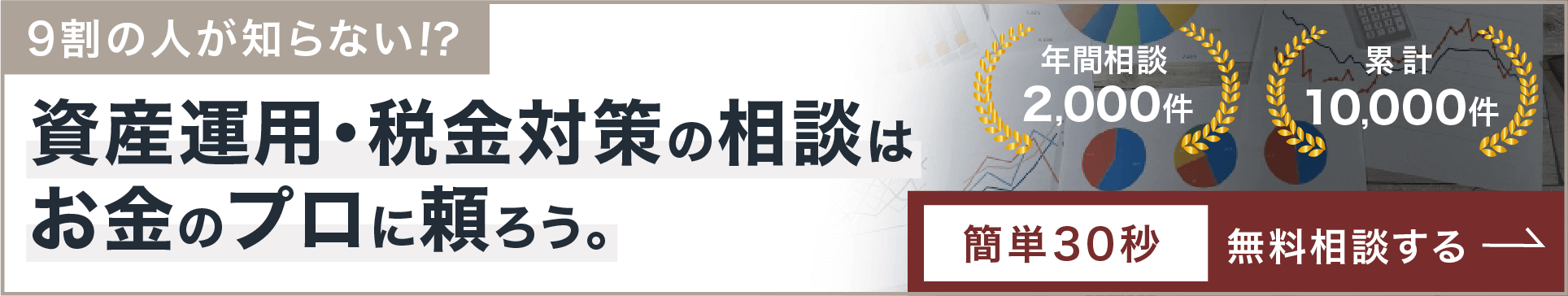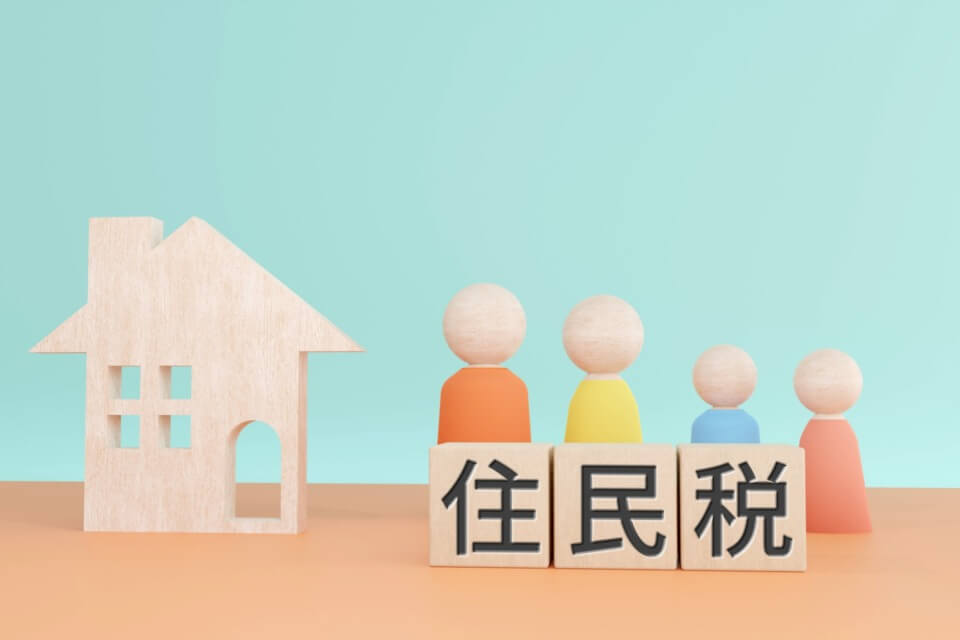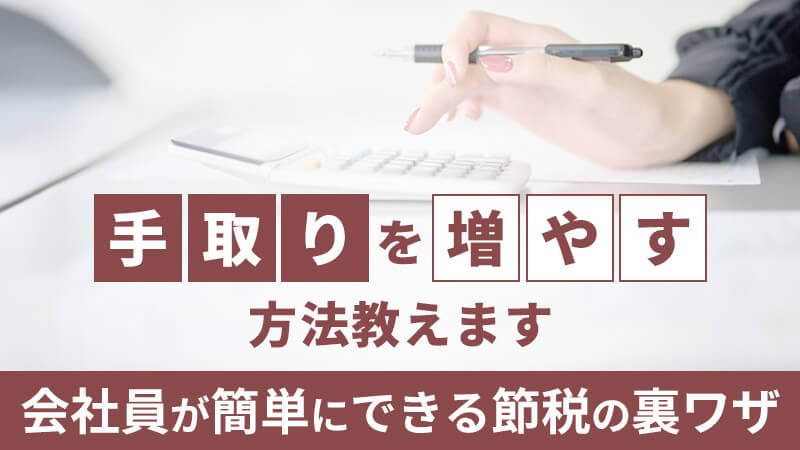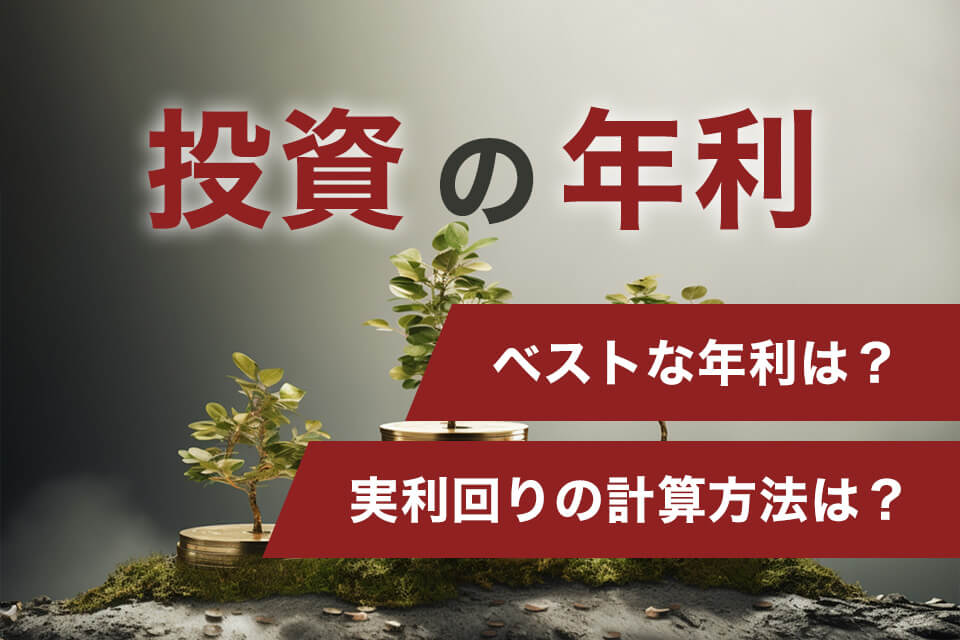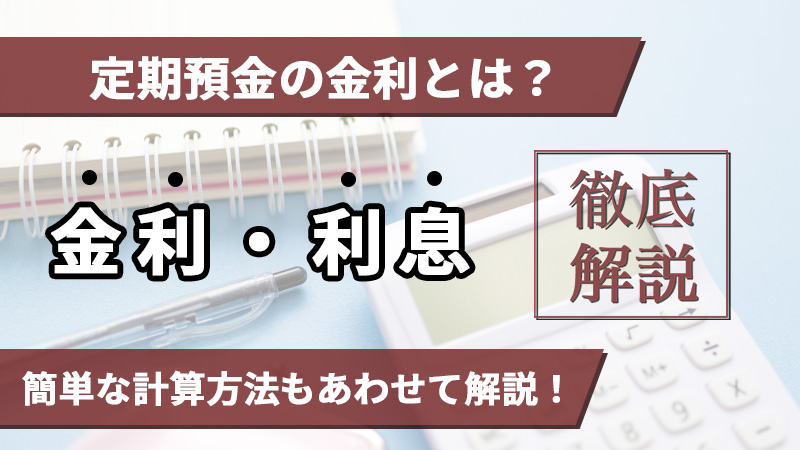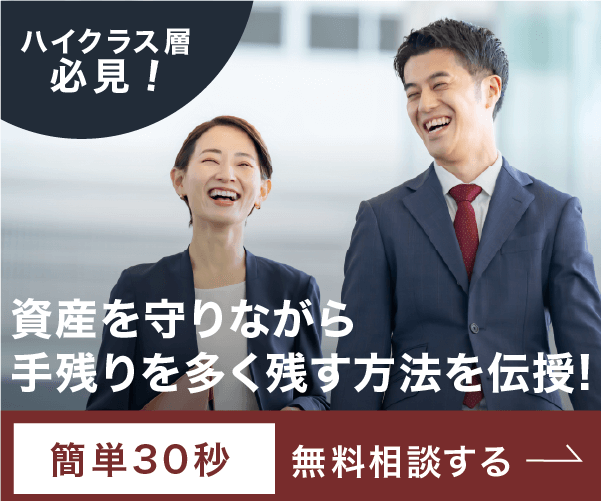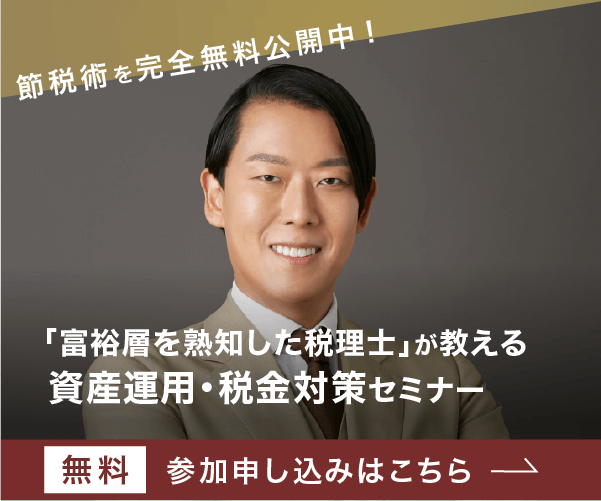![]() 2022年7月27日
2022年7月27日![]() 2025年4月24日税務
2025年4月24日税務
所得税のシミュレーション!年収別の手取り額や計算方法を紹介

所得税のシミュレーション!年収別の手取り額や計算方法を紹介
給与明細の収入や事業の売上は、その金額に応じて所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれます。この所得税や住民税、社会保険料はしっかりと正確な金額を申告・支払わなければなりません。
少しでも支払いが不足していると、督促やペナルティを課せられる可能性もあります。もし支払い額を用意できなければ、いかなる理由でも罰則を課せられてしまいます。
そこで、前もってどれくらいになりそうか把握できれば、安心して納税できるでしょう。
この記事では、収入ごとの所得税や手取り金額をシミュレーションして紹介します。計算方法も紹介しますので、自分のケースで所得税や手取り金額などがいくらになるのかシミュレーションしてみてください。
目次
年収別!所得税や手取り金額のシミュレーションができる早見表
「税金の計算が面倒」「自身の手残り金額がいくらか簡単に知りたい」という方は、早見表で手軽に確認できます。
ただし、早見表で分かるのはあくまで目安の金額です。
収入から差し引かれる税額や社会保険料は個人により異なります。概算であることを念頭に置きながら参考にしてみてください。
会社員における所得税・手取り金額のシミュレーション
会社員における所得税や手取り金額のシミュレーションをしてみましょう。
この記事では、以下の条件に当てはまる会社員を想定して早見表を作成しました。
- 配偶者、扶養親族なしの独身者
- 介護保険第2号被保険者に該当
- 所得控除は基礎控除のみ
- 健康保険料・厚生年金保険料は東京都の金額を使用
- 百の位以下切り捨て
実際には、扶養親族の有無や住宅ローンの適用などで控除額が増えるため、手残り金額も増えると考えましょう。
|
年収 |
所得税 |
手残り金額 |
|---|---|---|
|
300万円 |
57,400円 |
241万1,900円 |
|
400万円 |
89,400円 |
320万370円 |
|
500万円 |
145,700円 |
393万2,600円 |
|
600万円 |
212,100円 |
465万1,500円 |
|
700万円 |
335,300円 |
534万2,100円 |
|
800万円 |
495,800円 |
598万9,400円 |
|
900万円 |
655,700円 |
658万3,400円 |
|
1,000万円 |
850,100円 |
724万6,100円 |
|
2,000万円 |
3,744,100円 |
1,287万1,800円 |
|
3,000万円 |
7,843,700円 |
1,767万7,900円 |
|
4,000万円 |
11,906,400円 |
2,256万8,900円 |
|
5,000万円 |
16,280,700円 |
2,714万8,300円 |
個人事業主における所得税・手取り金額のシミュレーション
続いて、個人事業主における所得税・手取り金額のシミュレーションをしましょう。
この記事では、以下の条件に当てはまる個人事業主を想定して早見表を作成しました。
- 配偶者、扶養親族なしの独身者
- 介護保険第2号被保険者に該当
- 所得控除は基礎控除のみ
- 青色申告65万控除適用
- 個人事業税課税対象外の事業者
- 国民健康保険料・国民年金保険料は東京都の金額を使用
- 百の位以下切り捨て
|
経費差し引き後の金額 |
所得税率 |
所得税 |
手残り金額 |
|---|---|---|---|
|
300万円 |
5% |
約7万円 |
233万4,000円 |
|
400万円 |
10% |
約14万円 |
307万5,000円 |
|
500万円 |
10% |
約23万円 |
379万円 |
|
600万円 |
20% |
約40万円 |
442万2,000円 |
|
700万円 |
20% |
約59万円 |
504万5,000円 |
|
800万円 |
20% |
約77万円 |
566万9,000円 |
|
900万円 |
20% |
約95万円 |
629万1,000円 |
|
1,000万円 |
23% |
約116万円 |
689万6,000円 |
|
2,000万円 |
33% |
約437万円 |
1,262万2,000円 |
|
3,000万円 |
40% |
約863万円 |
1,732万5,000円 |
|
4,000万円 |
40% |
約1,271万円 |
2,224万1,000円 |
|
5,000万円 |
45% |
約1,721万円 |
2,674万3,000円 |
会社員と個人事業主とで、同じ収入でも支出額は大きく異なる点に注意しましょう。
所得税対策を考慮した、保有資産のさらなる向上を望まれる方に、資産運用・税金対策に特化した個人専門のコンサルファームが正しい節税方法をお伝えしています。税務効果も考慮した資産運用について気になる方は、ぜひ一度ネイチャーグループへご相談ください。
\【期間限定】今だけAmazonギフトカードプレゼント!/
所得税の計算シミュレーション!会社員・個人事業主のケース別
年収や売り上げと、実際に手元に入ってくる金額は異なります。手残り金額を増やすためには、どのような費用が差し引かれるのかをしっかりと把握し、適切な税金対策を施すことが大切です。
最初は会社員と個人事業主のケースに分けて、手残り金額の計算方法や差し引かれる費用の内訳についてご紹介します。
会社員のシミュレーション
会社員の年収から差し引かれる費用は、主に税金と社会保険料です。手取り金額は「給与収入金額-(社会保険料+税金)」で求めます。具体的な内容と金額の目安は以下の通りです。
|
差し引かれる税金 |
所得税 |
|
差し引かれる社会保険料 |
健康保険 |
例として、年収500万円を想定した場合の手取り金額をみていきましょう。
年収500万円の場合、税金や社会保険料は以下の通り。
- 所得税:約15万円
- 住民税:約25万円
- 社会保険料:約68万円
年収500万円の場合、「年収500万円-(社会保険料約68万円+所得税約15万円+住民税約25万円)=約392万円」という計算式から、手取り金額は約392万円と算出できます。
ただし社会保険料や税金の金額は、家族構成や経済状況、加入している社会保険の種類により異なるので注意しましょう。
個人事業主のシミュレーション
個人事業主の手取り金額を計算する際は、税金や保険料を売り上げから差し引きます。
また、会社員における給与所得控除の代わりに経費の差引と青色申告特別控除を活用できます。(要件有り)
経費控除後の所得から差し引かれる費用は、以下の通り。
|
差し引かれる税金 |
所得税 住民税 消費税(該当する方のみ) 個人事業税(該当する方のみ) |
|
差し引かれる社会保険料 |
国民年金保険料 国民健康保険料 |
では、例として売上600万円(経費控除後の所得500万円)での手取り金額を見ていきましょう。
上記のケースで発生する税金や保険料の金額は、以下の通り。
- 所得税:約22万9,000円
- 住民税:約32万6,000円
- 国民健康保険料:約45万7,000円
- 国民年金保険料:約19万9,000円
所得500万円の個人事業主の手取り金額の目安は、約379万円です。
具体的な計算式は、「所得500万円-(国民健康保険料約45万7,000円+国民年金保険料約19万9,000円+所得税約22万9,000円+住民税約32万6,000円)=約379万円」となります。
青色申告特別控除適用の有無や家族構成によって、納める保険料や税金の金額は異なるため注意してください。
なお、個人事業税は所得290万円以下または課税対象外の事業、消費税は課税売上高が1,000万円以下であれば発生しません。
手順に沿って解説!所得税の計算方法は4ステップ
所得税は、個人が1月1日〜12月31日の間で得た所得に対して課せられる税金です。会社員であれば基本的に源泉徴収で支払い、個人事業主であれば確定申告をします。
所得税にはさまざまな控除があり、最適な節税制度を利用するためにも、所得税の計算方法や税制度、控除内容を理解することが大切です。ここでは、所得税の計算方法を手順に沿って解説します。
ステップ1.給与所得控除や必要経費を差し引く
所得税額を求める際に用いるのは、年収や売り上げではなく所得です。会社員は年収から給与所得控除を差し引きます。具体的な金額は以下の通りです。
|
給与などの収入額 |
給与所得控除額(令和2年分以降) |
|---|---|
|
162万5,000円以下 |
55万 |
|
162万5,000円超180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
|
180万円超360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
|
360万円超660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
|
660万円超850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
|
850万円超 |
195万円(上限) |
(参考: 『給与所得控除|国税庁』)
個人事業主は、売り上げから経費を差し引きます。計上できるのは、業務で使用した費用です。例えば、オフィスで使用するパソコンの通信費や取引先への移動費が該当します。証明として、領収書やレシートの保管が義務付けられているため、処分しないように注意しましょう。
ステップ2.所得控除を適用する
所得から所得控除額を差し引き、課税所得を求めましょう。家庭の経済状況が反映される重要なポイントであるため、適用できるものがあるかしっかりと確認しましょう。
所得控除の種類は、以下の通りです。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
基礎控除は令和2年分より38万円から48万円に引き上げられ、合計所得金額が2,500万円以下の全ての納税者に適用されます。
合計所得金額が、2,400万円以下であれば控除額は48万円ですが、2,400万円超〜2,500万円以下であれば段階的に控除額が下がるので注意しましょう。
他の控除は、既定の要件に合致する方のみが対象です。
|
納税者本人の合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
|
2,400万円以下 |
48万円 |
|
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
|
2,500万円超 |
0円 |
(参考: 『基礎控除|国税庁』)
ステップ3.課税所得に税率をかける
課税所得に税率をかけて控除額を差し引き、算出税額を求めます。速算表は以下の通りです。
|
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
|---|---|---|
|
195万円未満 |
5% |
0円 |
|
195万円以上330万円未満 |
10% |
9万7,500円 |
|
330万円以上695万円未満 |
20% |
42万7,500円 |
|
695万円以上900万円未満 |
23% |
63万6,000円 |
|
900万円以上1,800万円未満 |
33% |
153万6,000円 |
|
1,800万円以上4,000万円未満 |
40% |
279万6,000円 |
|
4,000万円以上 |
45% |
479万6,000円 |
(参考:『所得税の税率|国税庁』)
ステップ4.税額控除をマイナスする
では最後に、税額控除を差し引きましょう。
算出税額から直接マイナスできるため、大きな節税効果を期待できます。
|
税額控除の種類 |
適用要件 |
|---|---|
|
配当控除 |
国内企業からの配当金が収入に含まれる場合 |
|
外国税額控除 |
外国で得た所得があり、すでに外国で所得税が課税されている場合 |
|
住宅借入金等特別控除 |
住宅の新築や増改築のために日本国内で住宅ローンを組んだとき |
|
住宅耐震改修特別控除 |
一定条件を満たす住宅に耐震改修をした場合 |
|
住宅特定改修特別税額控除 |
既定の改修工事をした場合 |
|
政党等寄附金特別控除 |
政治活動へ寄付をしたとき |
|
認定NPO法人等寄附金特別控除 |
対象の団体に寄付をしたとき |
|
公益社団法人等寄附金特別控除 |
対象の団体に寄付をしたとき |
所得税以外に年収から差し引かれる項目の詳細
年収や売り上げから差し引かれるのは所得税だけではありません。具体的には、住民税や厚生年金保険料などが差し引かれます。
ここでは、所得税以外に差し引かれる項目について理解を深めていきましょう。出ていくお金が分かることで、より本来の手残り金額に近い金額を算出できます。
住民税
住民税とは、1月1日時点で住所のある自治体に納める税金です。
住民税の金額は所得割と均等割に分かれており、所得割は前年1月1日〜12月31日の所得に対して一律10%、均等割は基本的に5,000円と定められています。自治体によって住民税の決まり方は異なるため、正確な金額を知りたい方は自治体に問い合わせてみましょう。
会社員であれば会社が給与から天引きし自治体に納め、個人事業主の場合には、自治体から送られてくる納付書で自ら納めます。
厚生年金保険料
厚生年金保険は、厚生年金に加入する会社の70歳未満の従業員などが入る公的年金です。
保険料は会社と従業員が折半し、従業員が支払う分は、会社側が給与から天引きし納付します。
従業員が支払う金額は、「標準報酬月額×9.15%」と「標準賞与額×9.15%」です。そのため、給与と賞与の金額が上がるほど、厚生年金保険料も上がることを覚えておきましょう。
健康保険料・介護保険料
健康保険は、医療費を一部負担するために加入する公的医療保険です。
保険料は会社と従業員で負担し、従業員が支払う分は会社と折半であれば「標準報酬月額×健康保険料率」で計算されます。加入する健康保険組合などによって保険料率は異なるため、正確に計算したい方は職場の担当者に聞いてみましょう。
一方で40歳〜64歳までの従業員であれば、健康保険料と一緒に介護保険料が給与から天引きされます。介護保険料は「標準報酬月額×介護保険料率」で算出された額を、会社と従業員で折半して納めます。
雇用保険料
雇用保険とは、失業給付や育児休業給付金といった仕事がなくなったときのための公的保険です。
会社と従業員で負担し、従業員側の支払い分は「賃金総額×雇用保険料率」となります。
賃金総額とは、毎月の賃金の総額と賞与、手当などを合わせた金額です。農林水産や建築業など業種によって保険料率は異なるため、注意しましょう。
所得税や手取り金額などの算出はシミュレーションツールがおすすめ
所得税や手取り金額を求めるには、計算式に当てはめて自分で導き出す必要があります。とはいえ、項目が多いうえに複雑な計算になりやすいため、時間がかかってしまうでしょう。
そこで所得税や手取り金額などの算出は、シミュレーションツールを活用してください。
シミュレーションツールは、入力欄に金額を記載するだけで具体的な額を瞬時に自動算出してくれます。
自分での計算が難しそうだと感じたなら、ぜひシミュレーションツールで計算しましょう。
毎月の給与にかかる所得税が変動する理由
毎月の給与が変わっていないにもかかわらず、所得税の納税額が変動する理由が気になる方もいるのではないでしょうか。
基本的に厚生年金や健康保険、介護保険、雇用保険などの社会保険料は、毎年4月~6月の給与の平均を元に算出されます。そのため、4月〜6月に残業代や休日出勤、基本給の増額などがあると、社会保険料が高くなり所得税が変動する仕組みです。
さらに扶養親族が増えた場合には扶養控除額が適用されるため、所得税は下がります。控除額などの税制改正も、所得税が変動する要因のひとつです。
会社員も個人事業主にもおすすめの税金対策3選
所得税は、会社員の給料や個人事業主の売上から差し引かれる費用の中で大きな割合を占めます。
納める税金を減らして手残り金額を増やすには、所得税の税金対策が必須といえるでしょう。ここでは、会社員と個人事業主のいずれも利用できる節税制度や税制優遇制度を紹介します。
- 住宅ローン控除を適用する
- 税制優遇制度を利用して資産形成する
- ふるさと納税をする
住宅ローン控除を適用する
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入したり住宅の増改築をしたりしたときに適用できる税額控除です。
所得税額から直接差し引けるため、高い節税効果が期待できます。最大控除額は年間35万円です。
ただし、適用するには一定の要件を満たす必要があり、居住開始時期によって控除期間や控除率は異なります。(下記は一例です)
|
項目 |
概要 |
|---|---|
|
居住開始時期 |
令和4年1月1日から令和5年12月31日 |
|
控除期間 |
13年(新築等) |
|
控除率 |
0.7% |
|
最大控除額 |
①エネルギー消費性能向上住宅 28万円 ②特定エネルギー消費性能向上住宅 31万5千円 ③認定住宅 35万円 |
(参考: 『認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁』)
税制優遇制度を利用して資産形成する
iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)で資産運用するのも方法のひとつです。
積立金額を所得控除できたり利益が非課税になったりするため、納める税金を抑えながら資産を増やせます。
・iDeCo:積立金は全額所得控除の対象。資産運用の利益は非課税
・新NISA(つみたて投資枠):年間120万円、非課税保有期間無期限
・新NISA(成長投資枠):年間240万円、非課税保有期間無期限
※令和6年よりNISAから新NISAに変更
ふるさと納税をする
ふるさと納税は、自治体に税金を納める(寄付する)ことで、寄附金控除を適用できる制度です。自治体からの返礼品として果物や肉といった名産品を受け取れるのも魅力的です。控除額は以下の計算式で求めます。
・所得税:(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
・住民税(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×10%
・住民税(特例分):(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)または(住民税所得割額)×20%
なお、ふるさと納税には控除上限額があるので注意しましょう。
上限額を超えた分は自己負担となります。上限額は年収や家族構成によって異なるため、詳しくは総務省の公式サイトをご確認ください。
(参考: 『ふるさと納税ポータルサイト|総務省』)
個人事業主におすすめの税金対策3選
個人事業主は、所得控除や税額控除以外にも適用できる節税方法があります。家族構成や事業の経営状況を確認の上、自身のケースに合う税金対策を導入しましょう。ここでは、個人事業主に適した税金対策を3つ紹介します。
- 青色申告控除を受ける
- 業務関連の経費を漏れなく計上する
- 特例制度を活用する
青色申告控除を受ける
個人事業主の確定申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。それぞれの概要と相違点は以下の通りです。
|
|
青色申告 |
白色申告 |
|---|---|---|
|
控除額 |
10万円~最大65万円 ※電子申告・電子帳簿保存の場合 |
無し |
|
記帳方法 |
複式帳簿 |
単式帳簿 |
|
事前申請 |
必要 |
不要 |
|
必要書類 |
・確定申告書B ・青色申告決算書 |
・確定申告書B ・収支内訳書 |
主な違いは控除額で、青色申告では最大65万円の控除を適用できます。また、青色申告の場合、損失が出た際の繰越控除や欠損金の繰り戻しも可能です。
なお65万円の特別控除を受けるためには、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告をしなければなりません。複式簿記であっても、税務署窓口での提出や郵送の場合には控除額が55万円になります。
業務関連の経費を漏れなく計上する
経費が増えると課税所得が減るため、所得税の減額につながります。経費にできるものの一例は以下の通りです。
|
種類 |
具体例 |
|---|---|
|
通信費 |
携帯電話料金、切手代、プロバイダー料金 |
|
交通費 |
電車代、タクシー代、バス代 |
|
消耗品費 |
文房具、事務用品、作業着、10万円未満のパソコン |
|
租税公課 |
固定資産税、自動車税 |
|
地代家賃 |
事務所の賃料 |
プライベートと仕事で併用しているものは、使用割合で家事按分して申告できます。例えば、プライベート用の携帯電話を仕事でも頻繁に使用する場合や自宅の一部をオフィスとして使用しているケースは、仕事用に該当する部分の経費計上が可能です。
特例制度を活用する
税制優遇制度(特例制度)の中でも、個人事業主が利用しやすいのは「少額減価償却資産の特例」です。通常の減価償却と特例制度には以下の違いがあります。
・通常の減価償却:10万円以上20万円未満のものは3年で均等償却する
・少額減価償却資産の特例(青色申告の場合のみ利用可能):10万円以上30万円未満のものを一括で経費として処理する
パソコンや事務機器のような比較的高価なものを購入する際に適用することで、経費計上できる金額が大きくなるため、節税効果を期待できます。
令和5年施行の税制改正に注意
令和5年4月1日に「令和5年度税制改正」が施行されました。令和5年4月以降、特に気を付けたい改正点は住宅ローン控除について以下の3つです。
・適用期限が4年延長され、2025年12月31日までに入居した人が対象
・2050年カーボンニュートラルの実現に向け、省エネ性能の高い住宅の取得を促す
・引き続き、控除率を改正前の1%から0.7%とする
控除を適用できる対象者や対象物、控除額が縮小されているため、会社員や個人事業主にとって厳しい税制改正となりました。確定申告に難しさを感じる方は専門家と相談しながら進めましょう。
所得税などの税金対策はネイチャーグループにお任せください!
手残り金額を増やす税金対策は複数あるものの、個人で計算するのは難しいケースもあるでしょう。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)に直接ご相談いただければ、無料でシミュレーションします。
当グループには、相談・案件数年間2,000件、累計1万件の実績があります。経済状況の確認から税金対策のご提案、確定申告の書類作成までトータルサポートが可能です。
納める税金を減らして手元に残る資産を増やせるように、税務に関する豊富な知識と経験を持つ税理士が全面的にサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。
\所得税の有効な対策方法とは?/
まとめ:所得税や手取り金額はシミュレーションしておおよそを把握しておこう
仕事で得た収入の中から手残り金額を計算する際は、税金や保険料を差し引きます。特に所得税は占める割合が大きく、所得が増えるほど税率が上がるのが特徴です。手元の資産を増やすには、税金対策をして納める税金を減らすといいでしょう。
また、しっかりとシミュレーションを行い、おおよその金額を把握しておくことが大切です。
なお、税金対策にお困りの際は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。
国内最大級のコンサルファームだからこそ可能な幅広いサポート体制が強みです。豊富な知識と経験を持つ税理士が、税金対策のご提案から確定申告書類の作成までトータルサポートします。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
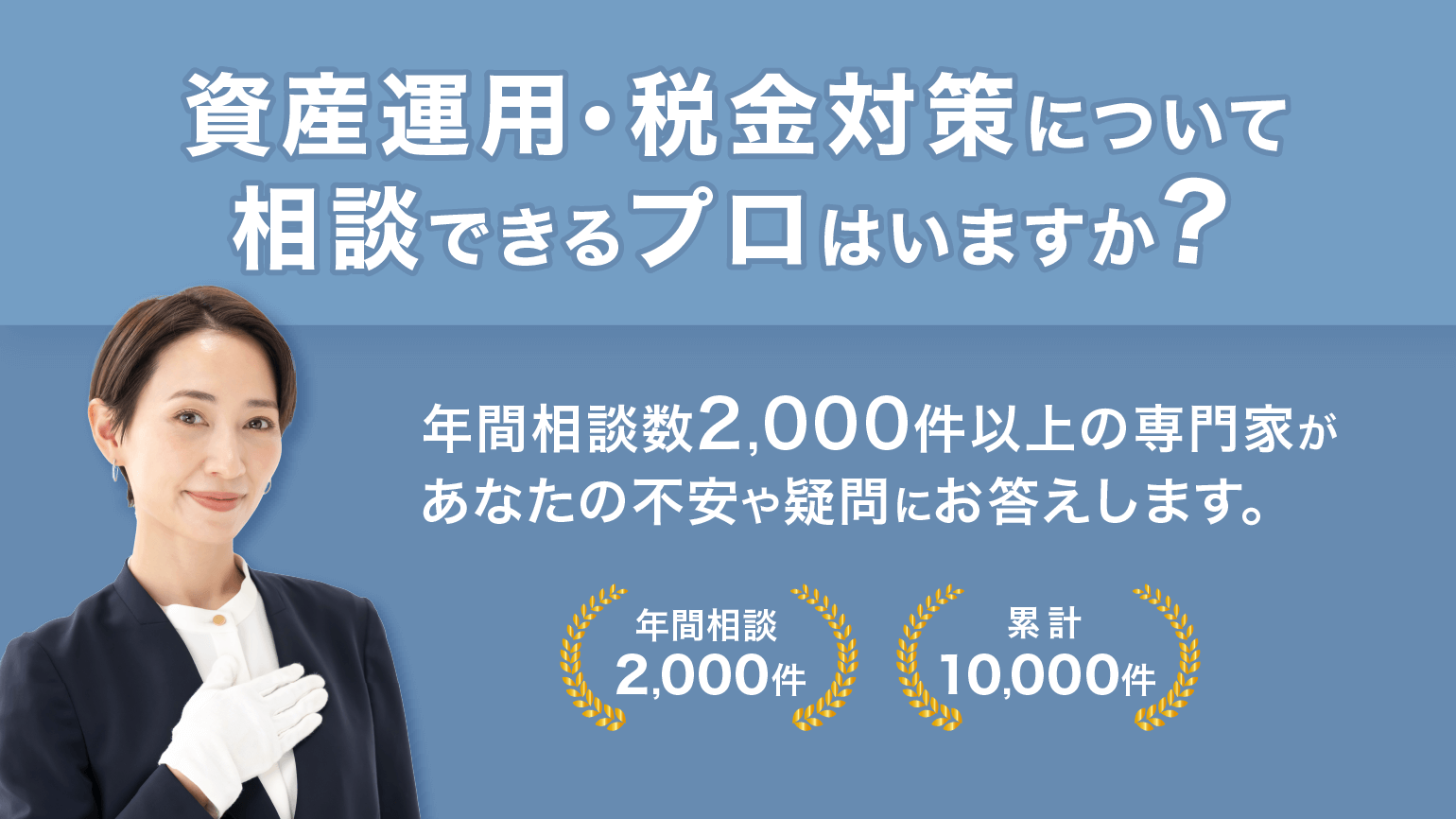
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。

芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。宅地建物取引士資格保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA取得。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用